静態データベース作成運用とは、複写先システムのデータベースを利用してデータベースの静止状態を作成し、参照系のバッチ処理などを実行する運用方法です。
静態データベース作成運用の流れを以下に示します。
操作の手順
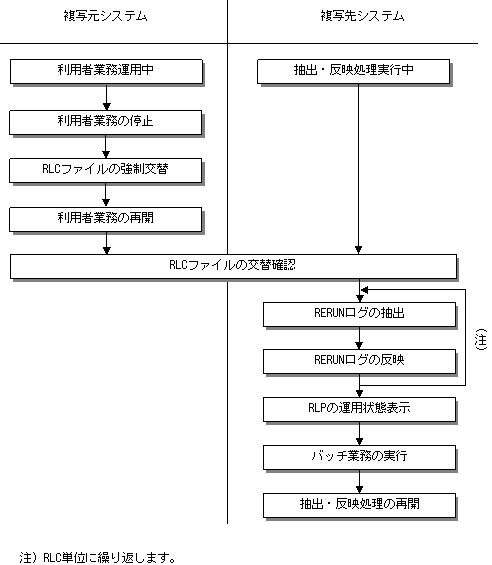
注意
ロードシェア運用で静態データベース作成運用を実施する場合は、以下の点に注意してください。
複数のロググループにまたがるトランザクションに対して保証された静態データベースを作成する場合は、関連する複数のロググループのRLPに対して、静態データベース作成運用を実施します。
関連するノードごとに静態データベース作成運用を実施します。
ポイント
静態データベースの作成単位はRLPです。
交替メッセージで確認したRLC通番までのRERUNログの抽出・反映処理完了を確認してからRERUNログの反映を停止します。
複数のロググループにまたがるトランザクションに対して保証された静態データベースを作成したい場合には、関連する複数のロググループのRLPに対して、運用操作を行います。
複写先システムのデータベースが静止状態の間も、複写元システムでのRERUNログの取得を継続することが可能です。この場合、反映処理を再開するまでは、RERUNログ抽出ファイルにRERUNログを蓄積することを推奨します。
次回の静態データベース作成する地点までRERUNログの運用を継続する場合は、バッチ処理中にRLCの容量不足を起こさないために、定期的にRERUNログの抽出を実行し、RERUNログ抽出ファイルを蓄積してください。バッチ処理終了後には蓄積したすべてのRERUNログ抽出ファイルを対象にRERUNログの反映処理を実行してください。
静態データベース作成後に、RERUNログの運用を継続する必要がない場合は、RLPを終了オフラインにしてからRLPを再作成します。RLPの再作成の詳細については“5.20 RLPの再作成”を参照してください。
参照
RLCファイルの強制交替については“2.2.2 RLCファイルの強制交替”を参照してください。
RLCファイルの交替確認については“2.2.1 RLCファイルの交替確認”を参照してください。
RERUNログの抽出については“2.3.2.2 RERUNログの抽出”を参照してください。
RERUNログの反映については“2.3.4 RERUNログの反映”を参照してください。
RLPの運用状態表示については“3.2.1 RLPの運用情報表示”を参照してください。