Systemwalker Centric Manager GEEが、SVPMと連携するための定義について説明します。SVPMを利用しない場合は、定義の必要はありません。
SVPM連携のための作業の概要を“SVPM連携の定義概要”に、作業の手順を“SVPM連携のための作業内容”に示します。なお、“SVPM連携の定義概要”の括弧付き数字は、“SVPM連携のための作業内容”の作業順番と対応しています。
SVPMが監視するハードウェア異常を監視したい場合は、被監視システムとしてSVPMを定義する必要があります。
図2.4 SVPM連携の定義概要
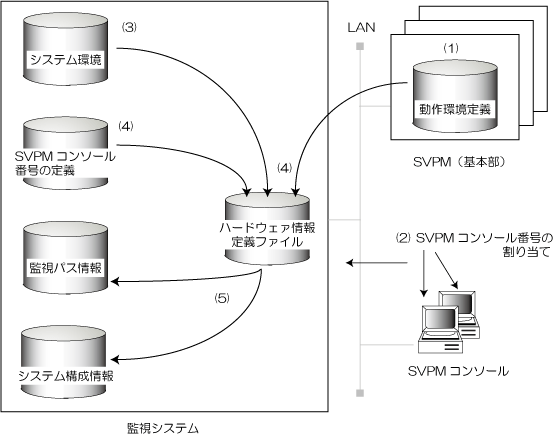
作業の順序 | 作業名 | 作業内容 | 作業分担 |
|---|---|---|---|
(1) | SVPM基本部の動作環境定義 | SVPM導入時の作業です。ハードウェア導入時の調整、ハードウェア構成情報の定義、その他必要な定義作業を行います。 ・ハード監視画面のセキュリティ機能を有効する場合 SVPM基本部の制御レジスタ0を、以下のように設定します。 ・SVPM基本部と運用管理サーバで時刻同期を行う場合 SVPM基本部の制御レジスタ1を、以下のように設定します。 備考) | 技術員 (CE) |
(2) | SVPMコンソール番号の割り当て | SVPM導入時の作業です。接続するSVPMコンソールに対して、それぞれのコンソールを識別するための番号を決めます。 | |
(3) | システム環境の定義 | 【Solarisの場合】 動作確認が必要な項目 【Linuxの場合】 動作確認が必要な項目 | 運用管理者 |
(4) | SVPMコンソール番号の定義 | (2)で運用管理サーバに割り当てたSVPMコンソール番号を、SVPMコンソール番号定義ファイルに設定します。 | |
(5) | 監視パスの定義およびシステム構成情報の登録 | (4)のハードウェア情報定義ファイルをもとに、SVPMの正確な情報のひな形を作成します。それを参照して、監視パスの定義およびシステム構成情報の登録を行います。 |
運用管理サーバへのコンソール番号の割り当てについて
“SVPM連携のための作業内容”の(2)の作業について、注意事項を以下に示します。
Systemwalker Centric Manager GEEが導入される運用管理サーバには、0以上7以下のコンソール番号を割り当ててください。
1台のSVPM(基本部)に接続するSVPMコンソールは、すべて一意なコンソール番号である必要があります。したがって、以下のように1台のSVPM(基本部)に複数のSystemwalker Centric Manager GEEが接続する場合は、それぞれ異なるコンソール番号を割り当ててください。
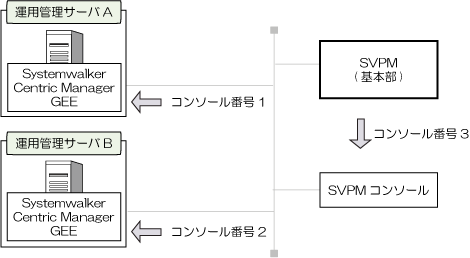
Systemwalker Centric Manager GEEは、複数のSVPMと接続して監視・操作ができます。一つのSystemwalker Centric Manager GEEに複数のSVPMを接続する場合には、各SVPMでSystemwalker Centric Managerに割り当てるコンソール番号を同じにしてください。
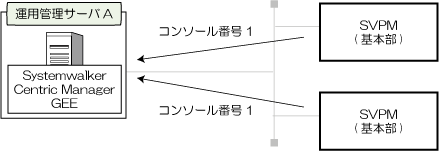
SVPMおよびPC-Xとの接続方式について【Linux版】
“SVPM連携のための作業内容”の(3)の作業について、注意事項を以下に示します。
Linux版ではSVPMとの接続に、rshまたはsshのどちらかを選択して使用します。
また、関連ソフトウェアのPC-X(運用管理クライアントからの[ハード監視制御]ウィンドウの起動で使用)は、運用管理サーバとの接続にrexec、rshまたはtelnetのいずれかを選択して使用します。
それぞれに以下の注意事項があります。どの接続方式を使用するか、環境に合わせて選択してください。
Red Hat Enterprise Linux 8以降では、rshはOSの標準機能としてインストールされません。
運用管理サーバの導入環境がRed Hat Enterprise Linux 8以降の場合、EPEL(エンタープライズ Linux 用の拡張パッケージ)の下記パッケージをインストールしてください。
rsh
rsh-server
連携するSVPMがssh接続に対応している必要があります。
SVPMのssh対応状況については、技術員にお問い合わせください。
Red Hat Enterprise Linux 8以降では、rexecはOSの標準機能としてインストールされません。
運用管理サーバの導入環境がRed Hat Enterprise Linux 8以降の場合、“rshを使用する場合(SVPMまたはPC-Xの接続)”に記載のパッケージをインストールしてください(該当パッケージにrexecも含まれます)。
なお、複数のSVPMと連携する場合、接続方式は連携するSVPMごとに決めます。各SVPMとの接続方式は、“SVPM連携のための作業内容”の(4)で定義します。
また、PC-Xの接続方式は“PC-X起動環境の定義”で定義します。
本節では、運用管理者が行う、以下の作業について説明します。