利用者に対する認証と識別について、説明します。
利用者に対する認証と識別は、以下の2つの方式があります。
Symfoware Serverが認証を行う方式
OSが認証を行う方式
認証は、CONNECT文実行時、または、CONNECT後にSET SESSION AUTHORIZATION文を指定して利用者を変更した場合に行います。
CONNECT文の指定方法については、“11.3 CONNECT文”を参照してください。
SET SESSION AUTHORIZATION文の指定方法については、“11.11 SET SESSION AUTHORIZATION文”を参照してください。
なお、以降の説明ではCONNECT文を中心に説明します。SET SESSION AUTHORIZATION文についても同様の認証方式なので、CONNECT文の説明をSET SESSION AUTHORIZATION文に置き換えて解釈してください。
Symfoware Serverへの接続時に認証を行う方式です。
利用者が実行できるのは、アプリケーションからのSQL文の実行です。
CONNECT文を使用した接続形式には以下の2つがあります。
OSのログイン名で接続する場合
データベース専用利用者名で接続する場合
ログイン時にOSが認証を行い、Symfoware Serverはこの識別情報をOSから引き継ぐ方式です。
同一サーバ内での共用メモリ通信(システム内通信)を用いてアプリケーションやRDBコマンドを実行する場合は、利用者は事前にサーバにログインしておく必要があります。この場合は、すでにOSの認証、識別が完了していることから、Symfoware Serverの利用者として登録されているかをチェックします。
サーバ内にログインして、そこから同一サーバ内のSymfoware Serverに対してCONNECT文を実行する場合には、CONNECT文に利用者名とパスワードを指定しないでアプリケーション実行時のログイン名を利用して接続することができます。これは、認証がOSに対してログイン時に終了しているからです。
この場合には、CONNECT文実行時には、そのログイン時の利用者がSymfoware Serverに対して(OSにログインできる利用者として)登録されているかのみをチェックします。
図2.3 OSが認証を行う方式
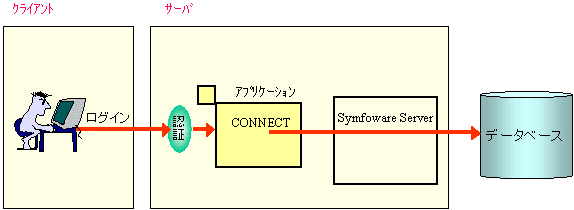
それぞれの場合の認証とパスワードの管理について以下の表に示します。
認証の方式 | CONNECT文での接続方法 | 認証を行う箇所 | パスワード |
|---|---|---|---|
Symfoware Serverが認証を行う | CONNECT OSのログイン名 | Symfoware Server | OS |
CONNECT データベース専用利用者名 | Symfoware Server | Symfoware Server | |
OSが認証を行う | CONNECT 利用者名指定なし | OS (注) | OS |
注) Symfoware Serverに利用者として登録されている必要があります。
認証に成功した場合または、失敗した場合の利用者の対応については、“12.1 認証時の対応”を参照してください。
パスワードは、長期間同じものを使用していると、他人に盗まれる可能性が高くなります。また、頻繁にパスワードを変更した場合、管理が難しくなります。そこで、パスワードのエージング制御によって、適度にパスワードの保守を行います。パスワードのエージング制御とは、パスワードが一定期間のみ有効であり、これを監視し、利用者に通知する機能です。
パスワードのエージング制御には、以下があります。
パスワードは、システムのセキュリティ強度に合わせて、適切なパスワード期限を設定する必要があります。
パスワードの期限は、以下の項目を考慮して決定します。
パスワードに使用できる文字種
パスワードに最低限必要なバイト数
パスワードの誤り時の待ち時間
パスワードを連続して失敗できる回数を設定します。
データベース専用利用者が、この回数を超えてパスワードを誤った場合、そのパスワードは自動的にシステムがロック(使用不可の状態)します。
この回数を設定することにより、不正な利用者から攻撃を受けた場合にも、システムを防御することができます。
パスワードを変更してからある程度の時間が過ぎると、パスワードの変更催促期間に入り、利用者にパスワードの変更を促します。パスワードの有効期限までにパスワードが変更されない場合は、利用者のパスワードは無効になります。
パスワードのエージング制御は、管理者がSET SYSTEM PARAMETER文を使ってセキュリティパラメタをチューニングすることで行います。
セキュリティパラメタのチューニングの詳細については、“2.5 セキュリティパラメタのチューニング”を参照してください。