ここでは、以下に示す保管フォルダの構成変更について説明します。
保管フォルダの追加
第一階層の保管フォルダの格納場所(物理パス)の変更<Windows版のみ>
保管フォルダの環境設定変更(保管フォルダのプロパティ情報の変更、保管フォルダ名の変更、移動、複写)
保管フォルダのアクセス権の変更
保管フォルダの削除
注意
複数ユーザが同時に、保管フォルダの構成変更を行うことはできません。
保管フォルダ名や帳票の管理情報の設定には、使用できない文字がありますので注意してください。
| 使用できない文字については、“運用手引書”を参照してください。 |
保管フォルダを追加する場合に考慮すべき事項と、保管フォルダの追加方法について説明します。
保管フォルダを追加する場合は、次の事項について事前に考慮が必要です。
保管フォルダ配下に格納される帳票の有効期限を設定することができます。有効期限を超え、「有効期限を過ぎたら削除対象にする」が設定されている帳票は、以下の帳票一括削除の処理対象となります。
リストクリーナ-サーバ(Windows版リスト管理サーバの場合のみ)
lvatdellコマンド(Solaris 版リスト管理サーバの場合のみ)
リストクリーナ-クライアント(マイ コンピュータの場合のみ)
なお、有効期限は登録からの日数で指定します。保管フォルダを追加する前に、有効期限を設定するかどうか、および設定する日数を何日にするかについて、決めておく必要があります。
| 有効期限の設定による帳票の削除については、“1.5 フォルダ/帳票の監視と削除”を参照してください。 |
リスト管理サーバにおいて保管フォルダを追加する場合は、追加したフォルダを帳票の振り分け先として定義するか検討が必要です。
振り分け先として定義する場合は、以下の振り分け先定義の更新が必要です。
受信フォルダの振り分け先の定義を更新します。
| 受信フォルダの振り分け定義の変更方法については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 |
帳票出力時に指定している帳票の格納先の設定を変更します。
| 帳票の格納先の設定については、“運用手引書”を参照してください。 |
Solaris版において、帳票の格納先として物理パスが指定されている場合、以下の手順で保管フォルダの物理パスと論理パスの対応関係を定義してください。対応定義がされていない状態で、物理パスを指定して帳票の登録を行った場合は、登録エラーとなります。
lvlstpthコマンドで、保管フォルダのパス対応表一覧を作成し、追加した保管フォルダに関する定義が存在しないことを確認します。
lvsetpthコマンドで保管フォルダの物理パスと論理パスの対応関係を定義します。
| lvlstpthコマンド、またはlvsetpthコマンドについては、“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
保管フォルダを追加するには、以下に示す方法があります。
リストナビによる追加
F5CWKEEP.EXEコマンドによる追加 <Windows版のみ>
lvsetfolコマンドによる追加 <Solaris版のみ>
保管フォルダの種類によって利用できる追加方法は以下のように異なります。
追加方法 | リスト管理サーバの保管フォルダ | マイ コンピュータの保管フォルダ | ||
|---|---|---|---|---|
Windows版 | Solaris版 | |||
リストナビによる追加 | ○ | ○ | ○ | |
コマンドによる追加 | F5CWKEEP.EXEコマンド | ○ | × | × |
lvsetfolコマンド | × | ○ | × | |
○:利用可能
×:利用不可
以下、各追加方法について説明します。
リストナビで、フォルダの階層を確認しながら、保管フォルダを追加することができます。
| リストナビで、リスト管理サーバ上の保管フォルダを追加する方法については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 リストナビで、マイ コンピュータ上の保管フォルダを追加する方法については、“操作手引書 利用者編”を参照してください。 フォルダの追加が行えるユーザのアクセス権については、“運用手引書”を参照してください。 |
注意
Windows版の場合、リスト管理サーバで保管フォルダとして使用しているフォルダを、マイ コンピュータの保管フォルダとして定義しないでください。リスト管理サーバの管理情報を破壊する恐れがあります。
リスト管理サーバの保管フォルダを追加する場合、F5CWKEEP.EXEコマンドが利用できます。追加する保管フォルダの数が多い場合などは、スクリプトに組み込んで使用することも可能です。
追加する保管フォルダごとに、格納する帳票の有効期限や、セパレータ削除の有無、抜き出し検索を有効にするかなど、細かい設定が行えます。
F5CWKEEP.EXEコマンドは、管理者で実行できます。
保管フォルダを追加する手順を以下に示します。
「保管フォルダ情報ファイル」を作成します。その際に、[FolderInformation]セクションのCreateFolderには「1」(保管フォルダを作成する)を設定します。
1.で作成した「保管フォルダ情報ファイル」を、F5CWKEEP.EXEコマンドにより登録します。
| 「保管フォルダ情報ファイル」の記述方法、およびF5CWKEEP.EXEコマンドの詳細は“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
Solaris 版において、リスト管理サーバの保管フォルダを追加する場合、lvsetfolコマンドが利用できます。
コマンドのオプションに、作成する保管フォルダのディレクトリ名、保管フォルダ名、作成者名、および「保管フォルダ情報ファイル名」を指定します。「保管フォルダ情報ファイル」には、保管フォルダに設定する定義を記述します。
ただし、コマンドの実行にはスーパーユーザの権限が必要です。
保管フォルダを新規追加する手順を以下に示します。
「保管フォルダ情報ファイル」を作成し、追加する保管フォルダの定義を記述します。
ディレクトリ名、保管フォルダ名、作成者名、および1.で作成した「保管フォルダ情報ファイル」を、lvsetfolコマンドにより登録します。
| lvsetfolコマンドの詳細、および「保管フォルダ情報ファイル」の定義の記述方法については、“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
(2) 第一階層の保管フォルダの格納場所(物理パス)の変更 <Windows版のみ>
第一階層の保管フォルダの格納場所(物理パス)を変更する手順について説明します。Windows版のみの機能です。
第一階層の保管フォルダの格納場所を変更するには、F5CWCKFP.EXEコマンドを使用します。手順に従って作業を実施することにより、別サーバへのデータ移行や、保管フォルダ格納先の別ディスクへの変更ができます。
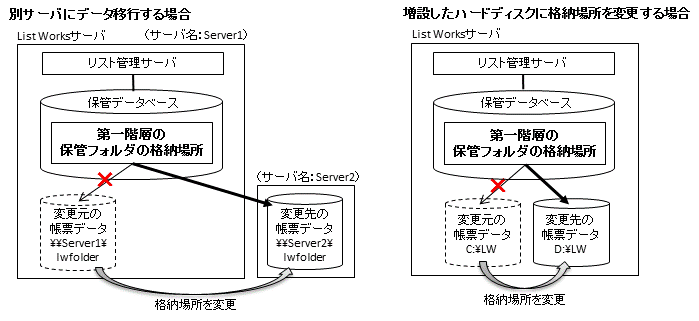
【リスト管理サーバ環境設定】ダイアログボックスの【データベース】タブに、保管フォルダの格納場所を変更したい保管データベースの情報が設定されており、データベースに接続できることを確認します。
| 【リスト管理サーバ環境設定】ダイアログボックスについては、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 |
【スタート】メニューの【管理ツール】-【サービス】からサービスマネージャを起動し、サービス「List Works」を停止します。
保管データベースの破損時に備えて、バックアップをします。
| 保管データベースのバックアップについては、“1.6.1 帳票と印刷資源の退避 <Windows版>”の“手順8:保管データベースの退避”を参照してください。 |
エクスプローラなどを使用して、変更元のフォルダの階層構造は崩さずにフォルダに格納されているファイルすべてを、変更先の保管フォルダの格納場所にそのまま複写します。
保管フォルダパス情報ファイルは、F5CWCKFP.EXEコマンドで保管フォルダの格納場所を変更するときに指定するCSV形式のファイルです。
保管フォルダパス情報ファイルは、以下の手順で作成します。
F5CWCKFP.EXEコマンドを実行して、保管フォルダパス一覧ファイルを作成します。
| F5CWCKFP.EXEコマンドの詳細については、“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
参考
保管フォルダパス一覧ファイルに出力された内容は、保管フォルダパス情報ファイルの「変更前の保管フォルダの格納場所」に相当します。
保管フォルダパス一覧ファイルを、任意のフォルダに退避します。
退避した保管フォルダパス一覧ファイルを編集し、保管フォルダパス情報ファイルとします。
保管フォルダパス情報ファイルの編集規約と記述形式を以下に示します。
文字コードは、シフトJISコードです。
保管フォルダの格納場所は、ダブルクォーテーションで囲みます。
フォルダ名には、以下の文字を使用できません。
半角 \ / : , ; * ? " < > |
全角 ~
"変更前の保管フォルダの格納場所","変更先の保管フォルダの格納場所"
:
:190バイト以内で指定します。必須項目です。
190バイト以内で指定します。必須項目です。なお、「変更先の保管フォルダの格納場所」がすでに保管フォルダの格納場所として定義されている場合は、 “手順6 F5CWCKFP.EXEコマンドの実行”でエラーとなります。
"C:\LW","C:\LW\DATA1" "D:\LW","D:\LW\DATA2" "\\Server1\lwfolder","\\Server2\lwfolder"
F5CWCKFP.EXEコマンドを実行し、第一階層の保管フォルダの格納場所を変更します。
| F5CWCKFP.EXEコマンドの詳細については、“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
【スタート】メニューの【管理ツール】-【サービス】からサービスマネージャを起動し、サービス「List Works」を開始します。
受信フォルダのプロパティに定義されている帳票の振り分け先定義を、リストナビで変更します。
| リストナビで受信フォルダの帳票振り分け先定義を変更する方法については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 |
既存の保管フォルダに対して行う、以下の変更について説明します。
保管フォルダの環境設定を変更する
保管フォルダ名を変更、移動、複写する(リスト管理サーバの保管フォルダのみ)
保管フォルダの環境設定を変更する方法は、以下のとおりです。
リストナビによる設定変更
F5CWKEEP.EXEコマンドによる設定変更 <Windows版のみ>
lvsetfolコマンドによる設定変更 <Solaris版のみ>
保管フォルダの種類によって利用できる変更方法は以下のように異なります。
環境設定変更方法 | リスト管理サーバの保管フォルダ | マイ コンピュータの保管フォルダ | ||
|---|---|---|---|---|
Windows版 | Solaris版 | |||
リストナビによる変更 | ○ | ○ | ○ | |
コマンドによる変更 | F5CWKEEP.EXEコマンド | ○ | × | × |
lvsetfolコマンド | × | ○ | × | |
○:利用可能
×:利用不可
以下、環境設定の変更方法について説明します。
リストナビで、保管フォルダの環境設定を変更することができます。
| リストナビで、リスト管理サーバ上の保管フォルダの環境設定を変更する方法については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 リストナビで、マイ コンピュータ上の保管フォルダの環境設定を変更する方法については、“操作手引書 利用者編”を参照してください。 フォルダの設定変更が行えるユーザのアクセス権については、“運用手引書”を参照してください。 |
Windows版において、リスト管理サーバの保管フォルダの設定変更をする場合、F5CWKEEP.EXEコマンドが利用できます。変更する保管フォルダの数が多い場合などは、スクリプトに組み込んで使用することも可能です。
保管フォルダごとに、格納する帳票の有効期限や、セパレータ削除の有無、抜き出し検索を有効にするかなど、細かい設定の変更が行えます。
F5CWKEEP.EXEコマンドは、管理者で実行できます。
保管フォルダを設定変更する手順を以下に示します。
「保管フォルダ情報ファイル」を変更します。その際に、[FolderInformation]セクションのCreateFolderには「0」(保管フォルダのプロパティ情報を変更する)を設定します。
1.で変更した「保管フォルダ情報ファイル」を、F5CWKEEP.EXEコマンドにより登録します。
| 「保管フォルダ情報ファイル」の記述方法、およびF5CWKEEP.EXEコマンドの詳細は“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
Solaris 版において、リスト管理サーバの保管フォルダの設定変更をする場合、lvsetfolコマンドが利用できます。
コマンドのオプションに、変更する保管フォルダの保管フォルダ名、作成者名、「保管フォルダ情報ファイル名」、および-rオプションを指定します。「保管フォルダ情報ファイル」には、保管フォルダに設定する定義を記述します。
ただし、コマンドの実行にはスーパーユーザの権限が必要です。
保管フォルダを変更する手順を以下に示します。
「保管フォルダ情報ファイル」を作成し、変更する保管フォルダの定義を記述します。
ディレクトリ名、保管フォルダ名、作成者名、および1.で作成した「保管フォルダ情報ファイル」を、lvsetfolコマンドにより登録します。
| lvsetfolコマンドの詳細、および「保管フォルダ情報ファイル」の定義の記述方法については、“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
リスト管理サーバ上の既存の保管フォルダに対し、フォルダ名の変更、移動、複写を行うことができます。
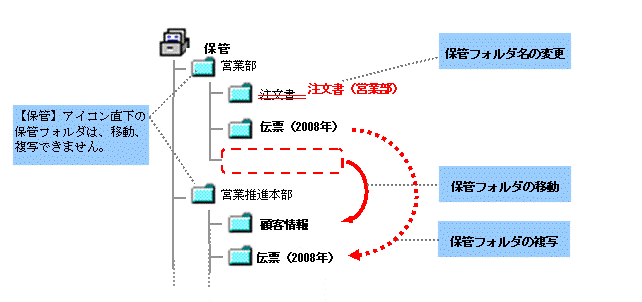
リスト管理サーバの保管フォルダ名の変更、移動、複写は、リストナビで操作します。ただし、【保管】アイコン直下の保管フォルダは、移動、および複写することはできません。
| リストナビで、保管フォルダ名の変更、移動、複写する方法については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 また、フォルダ名の変更、移動、複写が行えるユーザのアクセス権については、“運用手引書”を参照してください。 |
保管フォルダ名を変更、移動、複写したフォルダを帳票の振り分け先として定義するかどうか、検討が必要です。
振り分け先として定義する場合は、以下の振り分け先定義の更新が必要です。
受信フォルダの振り分け先の定義を更新します。ただし保管フォルダ名の変更、および移動の場合は、受信フォルダの振り分け定義は自動的に更新されるため、定義の変更は必要ありません。
| 受信フォルダの振り分け定義の変更方法については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 |
帳票出力時に指定している帳票の格納先の設定を変更します。
| 帳票の格納先の設定については、“運用手引書”を参照してください。 |
Solaris版において、帳票の格納先として物理パスが指定されている場合、以下の手順で保管フォルダの物理パスと論理パスの対応関係を変更してください。対応定義がされていない状態で、物理パスを指定して帳票の登録を行った場合は、登録エラーとなります。
lvlstpthコマンドで、保管フォルダのパス対応表一覧を作成し、保管フォルダに関する定義を確認します。
lvdelpthコマンドで、必要がない保管フォルダの物理パスと論理パスの対応関係を削除します。
lvsetpthコマンドで、新たに追加する保管フォルダの物理パスと論理パスの対応関係を定義します。
| lvlstpthコマンド、lvsetpthコマンド、またはlvdelpthコマンドについては、“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
注意
保管フォルダ名の変更、移動、複写は、リスト管理サーバの保管フォルダに対して操作することができます。マイ コンピュータの保管フォルダでは操作できません。
リストナビ上で表示される保管フォルダ名は論理的なフォルダ名であり、リスト管理サーバで物理的なフォルダとの関連付けを行っています。このため、同じ保管フォルダに対して、2台のリストナビから並行して操作した場合、以下のようになります。
一方のリストナビでフォルダの「移動」、他方のリストナビでフォルダの「複写」を行うことができます。
2台のリストナビからフォルダの「移動」を行った場合は、後から実行したリストナビで指定した移動先に移動します。
2台のリストナビから、同じ複写先を指定して同時にフォルダの「複写」を行った場合、複写先には2つの保管フォルダが複写されます。
この場合、フォルダの複写後にいずれかの保管フォルダ名を重複しない名前に変更してください。
フォルダ名の変更、移動、複写を行った保管フォルダを、ファイリングの対象に設定している場合は、グループフォルダの定義を変更する必要があります。
| グループフォルダの設定については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 |
複写したフォルダのアクセス権は、複写先の親フォルダと同じアクセス権になります。
移動したフォルダのアクセス権は、そのままの状態となります。管理者ツールを使用して、必要に応じてアクセス権を再設定してください。
同一保管フォルダ内に、保管フォルダを複写することはできません。運用上、そのような事象が発生した場合は、以下のいずれかの方法で同じ内容の保管フォルダを作成してください。
同一保管フォルダ内に新たに保管フォルダを作成して、帳票を複写します。
別階層の保管フォルダにいったん保管フォルダを複写し、保管フォルダ名を変更後、対象の保管フォルダに複写します。
保管フォルダ、および帳票ごとに、アクセス権(削除、移動、複写、表示など)が設定、変更できます。
アクセス権を設定、変更するには、以下の方法があります。
List Worksの管理者ツールによる設定、変更
アクセス権のインポート/エクスポートによる設定、変更
| 管理者ツールによる保管フォルダのアクセス権の設定、変更方法については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 |
保管フォルダ、および保管フォルダ配下の帳票に設定されているアクセス権を一括して確認、または設定する機能です。アクセス権のインポート/エクスポートには、以下の方法があります。
管理者ツール
F5CWACIM.EXEコマンド(Windows版のみ、アクセス権のインポート)
F5CWACEX.EXEコマンド(Windows版のみ、アクセス権のエクスポート)
lvacimptコマンド(Solaris版のみ、アクセス権のインポート)
lvacexptコマンド(Solaris版のみ、アクセス権のエクスポート)
| 管理者ツールについては、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 F5CWACIM.EXEコマンド、F5CWACEX.EXEコマンド、lvacimptコマンド、およびlvacexptコマンドについては、“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
保管フォルダ、および保管フォルダ配下の帳票に設定されているアクセス権を一括して確認する機能です。
保管フォルダ、または保管フォルダ配下の帳票に設定されているアクセス権を、保管フォルダ単位、帳票単位のブロックで、アクセス権データファイルに出力します。
保管フォルダ、および保管フォルダ配下の帳票に対し、アクセス権を一括して設定する機能です。アクセス権データファイルを読み込み、保管フォルダ、および保管フォルダ配下のアクセス権が追加/更新されます。アクセス権のインポートを行う場合、アクセス権に関する情報を、アクセス権データファイルに記述します。
参考
アクセス権のインポートは、運用中に行わないことを奨励します。運用中に保管フォルダ、および保管フォルダ配下の帳票のアクセス権が変更されることで、利用者の操作に支障をきたす場合があります。
すでにアクセス権が設定されている保管フォルダ、および保管フォルダ配下の帳票に対し、アクセス権が無い状態に変更する場合は、アクセス権データファイルにおいて、保管フォルダ/保管フォルダ配下の帳票の論理パス行のみを記述します。
アクセス権が変更されるのは、アクセス権データファイルに記述がある保管フォルダ/保管フォルダ配下の帳票だけとなります。その他の保管フォルダ/保管フォルダ配下の帳票に対しては、アクセス権は変更されません。
アクセス権データファイルに複数の同一保管フォルダ、または複数の同一保管フォルダ配下の帳票に対し、アクセス権設定の記述があった場合は、後に記述されている設定が有効となります。
インポート処理をキャンセルした場合、キャンセルされる前までのアクセス権は設定された状態となります。
保管フォルダ、および保管フォルダ配下の帳票のアクセス権情報が記述されている、Text形式のデータファイルです。以下のアクセス権に関する情報を、カンマ区切りで記述しています。
ID種別(0:Everyone、1:グループ、2:ユーザ)
ユーザ名、またはグループ名(ID種別が1または2の場合)
基準となるアクセス権
設定するアクセス権
グループに対する帳票のアクセス権を、カンマ区切りで、以下の順に設定します。
グループIDを先頭に記述する。
FULL(すべてのアクセス権を設定)、またはNONE(すべてのアクセス権を解除)のいずれかを記述する。
2.がFULLの場合、許可しないアクセス権を記述する。NONEの場合、許可するアクセス権を記述する。
つまり、アクセス権を設定する場合、以下のいずれかの方法で指定します。
FULLを設定し、アクセス権を与えないものを指定する
NONEを設定し、アクセス権を与えるものを指定する
アクセス権のキーワードは以下のとおりです。
アクセス権の一覧記述で基準となるキーワード
保管フォルダのアクセス権 保管フォルダ配下の帳票のアクセス権 | キーワード |
|---|---|
すべてのアクセス権を設定 | FULL |
すべてのアクセス権を解除 | NONE |
保管フォルダのアクセス権
保管フォルダのアクセス権 | キーワード |
|---|---|
保管フォルダの作成 | FCRE |
保管フォルダの移動 | FMOV |
保管フォルダの複写 | FCPY |
保管フォルダの削除 | FDEL |
保管フォルダの表示 | FVIW |
保管フォルダのプロパティ表示 | FPRV |
保管フォルダのプロパティ更新 | FPRM |
保管フォルダ名の変更 | FNAM |
保管フォルダ配下のフォルダ一覧表示 | FLST |
保管フォルダ配下の帳票一覧表示 | SLST |
帳票の移動 | MOVE |
帳票の複写 | COPY |
帳票の削除 | DELT |
帳票の表示 | VIEW |
帳票情報の変更 | MODY |
帳票への記入 | ITEM |
帳票のローカル印刷 | LPRT |
帳票のリモート印刷 (注) | RPRT |
ファイリング | FLNG |
メール送信 | |
PDF表示/保存 | PDFV |
PDF変換 | PDFC |
データ変換 | CONV |
上書き保存 | ASAV |
名前を付けて保存 | NSAV |
帳票項目の保存 | FLDS |
抜き出し範囲の設定 | INDX |
オーバレイ位置の設定 | OVLP |
クリップボードへのコピー | CLPB |
注:Solaris版の場合、Solaris 11上ではリモート印刷はできません。このため、Solaris 11上では意味をもちません。
保管フォルダ配下の帳票のアクセス権
保管フォルダ配下の帳票のアクセス権 | キーワード |
|---|---|
帳票の移動 | MOVE |
帳票の複写 | COPY |
帳票の削除 | DELT |
帳票の表示 | VIEW |
帳票一覧への表示 | LSTV |
帳票情報の変更 | MODY |
帳票への記入 | ITEM |
帳票のローカル印刷 | LPRT |
帳票のリモート印刷 (注) | RPRT |
ファイリング | FLNG |
メール送信 | |
PDF表示/保存 | PDFV |
PDF変換 | PDFC |
データ変換 | CONV |
上書き保存 | ASAV |
名前を付けて保存 | NSAV |
帳票項目の保存 | FLDS |
抜き出し範囲の設定 | INDX |
オーバレイ位置の設定 | OVLP |
クリップボードへのコピー | CLPB |
注:Solaris版の場合、Solaris 11上ではリモート印刷はできません。このため、Solaris 11上では意味をもちません。
注意
存在しない保管フォルダ/保管フォルダ配下の帳票の記述に対するインポートは行われず、操作ログにその旨が出力されます。
[ ]で囲んだ保管フォルダ/保管フォルダ配下の帳票の論理パスの記述形式に誤りがある場合は、インポートの実行時に次の[ ]が現れるまでのアクセス権情報がスキップされます。また、操作ログに何行目の記述に誤りがあるかが出力されます。
複数行記述されたアクセス権情報のひとつでも記述形式に誤りがある場合は、対象となる保管フォルダ/保管フォルダ配下の帳票へのアクセス権のインポートは行われず、次の[ ]が現れるまでアクセス権情報がスキップされます。また、操作ログに何行目の記述に誤りがあるか、何行目の保管フォルダ/保管フォルダ配下の帳票に対してインポートを行わなかったかが出力されます。
参考
アクセス権データファイルは、以下の文字コードで作成してください。
Windows版の場合:シフトJISで作成してください。
Solaris版の場合:EUCコードで作成してください。
アクセス権データファイルにおいて、ユーザ名またはグループ名は以下の文字数で指定してください。
ユーザ名 :26バイト以内
グループ名:Windows版の場合は256バイト以内、Solaris版の場合は26バイト以内
アクセス権データファイルの記述例は以下のとおりです。記述例の下に各行の示す内容を記述します。
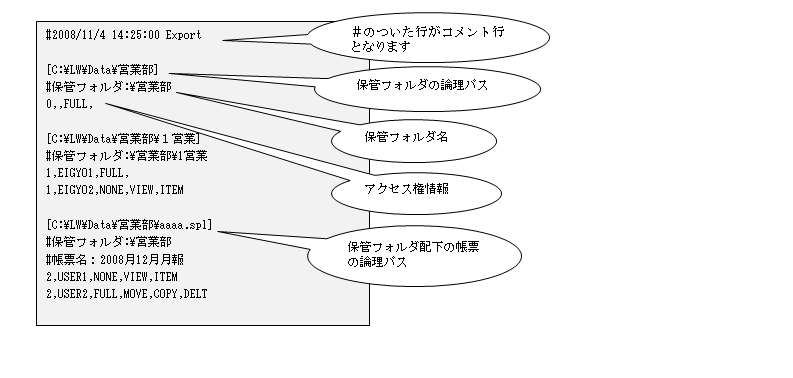
1行目:コメント行 2行目:フォルダブロックの開始。保管フォルダの論理パスを[]でくくる 3行目:保管フォルダ名(コメント行) 4行目:すべてのユーザ(Everyone)に対し、すべてのアクセスを設定する 5行目:フォルダブロックの開始。保管フォルダの論理パスを[]でくくる 6行目:保管フォルダ名(コメント行) 7行目:グループ「EIGYO1」に対して、すべてのアクセス権を設定する 8行目:グループ「EIGYO2」に対して、「帳票の表示」「帳票への記入」のアクセス権を設定する 9行目:帳票ブロックの開始。保管フォルダ配下の帳票の論理パスを[]でくくる 10行目:帳票が存在する保管フォルダ名(コメント行) 11行目:帳票名(コメント行) 12行目:ユーザ「USER1」に対して、「帳票の表示」「帳票への記入」のアクセス権を設定する 13行目:ユーザ「USER2」に対して、「帳票の移動」「帳票の複写」「帳票の削除」以外のアクセス権を設定する
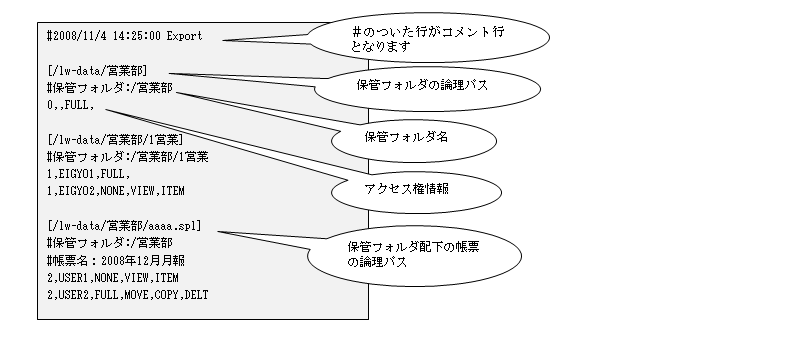
1行目:コメント行 2行目:フォルダブロックの開始。保管フォルダの論理パスを[]でくくる 3行目:保管フォルダ名(コメント行) 4行目:すべてのユーザ(Everyone)に対し、すべてのアクセスを設定する 5行目:フォルダブロックの開始。保管フォルダの論理パスを[]でくくる 6行目:保管フォルダ名(コメント行) 7行目:グループ「EIGYO1」に対して、すべてのアクセス権を設定する 8行目:グループ「EIGYO2」に対して、「帳票の表示」「帳票への記入」のアクセス権を設定する 9行目:帳票ブロックの開始。保管フォルダ配下の帳票の論理パスを[]でくくる 10行目:帳票が存在する保管フォルダ名(コメント行) 11行目:帳票名(コメント行) 12行目:ユーザ「USER1」に対して、「帳票の表示」「帳票への記入」のアクセス権を設定する 13行目:ユーザ「USER2」に対して、「帳票の移動」「帳票の複写」「帳票の削除」以外のアクセス権を設定する
保管フォルダを削除する場合に考慮すべき事項と、保管フォルダの削除方法について説明します。
保管フォルダを削除する場合は、次の事項について事前に考慮が必要です。
削除する保管フォルダを、帳票の振り分け先として定義している場合は、振り分けの指定方法によっては対処が必要です。
振り分け先として指定された保管フォルダを削除する際は、振り分け先の定義を他の保管フォルダに向けて再設定します。受信フォルダの振り分け定義を変更しない場合でも、必ず受信フォルダのプロパティにおいて【OK】ボタンを押してください。
また、保管フォルダを削除したあと、再度、同じ保管フォルダ名で保管フォルダを作成しても、すでに定義されている受信フォルダの振り分け定義は有効となりません。受信フォルダの振り分け定義を再定義する必要があります。
| 受信フォルダの振り分け先定義の設定については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 |
帳票出力時に指定している帳票の格納先の設定を変更します。
| 帳票の格納先の設定については、“運用手引書”を参照してください。 |
Solaris版において、帳票の格納先として物理パスが指定されている場合、以下の手順で保管フォルダの物理パスと論理パスの対応関係を削除してください。
lvlstpthコマンドで、保管フォルダのパス対応表一覧を作成し、削除した保管フォルダに関する定義が存在することを確認します。
lvdelpthコマンドで保管フォルダの物理パスと論理パスの対応関係を削除します。
| lvlstpthコマンド、またはlvdelpthコマンドについては、“コマンドリファレンス”を参照してください。 |
削除する保管フォルダを、グループフォルダのプロパティで「ファイリングする保管フォルダ」として定義している場合は、必要に応じて定義を変更します。
| グループフォルダのプロパティについては、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 |
保管フォルダを削除する方法は、以下のとおりです。
リストナビによる削除
F5CWKPDL.EXEコマンドによる削除
lvdelfolコマンドによる削除
List Worksの動作環境の違いにより、利用できる削除方法は以下のように異なります。
削除方法 | リスト管理サーバの保管フォルダ | マイ コンピュータの保管フォルダ | ||
|---|---|---|---|---|
Windows版 | Solaris版 | |||
リストナビによる削除 | ○ | ○ | ○ | |
コマンドによる削除 | F5CWKPDL.EXEコマンド | ○ | × | × |
lvdelfolコマンド | × | ○ | × | |
○:利用可能
×:利用不可
以下、各削除方法について説明します。
リストナビで、フォルダの階層を確認しながら、保管フォルダを削除することができます。
| リストナビで、リスト管理サーバ上の保管フォルダを削除する方法については、“操作手引書 運用管理者編”を参照してください。 リストナビで、マイ コンピュータ上の保管フォルダを削除する方法については、“操作手引書 利用者編”を参照してください。 フォルダの削除が行えるユーザのアクセス権については、“運用手引書”を参照してください。 |