QoS自動化機能の自動チューニングは、目標を設定したボリュームが目標に達するように、帯域幅を調整することにより実現します。この時、同時に、目標を設定していないボリュームの帯域幅も自動調整します。
評価は、リード+ライトのボリュームの実測レスポンスタイムを基に行います。
なお、調整はハードの限界性能の範囲内で行います。設定した目標値を保証するものではありません。
自動チューニング例
自動チューニングの実施例を、以下に示します。
業務の性能からボリューム1(Vol#1)の性能が不足していると判断した時は、レスポンスタイムの実測値が50ミリ秒であることから、利用者が、50ミリ秒より高速になるように30ミリ秒に設定します。ほかのボリューム(Vol#2、Vol#3)には目標値を設定しません。
その結果、Vol#1の帯域幅が広がり、ボリューム2(Vol#2)およびボリューム3(Vol#3)の帯域幅が狭められ、目標値に向けて自動チューニングが行われます。
帯域幅の調整の結果、Vol#1のレスポンスタイムが目標を達成します。
図5.2 帯域幅調整の仕組み
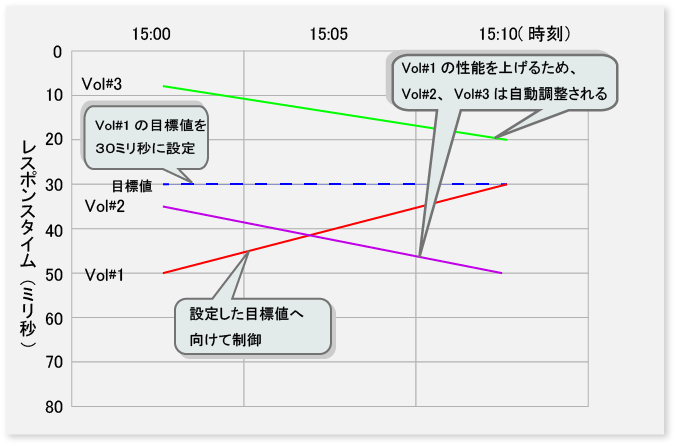
自動チューニングの仕組み
ETERNUS ディスクアレイのQoS機能は、帯域制限幅を60IOPS、5MB/sから無制限までの16段階で設定します。QoS自動化機能は、この機能を利用して帯域幅を変更することにより、性能を調整します。
対象ボリュームに初めて目標値を設定した直後では、初期値から段階的な調整を行うため、すぐに効果が表れない場合があります。
自動チューニングは、評価間隔(1分)ごとに性能情報を採取し、以下の処理を繰り返すことで実現しています。
Busy率が最大の共有リソース(CM、Port、スイッチPort、プール)を見つけます。
Busy率が最大のリソースを共有するボリューム間で帯域幅を調整します。調整内容は、以下のとおりです。
実測性能が目標性能を上回るボリュームの帯域幅を1段階狭めます。
実測性能が目標性能を下回り、かつQoSにより帯域を狭められているボリュームの帯域幅を1段階広げます。
目標性能を設定していないボリュームに、上記で生じた不足分の調整をします。
注意
QoS自動化機能は、性能調整対象となるFTVが属するストレージの性能情報と、スイッチの性能情報を参照します。
スイッチの性能管理機能が無効のままでもQoS自動化機能を利用できますが、その場合、CMとプールに関する共有リソースだけが性能調整の対象となります。
システムが低負荷状態のときの考慮
業務運用は、時間帯によって負荷状態が異なることが考えられます。
低負荷状態のときは、スループットが低いため、実測レスポンスタイムは最速の値になります。その結果、実測レスポンスタイムが目標レスポンスタイムを上回り、自動チューニングにより帯域幅が最狭の状態となります。この状態から、高負荷状態の時間帯になってスループットが急増すると、レスポンスタイムが極端に悪化する可能性があります。
目標値を設定したボリュームの実測レスポンスタイムが目標レスポンスタイムを上回っている場合に、Busy率が高い共有リソース配下のほかの目標値を設定したボリュームの実測レスポンスタイムが目標レスポンスタイムを下回っているときだけ、帯域幅を狭めます。共有リソース配下のすべてのボリュームが目標レスポンスタイムを上回っている場合は、帯域幅は調整されません。
ボリュームに対する業務からの負荷がないときも、そのボリュームの帯域幅は調整されません。
また、業務負荷がなく帯域に余裕がある場合は、帯域が不足しているほかのボリュームに、余っている帯域を一時的に融通して、不足分を解消します。これにより、目標レスポンスタイムを満たしている場合でもほかのボリュームの帯域に余裕があるときは、目標レスポンスタイム以上の性能を得られることがあります。