同期の実行単位となるレプリケーショングループを定義し、運用形態や同期方式などの機能を設定します。
図6.12 マスタグループ定義 - [基本設定]画面
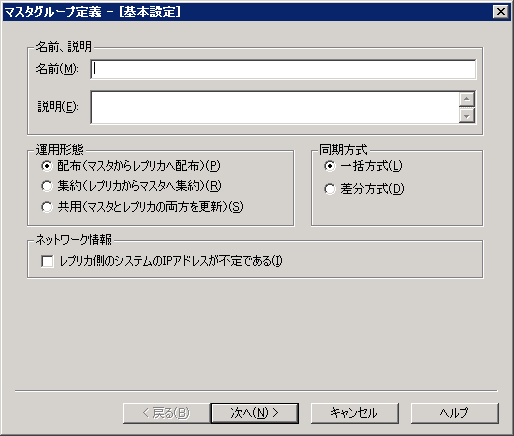
マスタグループ定義の作成方法
ツリービューで"マスタグループ"選択し、以下のいずれかの手順で作成できます。
[ファイル]メニュー → [新規作成] → [マスタグループの作成]
マウスを右クリック → [マスタグループの作成]
設定項目を入力して[次へ]ボタンを押し、設定が完了したら[OK]ボタンを押してください。
前の画面を戻って入力を訂正する場合、[戻る]ボタンを押してください。設定を取り消す場合、[キャンセル]ボタンを押してください。[ヘルプ]ボタンを押して、レプリケーションヘルプ画面を表示できます。
マスタグループ定義の表示方法
作成済みのマスタグループ定義を表示する場合、ツリービューでマスタグループ定義を選択し、以下のいずれかの手順で表示できます。
[ファイル]メニュー → [開く]
マウスを右クリック → [開く]
ツールバーの[開く]ボタンを押す
図6.13 マスタグループ定義表示画面
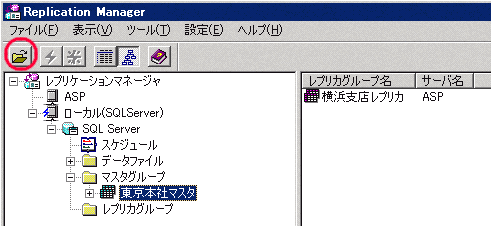
マスタグループ定義画面の設定項目
名前、説明
名前
マスタグループ定義の名前を入力します。
同一サーバ内に同名のマスタグループ定義を複数設定できません。
マスタグループ定義の名前は、英数字で62文字、日本語で31文字まで入力できます。
シフトJISコードで表現できる文字を使用してください。外字および特殊文字は使用できません。接続しているサーバがASP(PRIMERGY 6000)の場合、半角英小文字と半角カナ文字は使用できません。
説明
マスタグループ定義についての説明を入力します。
説明は、英数字で255文字、日本語で127文字まで入力できます。シフトJISコードで表現できる文字を使用してください。
省略も可能です。
運用形態
以下の3種類から選択します。
配布(マスタからレプリカへ配布)
データファイルの内容を、マスタ側からレプリカ側に反映します。
集約 (レプリカからマスタへ集約)
データファイルの内容を、レプリカ側からマスタ側に反映します。
共用 (マスタとレプリカの両方を更新)
データファイルの内容をマスタ側とレプリカ側の双方に反映します。
「同期方式」が"差分方式"の場合のみ選択できます。
同期方式
以下の2種類から選択します。ここで選択した内容によって、次に表示される画面が異なります。
一括方式
一括方式は、反映元のすべてのデータまたは指定した抽出条件に一致しているすべてのデータを反映先のデータファイルへ反映する方式です。
差分方式
差分方式は、前回の同期から更新したデータだけを反映先のデータファイルへ反映する方式です。
ネットワーク情報
レプリカ側のシステムがDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)を使用した動的なIPアドレスで運用している場合、"レプリカ側のシステムのIPアドレスが不定である"を選択します。
![]()
複数の通信アダプタを装着した場合、レプリケーションサービスで使用するIPアドレスは、レプリケーションマネージャのサーバ定義で設定したIPアドレス(ホスト名)を使用します。
![]()
レプリケーションサービスは、IPv6に対応していません。
マスタグループ定義 - [一括方式の設定]画面
"マスタグループ定義 - [基本設定]"の画面で、同期方式に「一括方式」を選択した場合、一括同期の処理モードを設定します。
図6.14 マスタグループ定義 - [一括方式の設定]画面
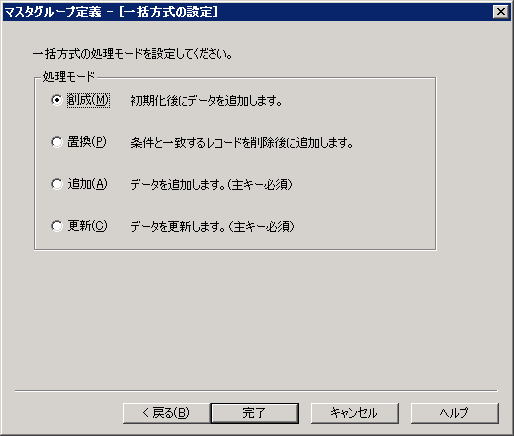
処理モードを以下の4種類から選択します。
創成
反映先のデータファイルを初期化した後に、反映するデータが追加されます。
置換
反映元の抽出条件に合致した反映先のデータは、すべて削除されてから、反映するデータが追加されます。
追加
反映先のマスタ定義またはレプリカ定義に設定した主キーの値と反映するデータの主キーの値が一致する場合は無効となります。一致する主キー値が存在しない場合は、データが追加されます。
更新
反映元の主キーの値と反映するデータの主キーの値が一致する場合、データは項目単位で更新されます。一致する主キーの値が存在しない場合は、データが追加されます。
マスタグループ定義 - [差分方式の設定]画面
「差分方式」の「配布」を選択した場合
"マスタグループ定義 - [基本設定]"の画面で、同期方式に「差分方式」、運用形態に「配布」を選択した場合、差分同期の詳細を設定します。
図6.15 マスタグループ定義-[差分方式の設定]画面
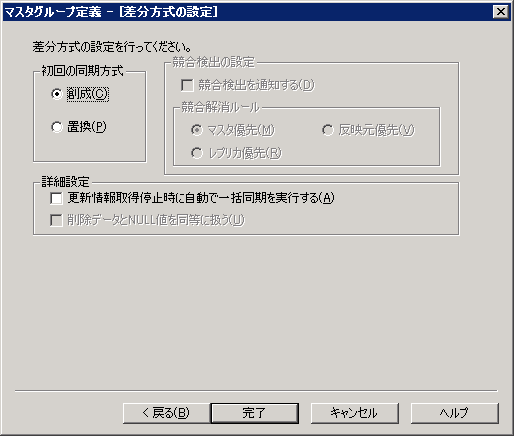
初回の同期方式
処理モードを以下の2種類から選択します。
創成
反映先のデータファイルが初期化された後、反映するデータが追加されます。
置換
反映元の抽出条件に合致した反映先のデータは、すべて削除されてから、反映するデータが追加されます。
この設定は、rpsyncコマンドで一括同期(-aオプション)を指定した場合、および「詳細設定」の「更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する」が実行された場合に有効となります。
rpsyncコマンドの詳細は、"7.2 同期実行コマンド"を参照してください。
詳細設定
更新情報の取得が停止している状態で差分同期が実行された場合、自動的に一括同期を実行するときに「更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する」を設定します。
自動的に実行される一括同期は、「初回の同期方式」に設定した処理モードに従って実行されます。
![]()
一括同期が実行されると、同期実行中は同期対象のデータファイルが排他獲得されるため、この間、利用者プログラムから同期対象のデータファイルにアクセスできません。
業務運用中に自動的に一括同期が実行されると問題がある場合は、「更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する」を設定しないでください。
更新情報の設定
ディレクトリ名
更新情報を格納するディレクトリ名を設定します。このディレクトリ名は、サーバの動作環境設定時に設定したディレクトリから選択します。
最大サイズ
更新情報を格納する最大サイズをMバイト単位で、1~2047の範囲で設定します。更新情報を格納するディレクトリ(磁気ディスク)の空き領域以下で設定してください。
警告通知使用率
更新情報を格納するディレクトリの使用率が何%に達したときにイベントビューア(アプリケーションログ)に警告を通知するかを設定します。"0"を設定すると警告を通知しません。初期値は"80"、指定範囲は"0~100"です。
「更新情報の設定」は、マスタグループ定義に以下のすべてが設定されたときに有効となります。
マスタグループ定義のDBMS種別が富士通製DBMS
運用形態が「配布」または「共用」
同期方式が「差分方式」
マスタグループ定義 - [差分方式の設定]画面
「差分方式」の「集約」を選択した場合
"マスタグループ定義 - [基本設定]"の画面で、同期方式に「差分方式」、運用形態に「集約」を選択した場合、差分同期の詳細を設定します。
図6.16 マスタグループ定義-[差分方式の設定]画面
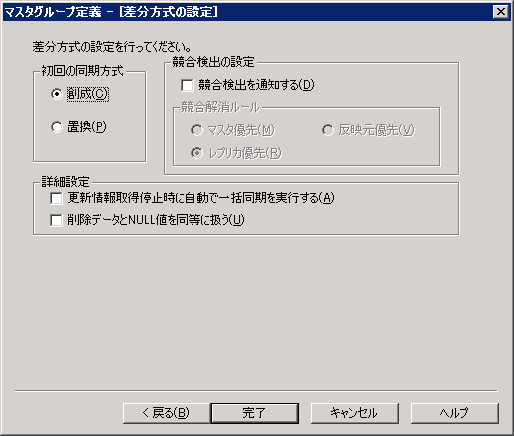
初回の同期方式
処理モードを以下の2種類から選択します。
創成
反映先のデータファイルが初期化された後、反映するデータが追加されます。
置換
反映元の抽出条件に合致した反映先のデータは、すべて削除されてから、反映するデータが追加されます。
この設定は、rpsyncコマンドで一括同期(-aオプション)を指定した場合、および「詳細設定」の「更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する」が実行された場合に有効となります。
rpsyncコマンドの詳細は、"7.2 同期実行コマンド"を参照してください。
競合検出の設定
同期実行時に競合が発生したことをイベントビューア(アプリケーションログ)に通知する場合、「競合検出を通知する」を設定します。
詳細設定
更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する
更新情報の取得が停止している状態で差分同期が実行された場合、自動的に一括同期を実行するときに設定します。
自動的に実行される一括同期は、「初回の同期方式」に設定した処理モードに従って実行されます。
![]()
一括同期が実行されると、同期実行中は同期対象のデータファイルが排他獲得されるため、この間、利用者プログラムから同期対象のデータファイルにアクセスできません。
業務運用中に自動的に一括同期が実行されると問題がある場合は、「更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する」を設定しないでください。
削除データとNULL値を同等に扱う
レコードを削除せず、関連づけた項目のデータをNULL値に更新する場合に設定します。
マスタグループ定義 - [差分方式の設定]画面
「差分方式」の「共用」を選択した場合
"マスタグループ定義 - [基本設定]"の画面で、同期方式に「差分方式」、運用形態に「共用」を選択した場合、差分同期の詳細を設定します。
図6.17 マスタグループ定義-[差分方式の設定]画面
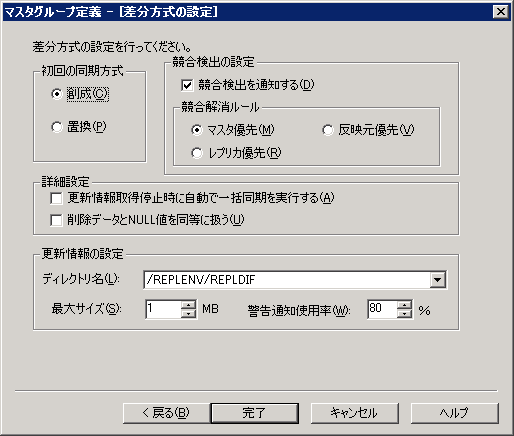
初回の同期方式
処理モードを以下の2種類から選択します。
創成
反映先のデータファイルが初期化された後、反映するデータが追加されます。
置換
反映元の抽出条件に合致した反映先のデータは、すべて削除されてから、反映するデータが追加されます。
この設定は、rpsyncコマンドで一括同期(-aオプション)を指定した場合、および「詳細設定」の「更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する」が実行された場合に有効となります。
rpsyncコマンドの詳細は、"7.2 同期実行コマンド"を参照してください。
競合検出の設定
競合検出を通知する
同期実行時に競合が発生したことをイベントビューア(アプリケーションログ)に通知する場合に設定します。
競合解消ルール
競合の検出を通知する場合、以下の3種類から選択します。
競合解消ルール | 競合検出時の動作 |
|---|---|
マスタ優先 | マスタ側の更新データを優先して、競合を解消 |
レプリカ優先 | レプリカ側の更新データを優先して、競合を解消 |
反映元優先 | マスタおよびレプリカで更新したデータを反映します(データは破棄されません)。競合が発生する状態では、双方で異なるデータを反映すると、マスタとレプリカのデータが一致しなくなります。 |
詳細設定
更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する
更新情報の取得が停止している状態で差分同期が実行された場合、自動的に一括同期を実行するときに設定します。
自動的に実行される一括同期は、「初回の同期方式」に設定した処理モードに従って実行されます。
![]()
一括同期が実行されると、同期実行中は同期対象のデータファイルが排他獲得されるため、この間、利用者プログラムから同期対象のデータファイルにアクセスできません。
業務運用中に自動的に一括同期が実行されると問題がある場合は、「更新情報取得停止時に自動で一括同期を実行する」を設定しないでください。
削除データとNULL値を同等に扱う
レコードを削除せず、関連づけた項目のデータをNULL値に更新する場合に設定します。
更新情報の設定
ディレクトリ名
更新情報を格納するディレクトリ名を設定します。このディレクトリ名は、サーバの動作環境設定時に設定したディレクトリから選択します。
最大サイズ
更新情報を格納する最大サイズをMバイト単位で、1~2047の範囲で設定します。更新情報を格納するディレクトリ(磁気ディスク)の空き領域以下で設定してください。
警告通知使用率
更新情報を格納するディレクトリの使用率が何%に達したときにイベントビューア(アプリケーションログ)に警告を通知するかを設定します。"0"を設定すると警告を通知しません。初期値は"80"、指定範囲は"0~100"です。
「更新情報の設定」は、マスタグループ定義が以下の設定のときにのみ表示されます。
マスタグループのDBMS種別が富士通製DBMS
運用形態が「配布」または「共用」
同期方式が「差分方式」
![]()
マスタグループ定義の設定を変更する場合、対象のマスタグループ定義に作成したマスタ定義および関連づけたレプリカグループ定義を削除してから行ってください。
![]()
マスタグループ定義を削除すると、対象のマスタグループ定義に作成されたマスタ定義も同時に削除されます。