GDS Snapshotと連携せず、AdvancedCopy Managerテープバックアップの機能だけで行う運用です。論理ボリュームがどの物理ボリュームから構成されているかを把握した設計・運用が必要です。
図5.15 スライス単位のバックアップ運用
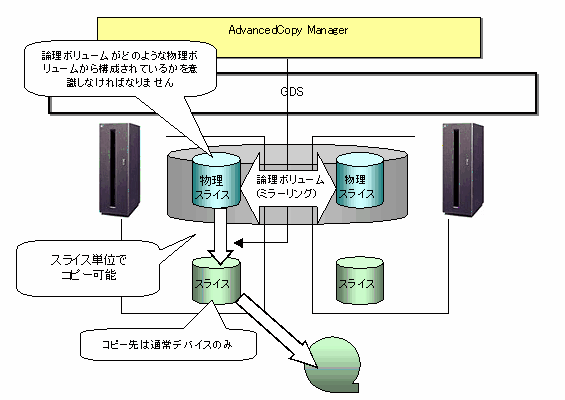
AdvancedCopy Managerテープバックアップコマンドに指定する場合は、論理ボリューム名とAdvancedCopy Managerデバイス名を組み合わせた以下の形式の名前を使用します。
スライス単位の運用
[Solarisの場合]
/dev/sfdsk/(クラス名)/dsk/(ボリューム名):(sdxinfoのDEVNAMの値) |
[Linuxの場合]
/dev/sfdsk/(クラス名)/dsk/(ボリューム名):(デバイス名) |
ボリュームを構成するデバイス名は、以下のいずれかを使用します。
sdxinfoのDEVNAMの値
以下に、スライス単位の運用で、sdxinfoのDEVNAMの値を使用した例を記載します。
例)/dev/sfdsk/class1/dsk/volume1:sda
クラス名:class1
ボリューム名:volume1
デバイス名:sda(sdxinfoのDEVNAMの値)
sdxinfoのDEVNAMの値が指すudev機構により生成するデバイス名(udevデバイス名)
以下に、スライス単位の運用で、udevデバイス名を使用した例を記載します。
例)/dev/sfdsk/class1/dsk/volume1:/dev/disk/by-id/scsi-3600e000000cb00000000000100020000
クラス名:class1
ボリューム名:volume1
デバイス名:/dev/disk/by-id/scsi-3600e000000cb00000000000100020000(sdxinfoのDEVNAMの値が示すudevデバイス名)
udevデバイス名が存在する環境では、udevデバイス名を優先して使用します。udevデバイス名はby-id名が使用可能です。udevデバイス名を使用する場合で、by-idが生成されていない場合は、by-idを生成してください。by-path名のみを生成した環境でテープバックアップオプションによるバックアップ運用を行う場合は、『ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書(Linux版)』の「stgxfwcmsetmode(情報取得モード設定コマンド)」にて従来形式(互換デバイス名)に変更してください。
udevデバイス名が存在する環境であっても、sdxinfoのDEVNAMの値を使用して運用する場合には、デバイス情報取得/反映処理の前に、udevデバイス名を使用しないように、情報取得モードを変更してください。
詳細は、『ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書(Linux版)』の「stgxfwcmsetmode(情報取得モード設定コマンド)」を参照してください。
[Windowsの場合]
ディスククラス名/ミラーボリューム:g?d?p? |
注意
論理ボリューム単位の運用は行えません。
サポートするOSは、Solaris、Linuxです。
Linuxの場合の注意事項
以下、PRIMECLUSTER GDS/SafeDISKのSDXオブジェクトをテープバックアップオプションで使用する場合の注意事項です。
udevデバイス名を使用する場合には、by-id名を使用するようにしてください。
by-id名が生成されていない場合には、by-id名が生成されるように設定を変更してください。by-pathでの運用は行えません。
ETERNUSマルチパスドライバが導入されていない環境で、udevデバイス名を使用する場合、以下に注意してください。
by-id使用時のディスク交換の場合、udevデバイス名が変更になる可能性があります。udevデバイス名が変更になった場合、「デバイス構成の変更」の手順による対応が必要となります。
SDXオブジェクトの運用上の注意点は、「16.1.5 SDXオブジェクト運用の注意」を参照してください。
筐体間ミラーを行っている場合、筐体障害の場合も、OPCによりリストアする必要があるときは、ミラーの両系をバックアップする必要があります。この場合、バックアップボリュームは、論理ボリュームの容量ではなく、物理ボリュームの容量分が必要です。
SymfowareのDBSPを筐体間ミラーしている場合、業務ボリュームとしてはどちらか一方の筐体にあるボリュームしか登録できません。したがって、バックアップ運用している筐体が筐体障害となった場合は、筐体障害から回復するまでバックアップ/リカバリができません。
バックアップ運用の設計を行う場合の注意事項は、「16.1.5 SDXオブジェクト運用の注意」を参照してください。
バックアップ運用を行うサーバをStorageサーバとして登録し、Storageサーバ配下のデバイスの情報を取得します。
デバイス情報の取得方法は、「5.3.3 Storageサーバ配下のデバイス情報の取り込み」を参照してください。
業務ボリューム
業務で使用している論理ボリュームを構成するスライスを、業務ボリュームとして登録します。
# /opt/FJSVswstc/bin/acmdevinfoset -t /dev/sfdsk/CLS01/dsk/VOL01:c1t0d1 acmdevinfoset completed # |
バックアップボリューム
SDXオブジェクトのスライスをバックアップボリュームに登録することはできません。
一般スライスのバックアップボリュームを使用します。
# /opt/FJSVswstc/bin/acmdevinfoset -b /dev/dsk/c1t0d2s6 acmdevinfoset completed # |
業務ボリュームがクラスタのリソースに登録されている場合、バックアップ前処理スクリプトにて業務ボリュームのアンマウントを行わないようにバックアップ前処理スクリプトを修正します。修正方法は、OSに対応した『ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書』の「バックアップ/リストアの前後処理」の業務ボリュームをアンマウントしたくない場合の手順を参照してください。
バックアップの例
以下は、コマンド実行例です。
# /opt/FJSVswstc/bin/acmbackup /dev/sfdsk/CLS01/dsk/VOL01:c1t0d1 /dev/sfdsk/CLS01/dsk/VOL01:c1t0d1 acmbackup completed # |
注意
クラスタリソースに登録されている業務ボリュームでは、テープのみを指定したバックアップは実施しないでください。テープのみへのバックアップでアンマウントを行わない場合は、採取したバックアップデータの整合性を確認することができないためです。
バックアップ時の状態
バックアップを実行できるのは、論理ボリュームを構成するSDXオブジェクトの状態が以下の状態になっている場合です。これ以外の状態になっている場合は、バックアップを実行することはできません。(SDXオブジェクトの状態は、SafeDISK/PRIMECLUSTER GDSのsdxinfoコマンドを用いてAdvancedCopy Managerテープバックアップが確認します)
ボリュームの状態が、"ACTIVE(起動中)"またはSTOP(停止)のとき
物理ディスクの状態が、"ENABLE(動作可)"のとき
スライスの状態が、"ACTIVE(起動中)"または"TEMP(切り離し中)"のとき
バックアップの前後処理
次のような場合、前後処理スクリプトは実行されません。
SDXオブジェクトのスライスがTEMP
14.2.2.4 acmrestore(リストア実行コマンド)でリストアを実施します。
以下は、コマンド実行例です。
# /opt/FJSVswstc/bin/acmrestore /dev/sfdsk/CLS01/dsk/VOL01:c1t0d1 /dev/sfdsk/CLS01/dsk/VOL01:c1t0d1 acmrestore completed # |
なお、業務ボリューム(リストア先ボリューム)が、クラスタのリソースに登録されている場合に、SDXオブジェクトのスライスのバックアップデータをリストアする手順は以下です。
リストア対象となるStorageサーバのクラスタサービスを停止します。
なお、Symfowareロググループのボリュームの場合は、この手順は不要です。
リストア先の共有ディスクをOnlineにします。
なお、Symfowareロググループのボリュームの場合は、この手順は不要です。
# sdxvolume -N -c クラス名 # |
リストア先ボリュームがミラーボリュームの場合、ミラーボリュームの切り離しをします。
シングルボリュームの場合、次の手順に進みます。
# sdxslice -M -c クラス名 -d ミラー先ディスク名 -v ボリューム名 -a jrm=off # |
注意
高速等価性回復モードのオフ(-a jrm=off)は必ず指定します。これをオフにしないでリストアをした場合、リストア後にミラーボリュームの組み込みを行うと、リストア前のデータに戻ってしまいます。
SWSTGNODEを設定した状態で、通信デーモンを起動します。
# /opt/FJSVswstf/bin/stgfwcom start # |
Storageサーバ上に、“物理IPアドレスファイル”を作成します。
ファイル名およびファイルのパスは、任意です。
以下にファイルの例を示します。
STGSRV_PHYS_IP=10.124.6.236 |
項目の意味は以下のとおりです。
項目 | 意味 |
|---|---|
STGSRV_PHYS_IP | リストアするStorageサーバのノードの物理IPアドレスを指定します。 |
リストアするStorageサーバのノードにログインします。
リストアは、14.2.2.4 acmrestore(リストア実行コマンド)の-fオプションに、手順5で作成したファイルを指定して実行します。
以下に、コマンド実行例を示します。
[Solaris/Linux/HP-UX/AIXの場合]
# /opt/FJSVswstc/bin/acmrestore -g 2 -m TAPE -f /home/acm/serverA_physIP /dev/sfdsk/CLS1/dsk/vol1:mplb48 /dev/sfdsk/CLS1/dsk/vol1:mplb48 acmrestore completed # |
[Windowsの場合]
C:\> C:\Win32app\AdvancedCopyManager\bin\acmrestore -g 2 -m TAPE -f D:\serverA_physIP g1d1p2 g1d1p2 acmrestore completed C:\> |
手順3でミラーボリュームの切り離しを実施している場合、ミラーボリュームを組み込みます。
# sdxslice -R -c クラス -d ミラー先ディスク名 -v ボリューム名 # |
リストア先の共有ディスクをOfflineにします。
なお、Symfowareロググループのボリュームの場合は、この手順は不要です。
# sdxvolume -F -c クラス名 # |
クラスタサービスを起動します。
なお、Symfowareロググループのボリュームの場合は、この手順は不要です。