レプリケーションは、関連システム(Symfoware/RDBとLinkexpress)を起動して、レプリケーション運用の準備を行った後、レプリケーション運用の開始の操作を行うことにより、運用状態に入ります。
レプリケーションの運用は、レプリケーション運用の一時停止の操作を行うと、一時的に停止します。この場合は、再びレプリケーション運用の開始を行うと、継続して運用ができます。
以降に、レプリケーション運用の操作手順を説明します。
関連システムの起動
レプリケーション運用のための準備
レプリケーション運用の開始
手動による同期操作
レプリケーション業務の取消し
レプリケーション運用の一時停止
レプリケーション運用の終了
関連システムの停止
なお、以降で説明する操作のうち、相手システムで実行する必要のある操作は、Linkexpressの業務定義で相手側ジョブ起動イベントとして定義することにより、自システムでも実行することができます。ここで、相手システムとは、自システムが複写元システムの場合は複写先システム、自システムが複写先システムの場合は複写元システムを指します。詳細は、“Linkexpress 運用ガイド”を参照してください。
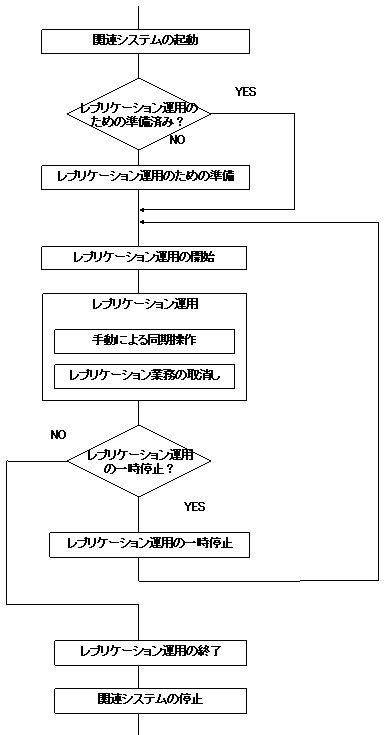
関連システムとは、Symfoware/RDBとLinkexpressを指します。
レプリケーションの運用を開始するためには、Symfoware/RDBとLinkexpressを起動する必要があります。
以下に、関連システムを起動するための手順を示します。
操作手順
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. Symfoware/RDBの起動 | - |
2. Linkexpressの起動 | - |
- | 3. Symfoware/RDBの起動 |
- | 4. Linkexpressの起動 |
説明
複写元システムのSymfoware/RDBを起動します。
複写元システムのLinkexpressを起動します。
複写先システムのSymfoware/RDBを起動します。
複写先システムのLinkexpressを起動します。
注意
1.から4.の順序に特に規定はありません。
レプリケーションの運用を開始するための準備を以下の手順で行います。
操作手順1:押出し型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 初期複写業務の開始 | - |
2. 差分ログの取得開始 | - |
操作手順2:取込み型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
- | 1. 初期複写業務の開始 |
2. 差分ログの取得開始 | - |
説明
全複写として定義した業務を指定して、“業務の開始”の操作を行います。この操作により、複写先データベースと複写元データベースの同期処理を実行します。
グループ単位のレプリケーションの場合は、レプリケーショングループに属するすべての抽出定義に対して、全複写業務を開始します。
“差分ログの取得開始”の操作を行います。この操作を行うと、差分ログがトランザクションログファイルと差分ログファイルに蓄積されるようになります。
注意
レプリケーション運用のための準備の操作は、複写元データベースに定義したすべての抽出定義に対して行います。一度操作を行うと、レプリケーションの運用を終了させるまで、再操作する必要はありません。
レプリケーション運用の開始手順を以下に示します。
操作手順1:押出し型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 一括差分複写業務の開始 | - |
2. 利用者プログラムの起動 | - |
操作手順2:取込み型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
- | 1. 一括差分複写業務の開始 |
2. 利用者プログラムの起動 | - |
説明
業務のスケジュール種別が一定時間間隔繰返し(rtry)のときは、一括差分複写として定義した業務を指定して、“業務の開始”の操作を行います。この操作を行った時間を基点にして、指定した時間間隔で、一括差分複写業務が繰り返し実行されます。
業務のスケジュール種別が日次(day)、週次(week)、月次(month)、年次(year)の場合は、指定した時刻に自動的に業務が実行されるので、業務の開始の操作を行う必要はありません。
次に、複写元システムで利用者プログラムを起動して複写元データベースの更新を行います。指定したスケジュールに従ってLinkexpress Replication optionが差分データを自動的に複写先データベースに複写します。
注意
業務のスケジュール種別に随時(real)が定義されている場合は、利用者プログラムの起動に関係なく、目的に合わせて“業務の開始”を操作してください。
手動による同期操作とは、スケジュール種別に“一定時間間隔繰り返し”など“随時”以外の業務スケジュールを指定したレプリケーション業務に対し、任意のあるタイミングで複写元データベースと複写先データベースの同期をとることをいいます。
“同期をとる”とは、複写元データベースと複写先データベースのデータを一致させることです。言い換えれば、複写されていない差分データが全くない状態にするということです。
手動による同期操作は、以下のような場合に行います。
業務スケジュールを有効にせずに複写元データベースと複写先データベースの同期状態を最新にしたい場合
差分ログファイルの残容量が少なくなってきたため、至急差分ログファイルに空きを作る場合
ここでは、一括差分複写業務を手動で操作する場合について説明します。
なお、全複写業務の説明は省略します。全複写業務は、基本的に初期創成や、複写元データベースと複写先データベースの同期ずれの復旧を目的としており、通常、スケジュール種別に“随時”を指定しているためです。
操作手順1:押出し型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 利用者プログラムの完了待ち | - |
2. 差分ログの追出し | - |
3. 一括差分複写業務の開始 | - |
4. 一括差分複写業務の中止 | - |
操作手順2:取込み型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 利用者プログラムの完了待ち | - |
2. 差分ログの追出し | - |
- | 3. 一括差分複写業務の開始 |
- | 4. 一括差分複写業務の中止 |
説明
利用者プログラムとの同期が必要な場合には、利用者プログラムの完了を待ってから操作を始めます。
“差分ログの追出し”の操作を行って、トランザクションログファイルに蓄積されている差分ログを差分ログファイルに追い出します。
“差分ログの追出し”の操作後、トランザクションログファイルのデータ部の使用率が0%になっていることを確認します。
一括差分複写として定義した業務を指定して、“業務の開始”の操作を行います。この操作により、一括差分複写業務がこの時点から開始されます。
(差分ログファイルの差分ログが、反映の対象になります)
一定時間間隔繰り返しなどの業務スケジュールを有効にしない場合は、業務の完了を待って、“業務の中止”操作を行います。この操作により、当日分のスケジュールが中止されます。
レプリケーション業務が異常完了した場合、同一の抽出定義名またはレプリケーショングループ名を指定したレプリケーション業務を開始することができません。
この場合は、まず、レプリケーション業務の取消しを実行します。その後、異常完了したレプリケーション業務の異常原因を取り除きます。また、異常完了したレプリケーション業務の種類または取り消した状態により、レプリケーション業務の復旧作業が必要な場合があります。レプリケーション業務の復旧作業については以下に説明します。また、レプリケーション業務の復旧作業を実施した後で、レプリケーション業務の再開を行うか、以下に示す方法でレプリケーション業務の開始の操作を行ってください。異常完了したレプリケーション業務の再開方法については、“2.2.3.1 レプリケーション業務の監視”または“2.2.2.4.3 業務の再開”を参照してください。
全複写業務で全件抽出処理の実行中の場合
(全件抽出処理の実行前を含む)
必要な復旧作業はありません。
全複写業務で全件抽出処理の実行後の場合
(データ送信またはデータ受信、格納処理、確定処理を含む)
先頭のイベントから再開するモードで再開する場合は、取消し対象の業務に対して、業務確定コマンドを実行する必要があります。業務確定コマンドについては“コマンドリファレンス”の“lxcmtdbコマンド”を参照してください。
一括差分複写業務で差分抽出処理の実行中の場合
(差分抽出処理の実行前を含む)
必要な復旧作業はありません。
一括差分複写業務で差分抽出処理の実行後の場合
(データ送信またはデータ受信、格納処理、確定処理を含む)
レプリケーション業務を取り消した後に再開する場合には、必要な復旧作業はありません。
レプリケーション業務を取り消した後にレプリケーション業務の運用を止める場合には、取消し対象の業務に対して、業務確定コマンドを実行する必要があります。業務確定コマンドについては“コマンドリファレンス”の“lxcmtdbコマンド”を参照してください。
さらに、業務確定コマンドを実行後、再開する場合には、必ず対象のデータベースに対する全複写業務を実行してください。
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 取消し作業の開始 | - |
2. レプリケーション業務の復旧作業 | - |
3. レプリケーション業務の開始 | - |
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
- | 1. 取消し作業の開始 |
- | 2. レプリケーション業務の復旧作業 |
- | 3. レプリケーション業務の開始 |
異常完了したレプリケーション業務は、業務中止コマンド(lxcanwrkコマンド)またはLinkexpressクライアントの“業務監視ウィンドウ”の操作を行うことにより、取り消すことができます。
異常完了したレプリケーション業務の異常原因を取り除いた後で、異常完了したレプリケーション業務の種類または取り消した状態により、レプリケーション業務の復旧作業を実施します。復旧作業の中で実行する業務確定コマンド(lxcmtdbコマンド)に抽出定義名またはレプリケーショングループ名を指定します。
レプリケーション業務の復旧作業の中で、グループ単位のレプリケーションの場合は、レプリケーショングループに属するすべての抽出定義に対して、全複写業務を開始します。
その後、必要に応じてレプリケーション業務を開始してください。
現在処理中のレプリケーション業務を取り消すことができます。取り消すことができるのは、処理中の業務だけです。すでに正常完了した(確定処理が完了した)業務については、取り消すことはできません。
なお、取り消したレプリケーション業務の種類または状態により、レプリケーション業務の復旧作業が必要な場合があります。レプリケーション業務の復旧作業については以下に説明します。また、レプリケーション業務の復旧作業を実施したあとで、以下に示す方法でレプリケーション業務の開始の操作を行ってください。
全複写業務で全件抽出処理の実行中の場合
(全件抽出処理の実行前を含む)
必要な復旧作業はありません。
全複写業務で全件抽出処理の実行後の場合
(データ送信またはデータ受信、格納処理、確定処理を含む)
先頭のイベントから再開するモードで再開する場合は、取消し対象の業務に対して、業務確定コマンドを実行する必要があります。業務確定コマンドについては“コマンドリファレンス”の“lxcmtdbコマンド”を参照してください。
一括差分複写業務で差分抽出処理の実行中の場合
(差分抽出処理の実行前を含む)
必要な復旧作業はありません。
一括差分複写業務で差分抽出処理の実行後の場合
(データ送信またはデータ受信、格納処理、確定処理を含む)
レプリケーション業務を取り消した後で再開する場合には、必要な復旧作業はありません。
レプリケーション業務を取り消した後で中止する場合には、取消し対象の業務に対して、業務確定コマンドを実行する必要があります。
業務確定コマンドを実行すると、複写先データベースに未反映の抽出データ格納ファイルが削除されます。詳細については“コマンドリファレンス”の“lxcmtdbコマンド”を参照してください。
さらにレプリケーション業務を中止後、再開する場合には、必ず対象のデータベースに対する全複写業務を実行してください。
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 取消し作業の開始 | - |
2. レプリケーション業務の復旧作業 | - |
3. レプリケーション業務の開始 | - |
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
- | 1. 取消し作業の開始 |
- | 2. レプリケーション業務の復旧作業 |
- | 3. レプリケーション業務の開始 |
異常完了したレプリケーション業務は、業務中止コマンド(lxcanwrkコマンド)またはLinkexpressクライアントの“業務監視ウィンドウ”の操作を行うことにより、取り消すことができます。
取り消したレプリケーション業務の種類または状態により、レプリケーション業務の復旧作業を実施します。復旧作業の中で実行する業務確定コマンド(lxcmtdbコマンド)に抽出定義名またはレプリケーショングループ名を指定します。
レプリケーション業務の復旧作業の中で、グループ単位のレプリケーションの場合は、レプリケーショングループに属するすべての抽出定義に対して、全複写業務を開始します。
必要に応じてレプリケーション業務を開始してください。
レプリケーション運用の一時停止とは、お客様業務の運用停止に合わせてレプリケーション運用を停止したい場合など、一時的にレプリケーション運用を停止することをいいます。
レプリケーション運用を一時的に停止する場合は、複写元データベースと複写先データベースの同期をとって、停止することを推奨します。
なお、レプリケーション対象のデータベースの定義変更や、抽出定義、DBサービス定義またはレプリケーション業務の変更など、レプリケーション運用の変更を目的とする場合は、“レプリケーション運用の終了”を行ってください。レプリケーションの終了については、“2.2.1.7 レプリケーション運用の終了”を参照してください。
以下にレプリケーション運用の一時停止の概念図を示します。
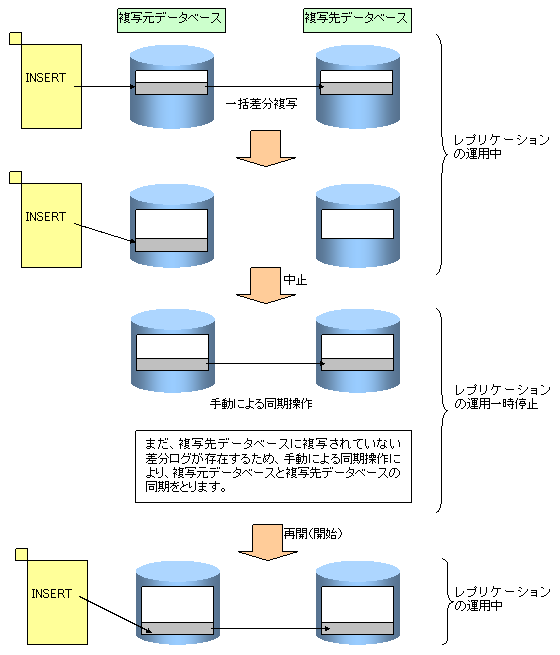
操作手順は以下のとおりです。
操作手順1:押出し型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 利用者プログラムの完了待ち | - |
2. 一括差分複写業務の完了待ち | - |
3. 一括差分複写業務の中止 | - |
4. 手動による同期操作 | - |
操作手順2:取込み型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 利用者プログラムの完了待ち | - |
- | 2. 一括差分複写業務の完了待ち |
- | 3. 一括差分複写業務の中止 |
- | 4. 手動による同期操作 |
説明
複写元データベースを更新する利用者プログラムが実行中でないことを確認します。実行中の場合は、利用者プログラムの完了を待ってから操作を始めてください。
停止したい業務が処理中でないことを確認します。処理中の場合は、業務の完了を待ってから操作を始めてください。
“業務の中止”の操作を行って、一括差分複写業務を中止します。
“手動による同期操作”を行い、複写元データベースと複写先データベースの同期をとります。
レプリケーション運用の終了とは、差分ログの取得を終了し、レプリケーションの運用をとり止めることです。
“レプリケーション運用の一時停止”同様、複写元データベースと複写先データベースの同期をとって、停止することを推奨します。
レプリケーション運用の終了は、以下のような場合に行います。
レプリケーション対象のデータベースの変更
抽出定義、DBサービス定義、レプリケーション業務の変更
修正プログラムの適用 など
操作手順1:押出し型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 利用者プログラムの完了待ち | - |
2. 差分ログの取得終了 | - |
3. 一括差分複写業務の完了待ち | - |
4. 一括差分複写業務の中止 | - |
5. 手動による同期操作 | - |
操作手順2:取込み型業務の場合
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
1. 利用者プログラムの完了待ち | - |
2. 差分ログの取得終了 | - |
- | 3. 一括差分複写業務の完了待ち |
- | 4. 一括差分複写業務の中止 |
- | 5. 手動による同期操作 |
説明
複写元データベースを更新する利用者プログラムが実行中でないことを確認します。実行中の場合は、利用者プログラムの完了を待ってから操作を始めてください。
差分ログの取得終了を行います。
停止したい業務が処理中でないことを確認します。処理中の場合は、業務の完了を待ってから操作を始めてください。
“業務の中止”の操作を行って、一括差分複写業務を中止します。
“手動による同期操作”を行い、複写元データベースと複写先データベースの同期をとります。
注意
レプリケーション運用の終了では、2.の“差分ログの取得終了”の操作で、差分ログの追出しが完了します。このため、レプリケーション運用の終了では、“手動による同期操作”中の“差分ログの追出し”の操作は必要ありません。
関連システムとは、Symfoware/RDBとLinkexpressを指します。
関連システムが停止すると、レプリケーションの運用が停止します。
以下に、関連システムを停止するための手順を示します。
操作手順
複写元システム | 複写先システム |
|---|---|
- | 1. Linkexpressの停止 |
- | 2. Symfoware/RDBの停止 |
3. Linkexpressの停止 | - |
4. Symfoware/RDBの停止 | - |
説明
複写先システムのLinkexpressを停止します。
複写先システムのSymfoware/RDBを停止します。
複写元システムのLinkexpressを停止します。
複写元システムのSymfoware/RDBを停止します。
注意
1.から4.の順序に特に規定はありません。