UNIX/IAサーバ側の環境設定には、以下の示す設定が必要です。
環境設定内容 | 対象サーバ |
|---|---|
データ転送用利用者登録 | デーモンまたはサービスを起動するUNIX/IAサーバ |
起動モード指定ファイルの作成 | サービスを起動するIAサーバ |
フィルターコマンド復帰コード変換ファイルの作成 | デーモンまたはサービスを起動し、フィルターコマンドを起動するUNIX/IAサーバ |
データ転送環境設定ファイルの設定 | データ転送コマンド、デーモンまたはサービスを起動するUNIX/IAサーバ |
データ転送用利用者登録は、XLデータムーバによるデータ転送を行う場合の設定です。SANデータ連携製品によるデータ転送だけを行う場合は必要ありません。
サーバシステムがUNIXサーバの場合
XLデータムーバでは、UNIXサーバ側のアカウントの権限でデータ転送を行います。
そのアカウントのホームディレクトリ配下に、".mftf"という利用者登録ファイルを以下の指示に従って作成してください。
ユーザ名 umask : :
1行あたり最大 256バイトまで指定できます。
ユーザ名とumaskの間は、空白(2バイト文字を除く)またはタブで区切ってください。
umaskは、8進数/3けた以下で指定してください。
umaskの省略値は、「133」です。フィルターコマンドを使用し、そのフィルターコマンドがディレクトリを作成する場合は実行権が必要です。
以下に例を示します。
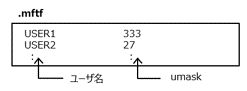
ユーザ名(USER ID)とumaskを指定します。
ユーザ名には以下のものを指定します。
MSPの場合、JOB文のUSERパラメタに指定するUSER IDを指定します。
XSPの場合、XSPのUSER IDを参照してUSER IDを指定してください。
ユーザ名(USER ID)をUNIXサーバ側のアカウントとして登録する必要はありません。
ユーザ名(USER ID)のかわりにKEYWORDとumaskを指定します。
ユーザ名(USER ID)をUNIXサーバ側のアカウントとして登録する必要はありません。
ユーザ名とumaskを指定します。
ユーザ名には、クライアントシステムで、転送コマンドを実行したときのユーザ名を、システムに定義してあるとおりに指定します。
ユーザ名をサーバシステム側のアカウントとして登録する必要はありません。
XLデータムーバでは、ユーザ認証の迂回をUNIXサーバ側の設定により可能にしています。
ユーザ認証の迂回を行うには、利用者登録ファイルの ユーザ名の箇所に "XLDATAMOVER" と登録してください。
ユーザ認証の迂回を行う場合の例を以下に示します。
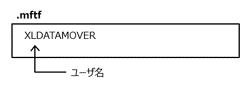
ユーザ認証の迂回を行う場合で、umaskを使用する場合の例を以下に示します。
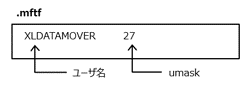
以下の例のように設定を行った場合、"XLDATAMOVER" 以後の認証は、迂回機能が優先され無効となります。
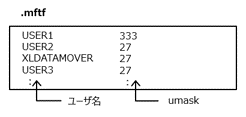
サーバシステムがIAサーバの場合
XLデータムーバがインストールされているフォルダ内に、"mftf.ini"という利用者登録ファイルを以下の指示に従って作成してください。
例えば、XLデータムーバがフォルダ "C:\Program Files\Datamover"にインストールされている場合、"C:\Program Files\Datamover\mftf.ini"を作成します。
ユーザ名 :
1行あたり最大 256バイトまで指定できます。
以下に記述例を示します。
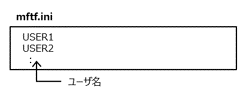
ユーザ名(USER ID)を指定します。
ユーザ名には以下のものを指定します。
MSPの場合、JOB文のUSERパラメタに指定するUSER IDを指定します。
XSPの場合、XSPのUSER IDを参照してUSER IDを指定してください。
ユーザ名をIAサーバ側のアカウントとして登録する必要はありません。
ユーザ名(USER ID)のかわりにKEYWORDを指定します。
ユーザ名をWindows側のアカウントとして登録する必要はありません。
ユーザ名を指定します。
ユーザ名にはクライアントシステムで、転送コマンドを実行したときのユーザ名を、システムに定義してあるとおりに指定します。
ユーザ名をWindows側のアカウントとして登録する必要はありません。
XLデータムーバでは、ユーザ認証の迂回をIAサーバ側の設定により可能にしています。
ユーザ認証の迂回を行うには、利用者登録ファイルの ユーザ名 の箇所に "XLDATAMOVER" と登録してください。
ユーザ認証の迂回を行う場合の例を以下に示します。
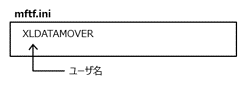
注意
この .mftfファイル(Windows の場合は mftf.iniファイル)はユーザ認証の目的で使用しているため、故意にあるいは誤って削除/編集されないよう .mftfファイル(Windows の場合は mftf.iniファイル)、およびそのファイルが格納されているホームディレクトリのパーミッションを適切に設定してください。
ユーザ名の大文字、小文字は区別されます。
ポイント
.mftfファイル(Windows の場合は mftf.iniファイル)を変更する場合:
データ転送実施中でなければ変更可能です。内容を変更しファイルを保存した時点で有効になります。起動済みのデーモンまたはサービスを再起動させる必要はありません。
XSPのUSER ID
XSPでのUSER IDは以下のとおりとなります。
XSPのPTFレベルが V00061 以降の場合は下記のとおりとなります。
USER IDは JOB 文の USERパラメタに指定された利用者名となります。
PASSWORDは、機密保護機能が導入されている場合、機密保護機能の利用者識別名に対するパスワードを指定します。
以下に V00061 以降の記述方法を示します。
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+
\ 名札 JOB ジョブ名
・ ・
・ ・
[,USER=利用者名]
[,PASSWORD=現在の利用者パスワード]
・ ・
・ ・
USERパラメタを指定しない場合、またはXSPのPTFレベルが V99101 以前の場合は JOB の入力方法により異なり、USER ID は以下のとおりとなります。
ジョブの入力方法 | USER ID | ||
|---|---|---|---|
STACK命令/マクロ指令によるジョブの入力 | コンソールからの入力 | コンソールに利用者属性の利用者識別名が付加されている場合 | 利用者属性の利用者識別名 |
コンソールに利用者属性の利用者識別名が付加されていない場合 | &XLMOVE | ||
自動発信コマンドによる入力 | &XLMOVE | ||
SCFプロシジャによる入力 | SCFプロシジャを入力したコンソールに利用者属性の利用者識別名が付加されている場合 | 利用者属性の利用者識別名 | |
SCFプロシジャを入力した利用者属性の利用者識別名が付加されていない場合 | &XLMOVE | ||
ジョブ制御文の命令文による入力(ジョブ制御文のSTACK文による入力も含む) | 機密保護機能が未導入の場合 | 指令文を入力した空間に付加されている利用者属性の利用者識別名 | |
機密保護機能が導入されている場合 | 指令文を入力したタスクに付加されている利用者属性の利用者識別名 | ||
CALLCMDマクロ命令による入力 | 機密保護機能が未導入の場合 | CALLCMDマクロ命令を発行した空間に付加されている利用者属性の利用者識別名 | |
機密保護機能が導入されている場合 | CALLCMDマクロ命令を発行したタスクに付加されている利用者属性の利用者識別名 | ||
AIFセション内でのSUBMITコマンド実行によるジョブの入力 | AIFセションのユーザ登録名 ただし、機密保護機能が導入されているシステムで、ユーザIDがRACF管理簿に登録されていない場合は"&XLMOVE" | ||
カード読取り装置、ホットリーダ処理指定のフロッピーディスク装置、またはRES端末からジョブを投入した場合 | USER文で指定した利用者識別名 | ||
起動モード指定ファイルの作成は、XLデータムーバによるデータ転送を行う場合の設定です。SANデータ連携製品によるデータ転送だけを行う場合は必要ありません。
サーバシステム側がIAサーバ(Windows)で、XLデータムーバの起動時にオプションの指定を行う場合は、起動モード指定ファイルの作成が必要になります。
OPTION= [-t] [-m]
終了メッセージの出力を指定するオプションです。
サーバシステム側のデータ転送処理が正常終了/警告終了した場合、終了メッセージをイベントログに出力します。
ただし、このメッセージはサーバシステム側の処理終了メッセージで、クライアントシステム側の処理終了を通知するものではありません。
省略された場合、終了メッセージの出力は行いません。
エラーメッセージの出力を指定するオプションです。
サーバシステム側でエラーが発生した場合、無条件にエラーメッセージをイベントログに出力します。
省略された場合、エラーメッセージの出力は行いません。ただし、クライアントシステム側にエラー情報が通知できなかった場合、エラーメッセージをコンソールに出力します。
起動モード指定ファイルは、以下の規則に従い作成してください。
定義ファイル名はXLデータムーバがインストールされているフォルダに、startup.ini のファイル名で作成してください。
1行あたり、最大256文字までとします。
コメントは # から開始し、行の最後までとします。
オプションを2つ以上指定する場合は、間に必ず1つ以上の空白(2バイト文字を除く)をおいて記述します。
上記の記述規則に従わない場合、エラーとなります。
なおオプションの記述は、1行だけ有効とし、2行目以降は無視されます。
参考
startup.iniファイルを変更する場合:
随時変更可能です。内容を変更しファイルを保存後、サービスを再起動させた時点で有効になります。
フィルターコマンド復帰コード変換ファイルの作成は、XLデータムーバによるデータ転送を行う場合の設定です。SANデータ連携製品によるデータ転送だけを行う場合は必要ありません。
XLデータムーバには、フィルターコマンドの復帰コードを利用者の任意の復帰コードに変換する機能があります。
変換機能の定義は、フィルターコマンド復帰コード変換ファイルに記述することにより有効になります。
構文形式
フィルターコマンド復帰コード変換ファイルは以下の規則に従い作成してください。
CMD=command n NORMAL n WARNING q n ERROR
定義ファイル名は、以下のとおり作成してください。
.filter_mftf (ユーザホームディレクトリ)
filter.ini (インストールされているフォルダ)
1行あたりの、最大文字数は1030バイトです。
コメントは # から開始し、行の最後までとします。
各情報の間は、空白(2バイト文字を除く)またはタブで区切ってください。
変換の定義の開始は CMD= とし、次の CMD= または、ファイルの最後で終了とします。
フィルターコマンドの復帰コードは、1行で1つの定義を行うこととします。
2回以上同一のフィルターコマンドまたは復帰コードの定義を行った場合、最初の指定だけ有効になります。
以下の場合は、正常終了(復帰コードが 0 )以外すべて異常終了とし、グローバルサーバ側に通知されます。
フィルターコマンド復帰コード変換ファイルが存在しない場合
フィルターコマンドの定義が存在しない場合
復帰コードの定義が存在しない場合
その他の理由により、復帰コードの定義が認識できない場合
各種情報
フィルターコマンドを1026バイト以内で指定します。
フィルターコマンドの有効な文字数は、サーバシステムのサーバ種別により異なります。
サーバ種 | 有効な文字数 |
|---|---|
UNIX/IAサーバ | 1026バイト |
グローバルサーバ | 66バイト |
ここに指定されたコマンドが、クライアントシステム側でデータ転送依頼時(バッチユーティリティや転送コマンド実行時)に指定した、フィルターコマンド(オプション部分を除く)と完全に一致する場合、復帰コード変換の対象となります。
また、フィルターコマンドのファイル名やディレクトリ名に空白が存在する場合、クライアントシステム側から転送依頼する際に、「 " 」(ダブルクォート)または「 ' 」(シングルクォート)で囲む必要があります。
(IAサーバ側のコマンドを指定する場合には、「 " 」(ダブルクォート)だけとなります。)
その場合、この指定もデータ転送依頼時に指定した、フィルターコマンド(オプション部分を除く)と同じ値を指定する必要があります。 (クォートで囲んだ値)
変換の対象となるフィルターコマンドの復帰コードを指定します。
指定できる範囲は以下のとおりです。
UNIXサーバ:0~255
IAサーバ:0~4294967295
フィルターコマンドの復帰コードが n で指定した値の場合、正常終了としてクライアントシステム側の復帰コードに以下の値を設定します。
MSP:0
XSP:10
OS/390:0
UNIX:0
Windows:0
フィルターコマンドの復帰コードが n で指定した値の場合、警告終了としてクライアントシステム側の復帰コードに q を設定します。
q に設定できる値は以下のとおりです。
MSP:0~4095
(4095以上の値が指定された場合は、4095が指定されたものとして動作します。)
XSP:10~89
(10未満の値が指定された場合は、10が指定されたものとして動作します。
90以上の値が指定された場合は、89が指定されたものとして動作します。)
OS/390:0~4095
(4095以上の値が指定された場合は、4095が指定されたものとして動作します。)
UNIX:0~255
(255以上の値が指定された場合は、255が指定されたものとして動作します。)
Windows:0~4294967295
(4294967295以上の値が指定された場合は、4294967295が指定されたものとして動作します。)
フィルターコマンドの復帰コードが n で指定した値の場合、異常終了としてクライアントシステム側の復帰コードに以下の値を設定します。
MSP:8
XSP:30
OS/390:8
UNIX:255
Windows:-1
例
以下に例を示します。
「C:\Windows\command\tfmdp32.exe」 を使用した場合、
フィルターコマンドの復帰コード "1" を NORMAL に、
フィルターコマンドの復帰コード "2" を "33" に、
フィルターコマンドの復帰コード "3" を ERROR に
変換する例と、
「C:\Program Files\soft\command\fmdp32.bat」 を使用した場合、
フィルターコマンドの復帰コード "1" を NORMAL に、
フィルターコマンドの復帰コード "2" を "33" に、
フィルターコマンドの復帰コード "3" を ERROR に
変換する例です。
# サンプル CMD=C:\Windows\command\tfmdp32.exe 1 NORMAL 2 WARNING 33 3 ERROR CMD="C:\\Program Files\\soft\\command\\fmdp32.bat" 1 NORMAL 2 WARNING 33 3 ERROR
参考
.filter_mftf(Windowsの場合は filter.iniファイル)を変更する場合:
データ転送実施中でなければ変更可能です。内容を変更しファイルを保存した時点で有効になります。起動済みのデーモンまたはサービスを再起動させる必要はありません。
データ転送環境設定ファイルは、XLデータムーバがデータ転送する際に必要な環境情報を設定するファイルです。
本ファイルに設定する情報には、以下の機能に関する情報があります。
データ転送統計情報出力機能
クラスタリング運用(仮想ノード名(UNIXサーバ)/仮想コンピュータ名(IAサーバ))
SANデータ連携製品によるデータ転送だけを行う場合は必要ありません。
本ファイルはインストール時に以下の場所に作成されます。
UNIXサーバの場合:/etc/mftf/env/mftfenv.conf
IAサーバの場合:インストールディレクトリ\mftfenv.ini
構文形式
データ転送環境設定ファイルは以下の規則に従い設定してください。
環境項目名 = 設定値 ←情報行
:1行あたりの、最大文字数は256バイトです。
コメントは # から開始し、行の最後までとします。
情報行の各情報(左辺、=、右辺)の間は、空白(2バイト文字を除く)またはタブで区切ってください。
1行に複数の情報行を記載することはできません。
右辺の後に、コメント等は付けられません。
同じ環境項目を複数指定できません。
環境項目名は大文字だけ有効です。
環境項目名、"="、および設定値はすべて必須です。
各種情報
環境項目名には以下のものが存在します。
環境項目名 | 意味 |
|---|---|
PUTDIR | データ転送統計情報出力ファイルの出力先ディレクトリの設定 |
PUTLINE | データ転送統計情報出力ファイルの切り換え設定 |
SERVERNAME | クラスタリング運用時に使用する仮想ノード名(UNIXサーバ)/仮想コンピュータ名(IAサーバ) |
各環境項目名に設定する設定値について、以下に記載します。
データ転送統計情報の出力ファイルの出力先ディレクトリ名を絶対パスで200バイト以内で設定します。
本環境項目およびPUTLINEの両方の設定を省略することで、データ転送統計情報は出力されません。
インストール時には、本設定はコメント行になっています。
値を設定する際には、PUTLINEの設定値を考慮に入れて、十分な空き領域が存在するディレクトリを指定してください。
データ転送統計情報の出力に必要な空き領域については、“データ転送統計情報出力に必要なデータ量の計算式”を参照してください。
データ転送統計情報の出力ファイルには、3つのファイルが存在し、サイクリックに利用します。
この出力ファイルを、切り換えるタイミングについてここで設定します。
本環境項目およびPUTDIRの両方の設定を省略することで、データ転送統計情報は出力されません。
インストール時には、本設定はコメント行になっています。
指定する内容には、以下の2種類が存在します。
各出力ファイルの切り換えを出力件数を元に行います。
各出力ファイルへの出力件数を、500~10000で指定します。
ここで指定した出力件数を満たした時点で出力先ファイルを切り換えます。
"DATE"と共に指定はできません。
各出力ファイルの切り換えを、1日単位で行います。
日付が変わった後、最初のデータ転送終了時に、出力ファイルを切り換えます。
"n"(出力件数) と共に指定はできません。
[13.0]
クラスタリングシステム上でXLデータムーバを使用する場合に、必要な設定項目です。
本項目は、クラスタリングシステム側の運用系/待機系の両サーバに設定する必要があります。
UNIXサーバの場合は、仮想ノード名、IAサーバの場合は、仮想コンピュータ名をASCIIコードで15バイト以内で定義します。
インストール時には、本項目は未設定になっています。
クラスタリング運用については、“付録G クラスタリング運用”を参照してください。
参考
PUTDIRとPUTLINEの2つの指定は、データ転送統計情報出力機能で使用される設定値です。
データ転送が実施されて、データ転送用ボリュームが使用される度に、データ転送統計情報出力ファイルに統計情報が出力されます。
よって、この指定は、XLデータムーバを使用した業務の運用や、ディスクの空き領域を考慮して設定する必要があります。
環境と不一致の設定をした場合、出力先ディレクトリに空き領域がなくなってしまう可能性があります。領域不足が発生すると、データ転送を実行する度にコンソール等にエラーが出力されます(データ転送は正常に完了します)。
そこで、データ転送統計情報出力機能が使用する、データ量の計算式を以下に記載します。
(1) | データ転送1件の情報量 | クライアントファイルのパス名長の最大値 + サーバファイルのパス名長の最大値 + 228バイト | |
(2) | 1つのデータ転送用ボリュームで使用するデータ転送統計情報出力ファイル3つの量 | PUTLINE = n指定の場合 | (1)の値 × PUTLINEで指定した出力件数 × 3 |
PUTLINE = DATE指定の場合 | (1)の値 × 1日に1つのデータ転送用ボリュームでデータ転送する回数 × 3 | ||
(3) | データ転送統計情報出力機能が使用する量 | (2)の値 × データ転送用ボリュームの使用数 | |
以上のことから、(3)でもとめた値が、必要な空き領域となります。
注意
データ転送環境設定ファイルとデータ転送統計情報出力ファイルの取扱いについて
データ転送環境設定ファイルは、データ転送コマンド、デーモンまたはサービスを必ず停止してから変更してください。
データ転送環境設定ファイルの設定値を変更した場合には、それまで出力されたデータ転送統計情報出力ファイルを、必要であれば退避し、必ず削除してください。