サーバシステム上のアプリケーションより他のサーバシステムのデータベースを利用する場合、以下の定義が必要です。
ホスト定義
クライアント環境管理簿定義
ホスト定義
TCP/IP手順を使用してサーバシステム上のアプリケーションより他のサーバシステムのデータベースを利用する場合、/etc/hostsファイルにIPアドレスおよびホスト名を設定します。
サーバとなるホストのIPアドレスをAAA.BBB.CCC.DDDの形式で1バイトごとに10進で設定します。
サーバとなるホストを識別するための一意な名称を英字で始まる20文字以内の英数字、ハイフン(“-”)で設定します。
以下にホスト定義の設定例を示します。
# IPアドレス ホスト名 1.0.0.1 sol00
ホスト定義を設定する場合は、rootまたはスーパユーザの権限でログインする必要があります。
ホスト定義で設定したIPアドレスは、相手システムの環境セットアップで定義する必要があります。
クライアント環境管理簿定義
サーバシステム上のアプリケーションから他のサーバシステムのデータベースを利用する場合、接続する相手システムの情報を定義します。以下にクライアント環境管理簿定義項目を示します。
接続する相手システムを識別するための一意な名称を英字で始まる18文字以内の英数字、ハイフン(“-”)、アンダースコア(“_”)または9文字以内の日本語で設定します。
“tcp”を設定します。
ホスト定義で登録したホスト名を設定します。
相手システムのRDA-SVで定義したポート番号を設定します。
相手システムのRDA-SVで定義したデータ資源名(アクセス環境名)を設定します。なお、データ資源名が不要な場合はハイフン(“-”)を設定してください。
相手システムがグローバルサーバの場合、EBCDICへの変換情報にkana,eijiまたはasciiのいずれかを設定してください。なお、相手システムがグローバルサーバ以外の場合は、“-”を設定してください。
なお、SQLサーバ名を重複して設定することはできません。
クライアント環境管理簿定義は、利用者定義ファイルに必要な項目をフリーフォーマットで記述し、これをrdafileコマンドにより固定フォーマットのRDA-SV定義ファイルに変換することで有効となります。
以下の図にRDA-SV定義ファイル作成手順を示します。
図2.3 RDA-SV定義ファイル作成手順
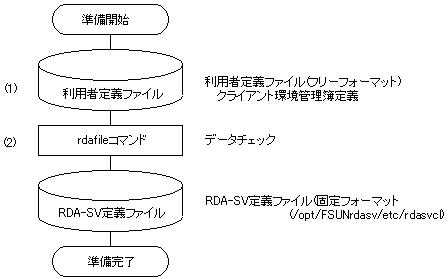
(1) 利用者責任で、エディタ(viなど)を使用して、利用者定義ファイルを事前に準備してください。
(2) RDA-SV定義ファイル作成コマンド(rdafile)により、RDA-SV定義ファイルを作成します。
ファイル形式は、/etc/hostsと同様のキャラクタベースのフリーフォーマットで、各エントリは必要な項目の情報を含む1行でクライアント環境管理簿定義を行います。
以下に利用者定義ファイル(クライアント環境管理簿定義)の設定例を示します。
# 利用者定義ファイル # クライアント環境管理簿定義 # SQL サーバ名 接続形態 ホスト名 ポート番号 データ資源名 EBCDIC変換情報 s-rdb tcp sol00 2005 - - d-rdb tcp uxp00 2002 dbrdb01 - m-rdb tcp mhost 2100 dbrdb02 eiji
各項目は、1つ以上の空白文字やタブ文字で区切られています。行の先頭(1バイト目)に“#”がある場合は、その行が注釈行であることを表します。行の途中に“#”を挿入しても、注釈文とはみなされません。
rdafileコマンドは、利用者定義ファイルに格納されているクライアント環境管理簿定義を読み込み、データのチェックを行いすべてのデータが正しい場合、クライアント環境管理簿定義を以下のRDA-SV定義ファイルに格納します。
/opt/FSUNrdasv/etc/rdasvcl : RDA-SV定義ファイル
rdafileコマンドの詳細は、“第3章 運用操作”およびmanコマンドを利用して参照してください。