サーバシステムの利用者が作成したシェルを利用する場合、以下の定義が必要です。
シェル連携定義
シェル連携定義
パソコンから利用者が作成したシェルを実行するために必要となるシェル連携情報を定義します。以下にシェル連携定義項目を示します。
パソコンに公開するシェルの処理を識別するための一意な名称を36文字以内の英数字、ハイフン(“-”)、アンダースコア(“_”)または18文字以内の日本語で設定します。
シェル名をフルパスで設定します。
シェルを実行するときのパラメタの有無を設定します。パラメタが複数ある場合は、パラメタ全体を1つの文字列として扱います。パラメタがある場合は“1”、ない場合は“0”を設定してください。
シェルに関するコメントを100文字以内の英数字または50文字以内の日本語で設定します。
シェル連携定義は、利用者定義ファイルに必要な項目をフリーフォーマットで記述し、これをrdafileコマンドにより固定フォーマットのRDA-SV定義ファイルに変換することで有効となります。
以下の図にRDA-SV定義ファイル作成手順を示します。
図2.4 RDA-SV定義ファイル作成手順
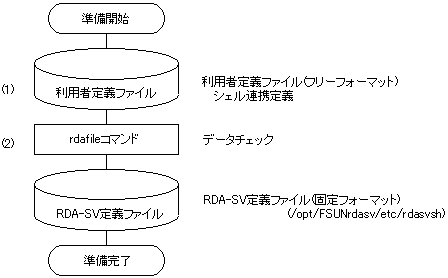
(1) 利用者責任で、エディタ(viなど)を使用して、利用者定義ファイルを事前に準備してください。
(2) RDA-SV定義ファイル作成コマンド(rdafile)により、RDA-SV定義ファイルを作成します。
ファイル形式は、キャラクタベースのフリーフォーマットで、各エントリは必要な項目の情報を含む1行でシェル連携定義を行います。
以下に利用者定義ファイル(シェル連携定義)の設定例を示します。
# 利用者定義ファイル # シェル連携定義 # ALIAS 名 フルパス名 パラメタの有無 コメント ××業務 /home/gyoumu/shell01 0 ××発注業務 △△業務 /home/gyoumu/shell02 1 △△business
各項目は、1つ以上の空白文字やタブ文字で区切られています。行の先頭(1バイト目)に“#”がある場合は、その行が注釈行であることを表します。行の途中に“#”を挿入しても、注釈文とはみなされません。
rdafileコマンドは、利用者定義ファイルに格納されているシェル連携定義を読み込み、データのチェックを行いすべてのデータが正しい場合、シェル連携定義を以下のRDA-SV定義ファイルに格納します。
/opt/FSUNrdasv/etc/rdasvsh : RDA-SV定義ファイル
rdafileコマンドの詳細は、“第3章 運用操作”およびmanコマンドを利用して参照してください。
サーバシステム起動後にシェル連携定義を変更(追加、削除、更新)した場合、修正した定義情報はサーバシステムの再起動時に反映されます。したがってサーバシステム運用中に変更した定義を反映したい場合は、サーバシステムの停止および再起動を行わなければなりません。
なお、マルチRDBを使用している場合、全サーバシステムの停止・起動が必要となります。