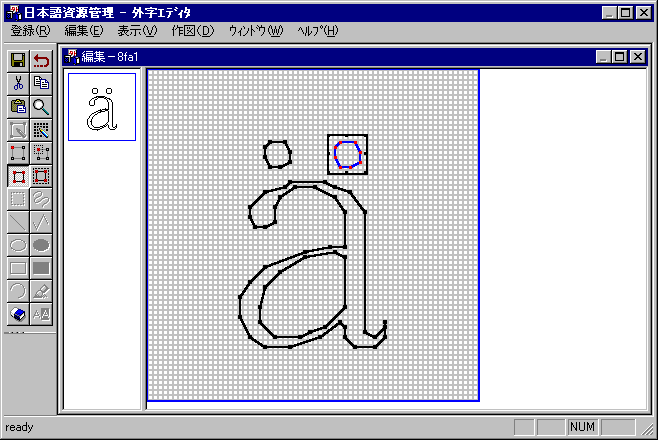外字の作成、更新方法を説明します。
『操作』
[外字一覧]ウィンドウから作成、更新を行う外字を選択します。
作成の場合は、登録されていない文字コードを選択します。
図4.38 作成、更新文字の選択
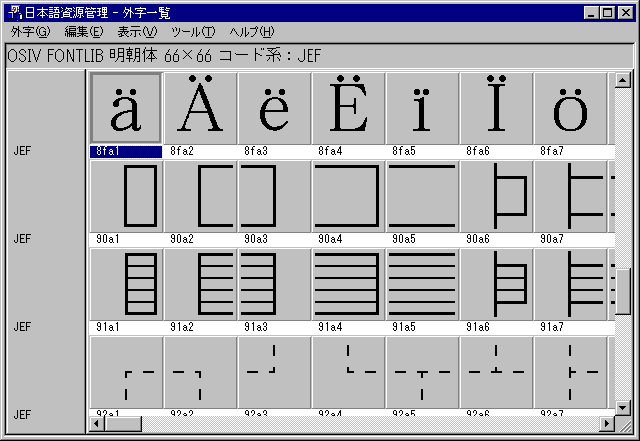
[外字]メニューの[外字編集]をクリックします。
→ 外字エディタの編集画面が表示されます。
[外字一覧]ウィンドウで選択されているフォントシステムのデータ形式に従って、ドット編集画面、アウトライン編集画面が表示されます。ただしデータ形式がAPPの場合、30×30以下の文字サイズの外字はドット編集画面が表示されます。
図4.39 ドット編集画面
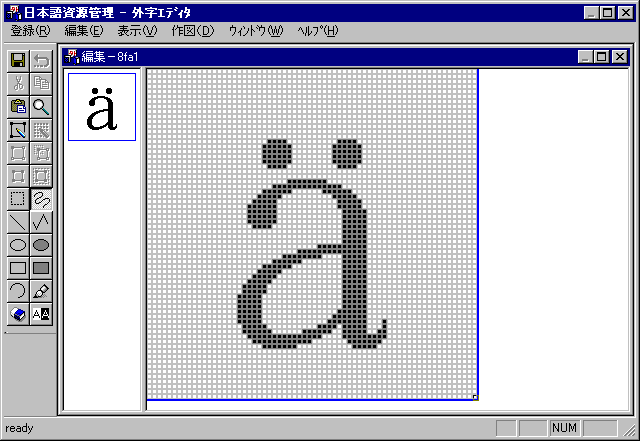
図4.40 アウトライン編集画面
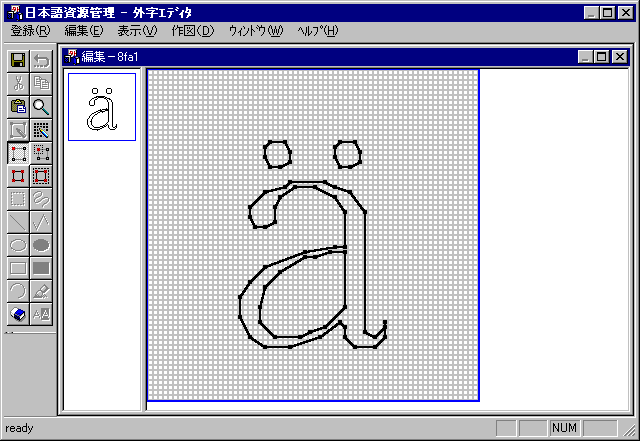
注意
コードの対応定義がない文字(外字一覧でコードの部分が「-」(ハイフン)になっている文字)を編集する場合、他のフォントシステムに移行したときに使えなくなる恐れがあります。
TrueTypeフォントは、空白の文字を作成することができません。すべてのドットまたはアウトラインのデータを消して保存すると、その文字を削除したことになります。
参考
外字エディタは、以下の操作でも実行できます。
[外字一覧]ウィンドウで作成、更新を行う外字をダブルクリック
外字エディタの起動時には、[日本語資源管理]ウィンドウで指定したフォントシステム(ドットまたはアウトライン)に従ったモードで、編集画面が表示されます。
この編集モードをドット、アウトラインそれぞれのモードに変更し、それぞれの機能で編集することができます。
編集モード
ドット編集
アウトライン編集
『操作』
外字エディタの[編集]メニューの[アウトライン編集]または[ドット編集]をクリックします。
または、以下の“図4.41 編集モードのアイコン”のツールバーのアイコンをクリックします。
現在の編集モードは選択できません。
図4.41 編集モードのアイコン
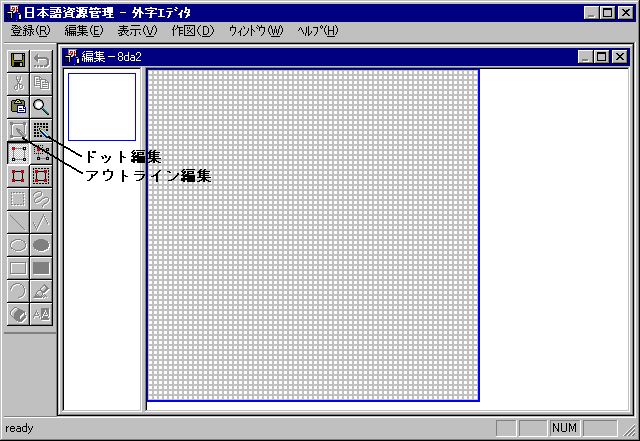
ドット編集機能では、以下の線、図形を描画することができます。
また、消去することもできます。
直線
折れ線
自由線
楕円
塗りつぶし楕円
長方形
塗りつぶし長方形
円弧
消しゴム
また、描画機能以外にも以下の機能があります。
筆サイズ変更
筆サイズを元に戻す
ネガポジ反転
『操作』
外字エディタの[作図]メニューから描きたい線、図形を選んでクリックします。
または、“図4.42 ドット編集のアイコン”のツールバーのアイコンをクリックします。
図4.42 ドット編集のアイコン
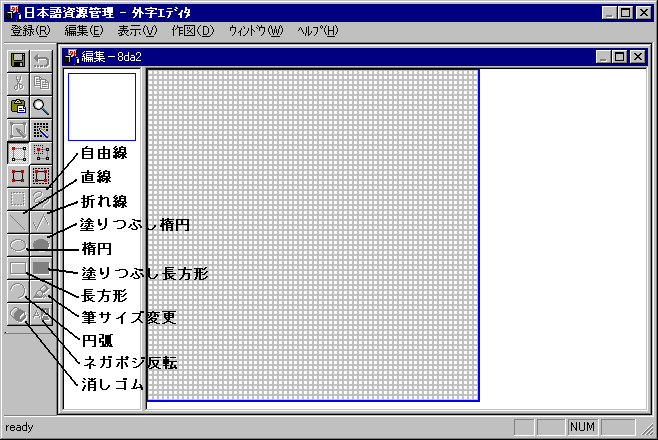
描きたい線、図形を操作します。
折れ線の開始位置からマウスをドラッグします。または、折れ線の開始位置で左クリックします。
屈曲点位置で、左ボタンを離します。または、再度左クリックします。
操作2の処理を繰り返し、折れ線の終了位置にきたら、マウスをダブルクリックします。または、ほかの処理を選択します。
LPモード文字とは、30×24ドットで構成される文字です。ASPに直結(SIF接続)されたレーザ系カット紙プリンタの縮小文字印刷用として使われます。
この文字は、30×30の文字を30×24の構成に変更するため、縦6ドット分削除する情報(LPモード制御ビット)を持っています。
日本語資源管理では、LPモード制御ビットを以下のように処理します。
図4.44 LPモード制御ビット
LPモード制御ビットの処理は、以下のフォントシステムの文字パターンに対して有効です。
文字パターン辞書のサイズ(30×30)
上下隅のビットは、入力不可です。
LPモード制御ビットは、必ず6ライン分の制御ビットをONにします。
LPモード制御ビットの詳細については、ADJUSTのマニュアルを参照してください。
アウトライン編集機能には、以下の機能があります。
屈曲点選択
閉曲線結合
閉曲線分割
『操作』
外字エディタの[編集]メニューから使用する機能をクリックします。
屈曲点の追加、移動、削除を行います。
新規閉曲線作成
開始点を決め、マウスをクリックします。
図4.45 新規閉曲線作成[1]
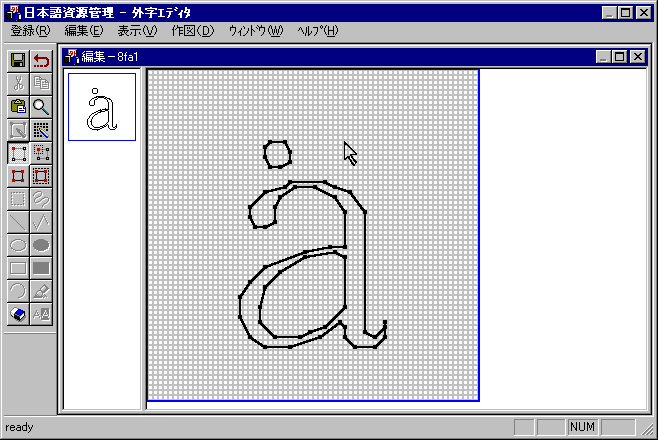
屈曲点位置で、マウスをクリックします。
図4.46 新規閉曲線作成[2]
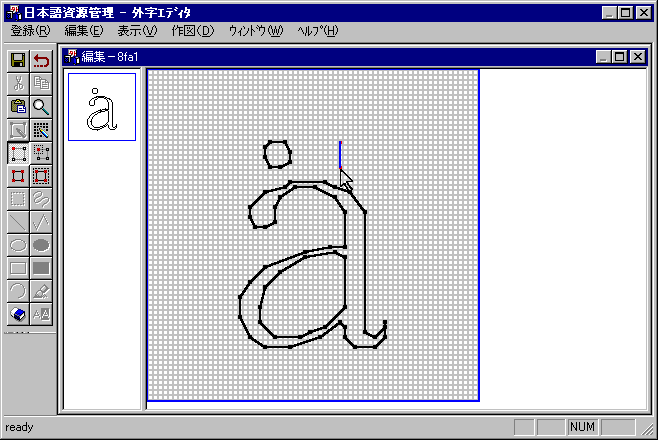
操作2の処理を繰り返し、最終点として、操作1で指定した屈曲点と隣り合う屈曲点位置で、マウスをダブルクリックします。
図4.47 新規閉曲線作成[3]
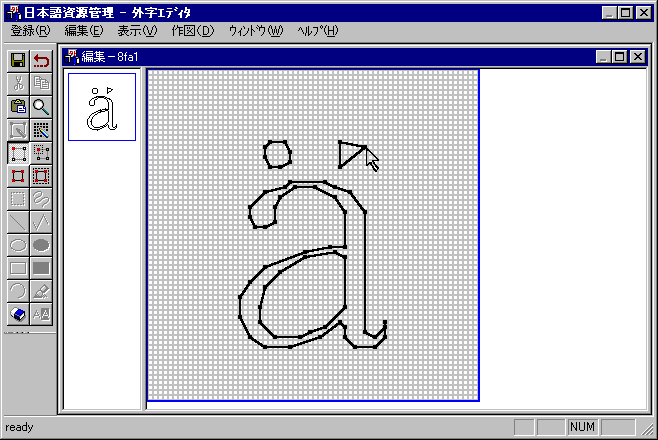
既存の閉曲線への追加
既存の屈曲点(開始点)を決め、マウスをダブルクリックします。
図4.48 既存の閉曲線への追加[1]
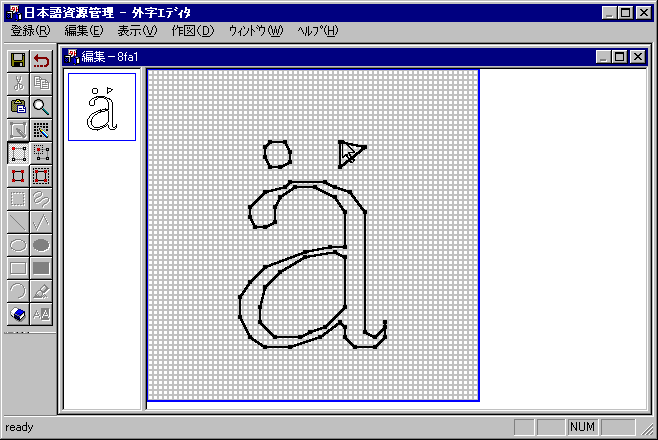
新しく追加する屈曲点位置を決め、マウスをクリックします。
図4.49 既存の閉曲線への追加[2]
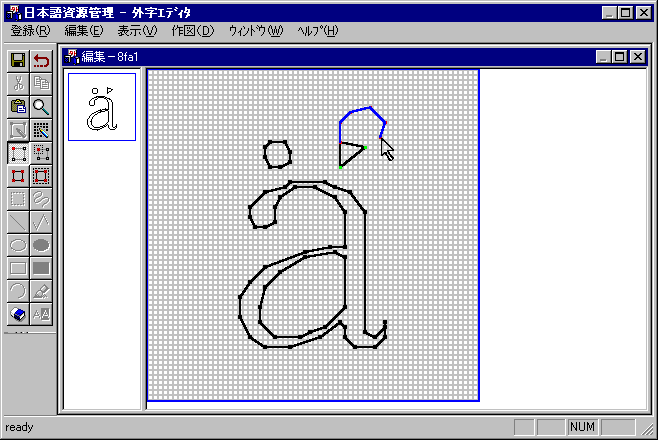
操作2の処理を繰り返し、最終点として、操作1で指定した屈曲点と隣り合う屈曲点位置(既存の閉曲線上)で、マウスをダブルクリックします。
図4.50 既存の閉曲線への追加[3]
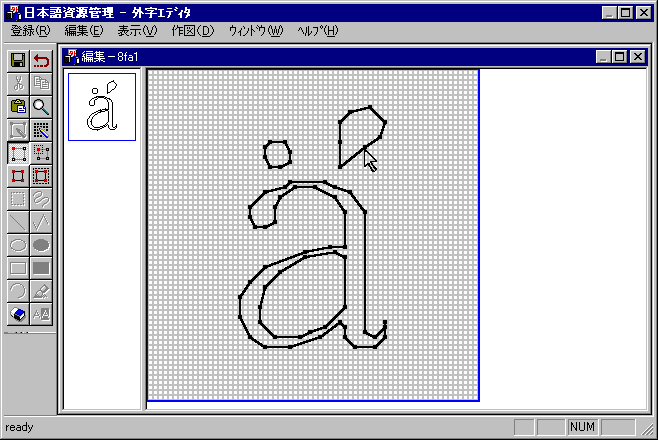
移動させたい屈曲点の位置から、マウスをドラッグします。
図4.51 移動[1]
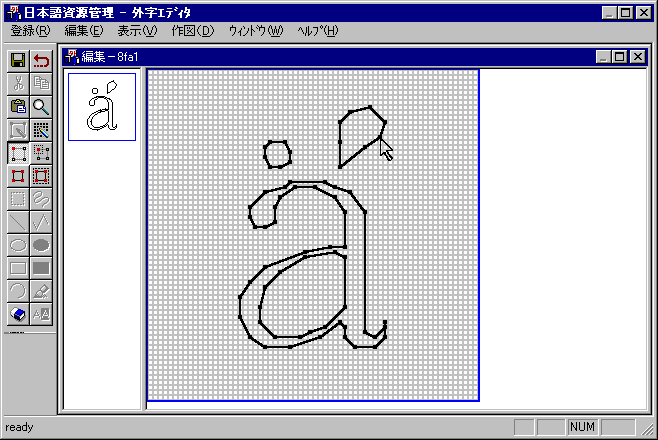
移動位置にきたら、左ボタンを離します。
図4.52 移動[2]
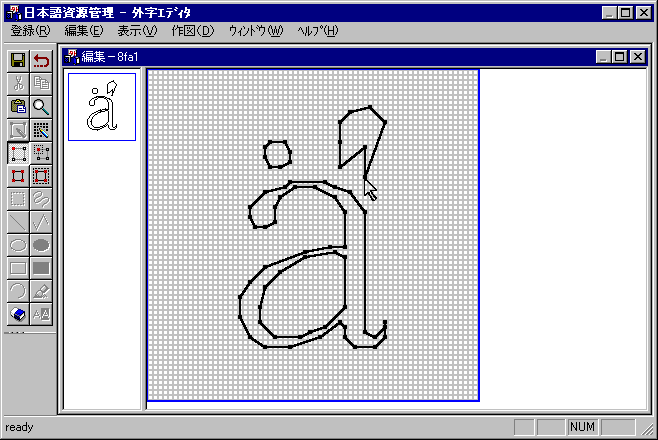
削除したい屈曲点を、マウスでクリックします。
図4.53 削除[1]
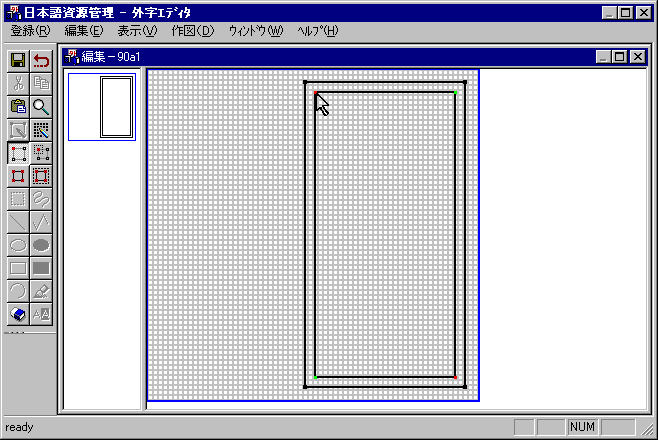
消しゴムを選択します。
図4.54 削除[2]
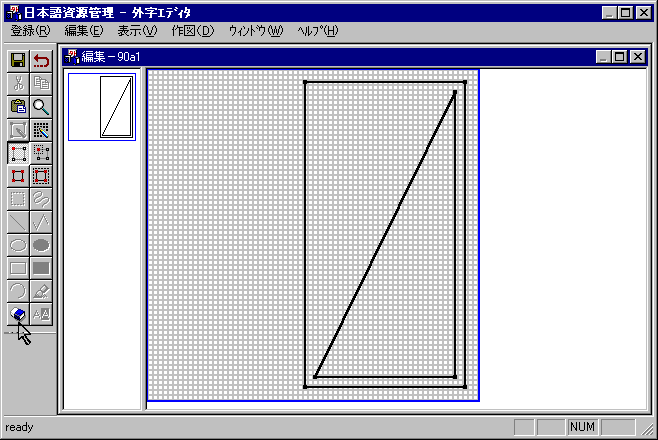
二組の閉曲線の結合を行います。
一方の閉曲線上の屈曲点(結合点1)を決め、マウスをクリックします。
図4.55 閉曲線結合[1]
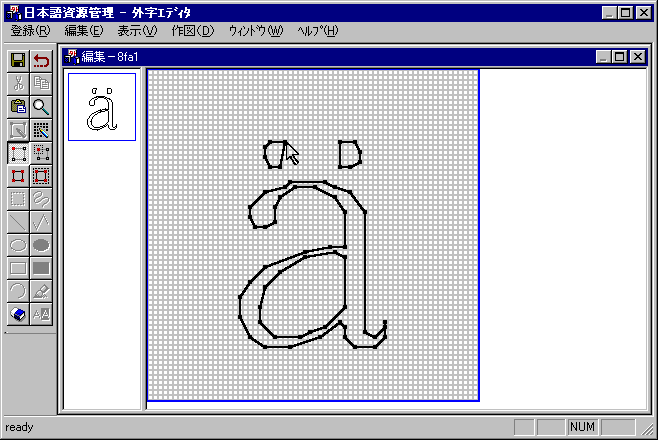
もう一方の閉曲線上に存在する屈曲点(結合点2)を決め、マウスをクリックします。
→ 結合点1と結合点2が結びつきます。
図4.56 閉曲線結合[2]
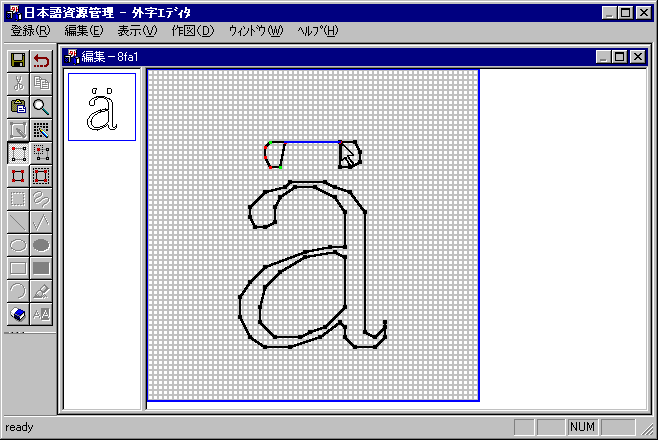
別の屈曲点(結合点3)を、マウスでクリックします。
図4.57 閉曲線結合[3]
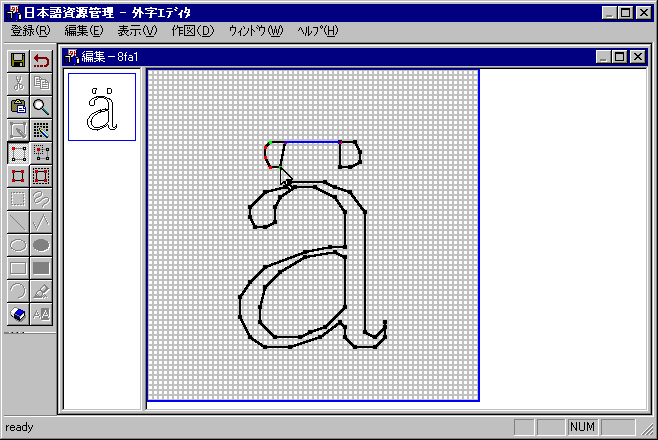
もう一方の閉曲線上に存在する屈曲点(結合点4)を決め、マウスをクリックします。
→ 結合点3と結合点4が結びつきます。
図4.58 閉曲線結合[4]
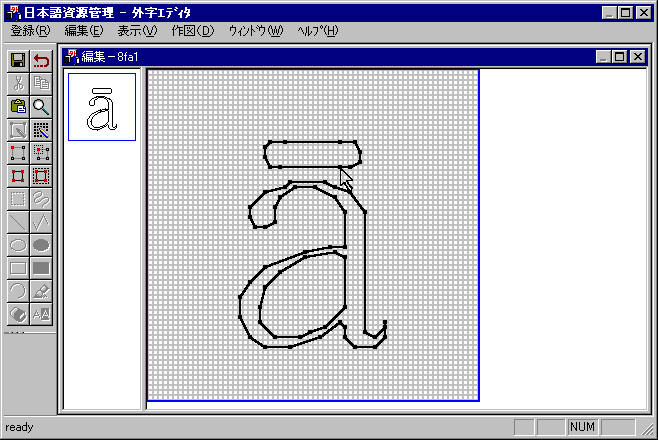
一組の閉曲線を切り離し、二組の閉曲線とします。
閉曲線上の屈曲点(分割点1)を決め、マウスをクリックします。
図4.59 閉曲線分割[1]
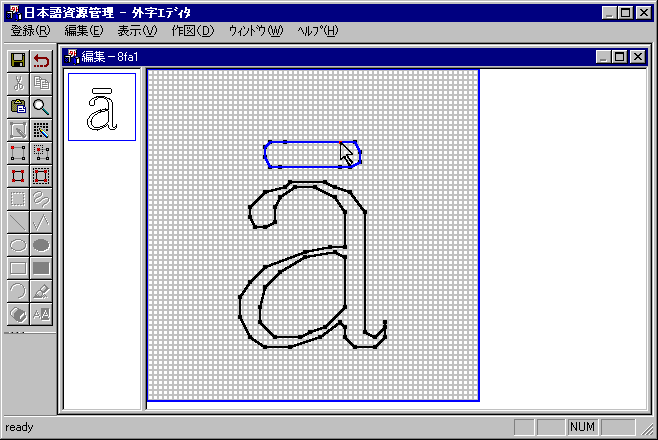
操作1で指定した屈曲点と接続する屈曲点(分割点2)を決め、マウスをクリックします。
図4.60 閉曲線分割[2]
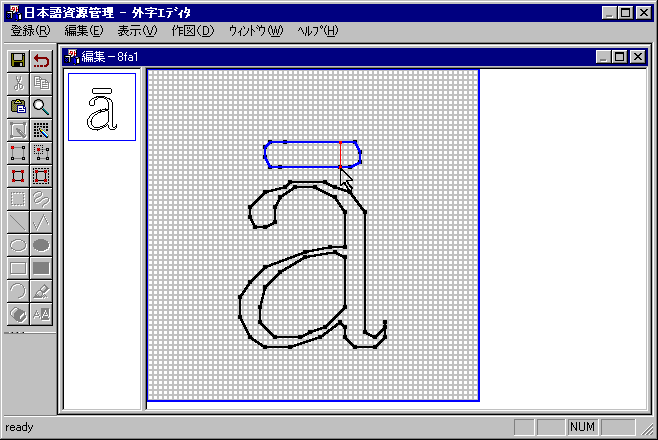
操作1で指定した屈曲点と同一閉曲線としたい屈曲点を決め、マウスをクリックします。
図4.61 閉曲線分割[3]
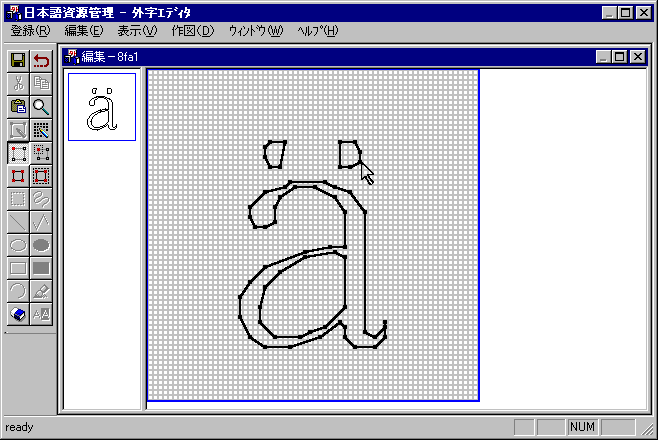
注意
外字(1文字パターン)内で編集できる屈曲点は、4000点以下です。
選択した屈曲点を含む閉曲線が複数存在する場合には、マウスをダブルクリックして、選択したい閉曲線を決めることができます。選択中の閉曲線は、青色の直線で描かれ、選択中の屈曲点は、青色の矩形で表示されます。
範囲の指定には、以下の方法があります。
範囲選択
閉曲線選択
閉曲線範囲選択
屈曲点範囲選択
指定処理を行ってから、切り取り、コピー、消しゴムによる削除を行います。
また、以下に示すリサイズハンドルをマウスでドラッグすることにより、拡大/縮小、移動が可能です。
図4.62 リサイズハンドル
『操作』
外字エディタの[編集]メニューから範囲指定の機能をクリックします。
または、以下のツールバーのアイコンをクリックします。
図4.63 範囲指定のアイコン
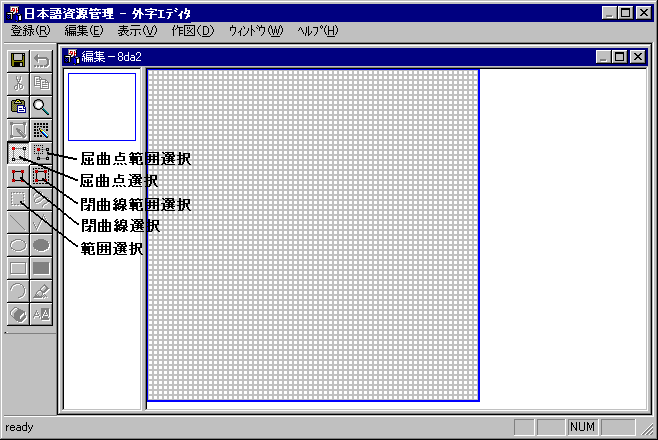
使用する機能を選択します。
指定した長方形内を選択状態にします(ドット編集時に有効です)。
選択をしたい部分を含むように長方形を描きます。
長方形の四隅のいずれかから対角線を引くようにマウスをドラッグします。
図4.64 範囲選択[1]
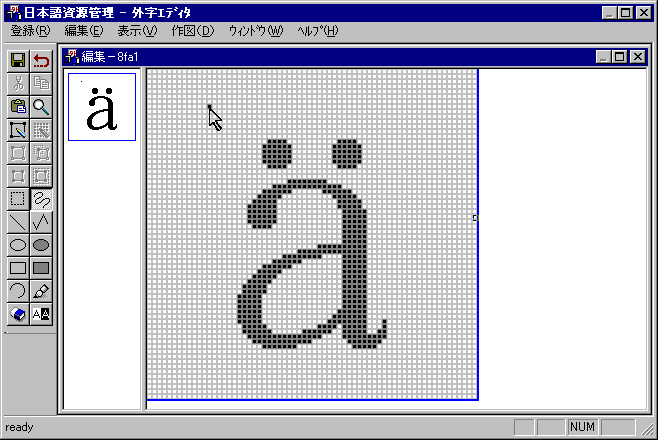
終了位置で、左ボタンを離します。
図4.65 範囲選択[2]
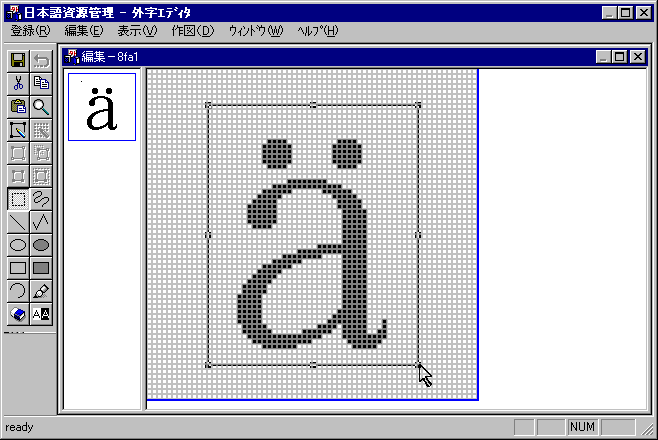
指定した屈曲点を含む閉曲線を、選択状態(閉曲線は1つだけ選択可能)にします。
アウトライン編集時に有効です。
選択したい閉曲線を構成する屈曲点(1点)を、マウスでクリックします。
図4.66 閉曲線選択[1]
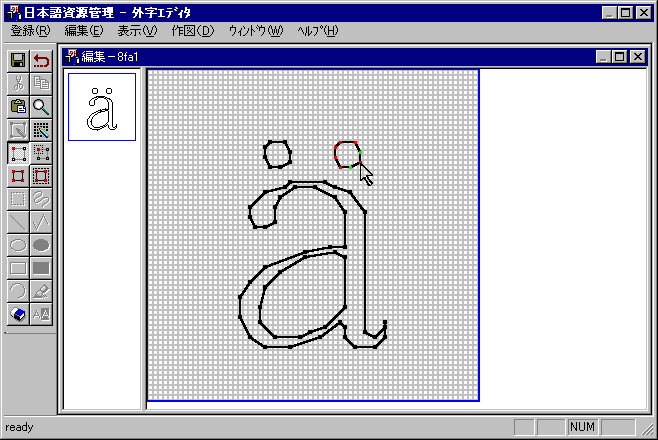
→選択状態になります。
図4.67 閉曲線選択[2]