伝送路二重化機能では、クラスタシステムにおいて以下の運用形態をサポートしています。
運用待機構成(1:1およびN:1)
相互待機構成
カスケード構成
移動待機構成
表5.1 クラスタ対応機能一覧に、各二重化方式のクラスタ対応機能一覧を示します。
二重化方式 | 運用待機 | 運用待機 | 相互待機 | カスケード | 移動待機 | SISの |
|---|---|---|---|---|---|---|
高速切替方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
NIC切替方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GS/SURE連携方式 | ○ | × | × | × | × | × |
[記号の説明]○:サポート、×:未サポート
クラスタ切替え時の引継ぎ情報は、仮想インタフェースに割当てる引継ぎIPアドレスのみです。MACアドレスやシステムノード名の引継ぎはサポートしていません。
また、仮想インタフェースが使用する物理インタフェースを、クラスタの引継ぎ対象(MACアドレス、IPアドレス)に設定することはできません。
表5.2 サポートするクラスタ引継ぎ情報に、サポートする引継ぎ情報を示します。
クラスタ運用形態 | IPアドレス | MAC | IPアドレス | IPアドレス | IPアドレス |
|---|---|---|---|---|---|
1:1運用待機 | ○ | × | × | × | × |
N:1運用待機 | ○ | × | × | × | × |
相互待機 | ○ | × | × | × | × |
カスケード | ○ | × | × | × | × |
移動待機 | ○ | × | × | × | × |
[記号の説明]○:サポート、×:未サポート、-:組み合わせなし
注意
クラスタ運用形態である移動待機構成での伝送路二重化機能の構築(設定)は、カスケードの場合と同じように行います。
高速切替方式を使用する場合、クラスタシステムを構成するノード以外に、通信相手として高速切替方式を使用しているホストが1台以上必要です。伝送路監視先がクラスタシステムを構成する1ノードしかない場合、運用ノードと待機ノードで伝送路異常が同時に検出され、クラスタ切替えを正常に行うことができません。
高速切替方式またはNIC切替方式において、引継ぎ仮想インタフェースとしてIPv6アドレスを使用した場合、ノード切替え後に通信が再開できるまで、およそ30秒程度の時間がかかる場合があります。この場合、運用ノードと待機ノードの双方であらかじめIPv6ルーティングデーモン(in.ripngd)を起動しておくことにより、ノード切替え後、即座に通信を再開させることができます。詳細については、本マニュアルの“F.2 トラブルシューティング”を参照してください。
Solarisゾーンにより割り当てられた論理仮想インタフェース、およびIPアドレスは、クラスタ切替えによる引継ぎを行うことはできません。運用ノード上ですべての伝送路に異常が発生した場合、ゾーンの通信を継続することはできません。
GS/SURE連携方式については、待機ノード側の仮想インタフェースは非活性であり、待機ノード側の通信相手先監視は停止します。このため、待機ノード上のGLSリソース状態監視を行うことはできません。従って、GS/SURE連携方式ではクラスタアプリケーション作成時に“StandbyTransition”属性を設定する必要はありません。
図5.1 仮想インタフェースのクラスタ切替えに、仮想インタフェースのクラスタ切替えの例を示します。
図5.1 仮想インタフェースのクラスタ切替え
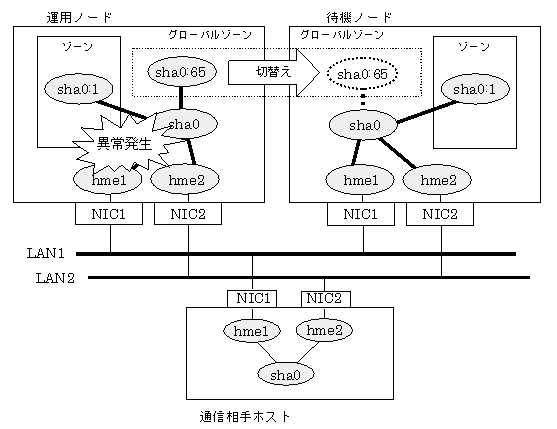
クラスタ切替え対象となる引継ぎ仮想インタフェースの論理ユニット番号は、65以降が使用されます。(sha0:65、sha0:66等)