DBミラーリングシステムの環境設定のために、以下のファイルを編集します。
DBミラーリング動作環境ファイル
RDB構成パラメタファイル
BC構成パラメタファイル
RLP動作環境ファイル
RLP定義ファイル
各ファイルの関係を以下に示します。
図5.4 DBミラーリングシステムを構成する各ファイルの関係
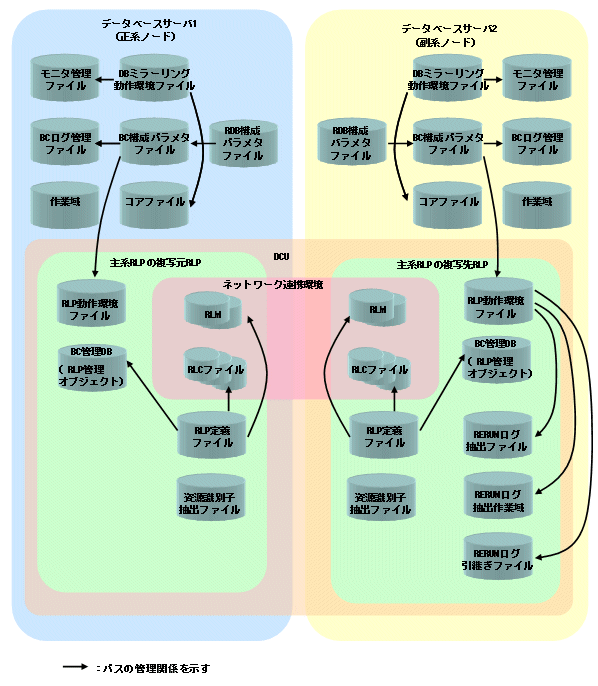
以降に、各定義ファイルの編集方法について説明します。
注意
Mirroring Controllerを使用する場合、DBミラーリング動作環境ファイルの編集方法については“D.1 DBミラーリング動作環境ファイルの編集”を参照してください。
DBミラーリングシステムの動作環境に関する定義は、DBミラーリング動作環境ファイルに定義します。
DBミラーリング動作環境ファイルは、UNIX系ファイルで作成します。
DBミラーリング動作環境ファイルは、両ノードで設定します。環境定義以外は両ノードで定義内容を一致させてください。環境定義は、両ノードの環境に合わせて編集してください。
以下のディレクトリ配下に作成してください。
/opt/FJSVsymdx/etc
ひな型を複写し、以下のファイル名で作成してください。
“RDBシステム名”.dx
sysconfig.dx
ひな型は、/opt/FJSVsymdx/demo/std配下に、下表に示すファイル名で格納してあります。
ひな型ファイルでは、設定値を編集する必要のあるパラメタはコメントになっています。設定値にはサンプル値が記述されていますので、設定値を編集した後、行の先頭の“#”を削除して、その行を有効にしてください。
ファイル名 | 内容 |
|---|---|
sysconfig.dx.net.utf-8 | 日本語版(UTF-8) |
sysconfig.dx.net.euc | 日本語版(EUC) |
sysconfig.dx.net.sjis | 日本語版(SJIS) |
sysconfig.dx.net | 英語版 |
DBミラーリング動作環境ファイルに記述する定義種別と定義内容を以下に示します。
種別 | 定義種別 | 定義内容 | 記述の省略 |
|---|---|---|---|
通信タイプ | RLPの通信タイプ | 不可 | |
環境定義 | 自側のIPアドレスまたはホスト名 | 不可 | |
相手側のRDBシステム名 | 不可 | ||
相手側のIPアドレスまたはホスト名 | 不可 | ||
相手側のポート番号 | 不可 | ||
モニタ管理ファイルの配置先ディレクトリの絶対パス名 | 不可 | ||
モニタデーモンのコアファイル出力先ディレクトリの絶対パス名 | 不可 | ||
ネットワーク連携の設定 | RERUNログ転送結果の待ち時間 | 可 | |
LAN断線時の再接続リトライ回数、再接続タイムアウト時間、およびリトライ間隔 | 可 | ||
ノード間の監視設定 | ハートビートを行う間隔 | 可 | |
ハートビートの異常を検知するまでのタイムアウト時間 | 可 |
ポイント
DBミラーリング動作環境ファイルの環境定義パラメタ、およびネットワーク連携設定のパラメタは、モニタデーモンを起動することで有効となります。またその他のパラメタは、DBミラーリングサービスを開始することで有効となります。
参照
DBミラーリングシステムの運用開始後に各パラメタを変更する場合の手順は、“10.2 DBミラーリングシステムの定義ファイルの環境変更”を参照してください。
利用者は、エディタを使用して、このテキストファイルに各パラメタを定義します。記述形式は、以下のとおりです。
なお、行の先頭が番号記号“#”の場合、その行はコメント行として扱われます。また、行の途中に番号記号“#”を指定することはできません。
定義指示文<改行> :
各行の定義指示文の記述形式は、次のとおりです。
定義種別 = [指定値1][,指定値2]・・・
注意
定義指示文は複数行にまたがって記述することはできません。
等号“=”前後に空白、タブを指定することができます。
コンマ“,”前後に空白、タブを指定することができます。
指定値がパス名の場合は、パス名中に空白、タブ、コンマ“,”、セミコロン“;”および番号記号“#”の指定はできません。
大文字と小文字は、区別して扱われます。
ポイント
同じパラメタを複数記述した場合、最後に書いた記述が有効となります。
各パラメタの説明
モニタデーモンがノード間通信を行うための自側のIPアドレスまたはホスト名を指定します。
ホスト名を指定する場合は、“H.1 hostsファイルの編集”を参照してください。
なお、モニタデーモンのノード間通信は、DBミラーリングサービスの運用を確実にするため、管理用のLANおよびデータ転送用のLANを設定します。
記述形式は、以下のとおりです。
OWN_NODE_ADDRESS = 1系統目の自側のIPアドレスまたはホスト名[,2系統目の自側のIPアドレスまたはホスト名]
1系統目の自側のIPアドレスまたはホスト名、および、2系統目の自側のIPアドレスまたはホスト名を、それぞれ255バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
IPv6アドレスを使用する場合は、グローバルアドレスのみ使用可能です。
2系統のLANを使用することを推奨します。
2系統目のLANの情報を設定する場合は、OTHER_NODE_ADDRESSも2系統の情報を設定してください。
業務用のLANを使用し、かつ回線が1系統の場合に、“-”と指定することも可能です。
注意
2系統のIPアドレスを定義する場合は、1系統目と2系統目のIPアドレスは異なるセグメントにしてください。なお、セグメントは、IPアドレスとネットワークマスクをAND演算することで求めることができます。
1系統目
IPアドレス:10.128.20.1、ネットワークマスク:255.255.255.0の場合、セグメントは10.128.20.0となります。
2系統目
IPアドレス:10.128.30.1、ネットワークマスク:255.255.255.0の場合、セグメントは10.128.30.0となります。
相手側のRDBシステム名を設定します。なお、RDBシステム名を付けない運用の場合は、ハイフン (“-”)を設定してください。
記述形式は、以下のとおりです。
OTHER_RDBSYSTEM_NAME = 相手側のRDBシステム名
相手側のRDBシステム名を、8バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
参照
RDBシステム名の詳細は“セットアップガイド”を参照してください。
モニタデーモンがノード間通信を行うための相手側のIPアドレスまたはホスト名を指定します。
ホスト名を指定する場合は、“H.1 hostsファイルの編集”を参照してください。
なお、モニタデーモンのノード間通信は、DBミラーリングサービスの運用を確実にするため、管理用のLANおよびデータ転送用のLANを設定します。
記述形式は、以下のとおりです。
OTHER_NODE_ADDRESS = 1系統目の相手側のIPアドレスまたはホスト名[,2系統目の相手側のIPアドレスまたはホスト名]
1系統目の相手側のIPアドレスまたはホスト名、および、2系統目の相手側のIPアドレスまたはホスト名を、それぞれ255バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
IPv6アドレスを使用する場合は、グローバルアドレスのみ使用可能です。
2系統のLANを使用することを推奨します。
2系統目のLANの情報を設定する場合は、OWN_NODE_ADDRESSも2系統の情報を設定してください。
注意
2系統のIPアドレスを定義する場合は、1系統目と2系統目のIPアドレスは異なるセグメントにしてください。なお、セグメントは、IPアドレスとネットワークマスクをAND演算することで求めることができます。
1系統目
IPアドレス:10.128.20.2、ネットワークマスク:255.255.255.0の場合、セグメントは10.128.20.0となります。
2系統目
IPアドレス:10.128.30.2、ネットワークマスク:255.255.255.0の場合、セグメントは10.128.30.0となります。
モニタデーモンがノード間通信を行うための相手側のポート番号を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
OTHER_PORTNO = 相手側のポート番号
ポート番号は、1024~65535(推奨値:1024~32767)の範囲で、未使用の値を指定します。
本パラメタは省略できません。
モニタ管理ファイルの配置先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
DX_MANAGE_PATH = モニタ管理ファイルを配置する格納先ディレクトリの絶対パス名
モニタ管理ファイルを配置する格納先ディレクトリの絶対パス名を、256バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
注意
DX_MANAGE_PATHパラメタで指定したディレクトリには、データベース二重化で利用するための専用のディレクトリを用意してください。同ディレクトリ配下には、他のファイルなど資源を格納しないようにしてください。
参照
モニタ管理ファイルの構成については、“付録E データベース二重化の資源のファイル名”を参照してください。
モニタデーモンのコアファイル出力先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
DX_CORE_PATH = コアファイル出力先ディレクトリの絶対パス名
モニタデーモンのコアファイル出力先ディレクトリの絶対パス名を、256バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
アプリケーションからのデータベース更新に対するRERUNログ転送結果の受信タイムアウト時間を指定します。
副系ノードからの返信がない場合、指定タイムアウト時間を待ち合わせるため、アプリケーションのデータベース更新レスポンス時間に影響があります。
記述形式は、以下のとおりです。
TRANS_TIMEOUT = 受信タイムアウト時間(秒)
5~3600秒の範囲で指定します。この時間までに応答がない場合、アプリケーションの更新処理は成功しますが、RERUNログの転送は失敗となり正系ノードにログを蓄積します。
なお、蓄積したログは、ネットワーク復旧後に自動的に副系ノードに転送されます。
本パラメタは省略可能です。省略時は30が指定されたものとみなします。
注意
ログデータ転送休止状態になった場合は、TRANS_TIMEOUTの指定に関わらずdxaccumコマンドを実行するまでの間、アプリケーションの更新は待ち状態になります。
相手モニタデーモンとの通信においてネットワーク異常を検知、および、POLL_WAITOUT指定でのタイムアウトを検知した場合に、相手ノードへの再接続を試みる回数、再接続タイムアウト時間、および、リトライ間隔を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
CONNECT_RETRY = リトライ回数 [,再接続タイムアウト時間(秒),リトライ間隔(秒)]
指定範囲でネットワークの再接続ができなかった場合は、ネットワーク切断と判断します。
本パラメタは省略可能です。省略時は「リトライ回数=5」、「再接続タイムアウト時間=1」および「リトライ間隔=1」が指定されたものとみなします。
5~60回の範囲で指定します。
1~60秒の範囲で指定します。
1~60秒の範囲で指定します。
モニタデーモンが正本のデータベースを監視するために、ハートビートを行う間隔を指定します。また、LANの通信状況の監視間隔としても使用します。
記述形式は、以下のとおりです。
POLL_TIME = 送受信間隔時間(ミリ秒)
送受信間隔時間は500から10000の間の値を指定します。
本パラメタは省略可能です。省略時は1000が指定されたものとみなします。
モニタデーモンが、POLL_TIMEパラメタで指定した送受信間隔を元に、ハートビートの異常を検知するまでの時間(確認データを受信してから、次の確認データが到着するまでのタイムアウト時間)を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
POLL_WAITOUT = タイムアウト時間(秒)
3~3600秒の範囲で指定します。この時間までに応答がない場合、無応答として検知します。
本パラメタは省略可能です。省略時は5が指定されたものとみなします。
タイムアウト検出後の動作は、CONNECT_RETRYの指定に従います。
DBミラーリング動作環境ファイルの記述例を、以下に示します。
![]() Solarisの場合
Solarisの場合
RLP_TYPE = TCP OWN_NODE_ADDRESS = 10.128.25.128, 10.128.25.129 OTHER_RDBSYSTEM_NAME = rdbsys3 OTHER_NODE_ADDRESS = 10.128.25.130, 10.128.25.131 OTHER_PORTNO = 26800 DX_MANAGE_PATH = /work/duplex/def DX_CORE_PATH = /work/duplex/core_dir TRANS_TIMEOUT = 30 CONNECT_RETRY = 5,1,1 POLL_TIME = 1000 POLL_WAITOUT = 10
![]() Linuxの場合
Linuxの場合
RLP_TYPE = TCP OWN_NODE_ADDRESS = 10.128.20.1, 10.128.30.1 OTHER_RDBSYSTEM_NAME = rdbsys3 OTHER_NODE_ADDRESS = 10.128.20.2, 10.128.30.2 OTHER_PORTNO = 26800 DX_MANAGE_PATH = /work/duplex/def DX_CORE_PATH = /work/duplex/core_dir TRANS_TIMEOUT = 30 CONNECT_RETRY = 5,1,1 POLL_TIME = 1000 POLL_WAITOUT = 10
Symfoware/RDBの動作環境ファイルであるRDB構成パラメタファイルに、データベース二重化の動作環境を指定します。
本作業は、両ノードで実施します。
RDB構成パラメタファイルに記述する定義種別と定義内容を以下に示します。
定義種別 | 定義内容 |
|---|---|
BC構成パラメタファイルの絶対パス名 |
BC構成パラメタファイルを指定します。データベース二重化は、本パラメタに指定されたBC構成パラメタファイルから、運用に必要な動作環境の定義を読み込みます。
記述形式は、以下のとおりです。
RDBBC = BC構成パラメタファイルの絶対パス名
BC構成パラメタファイルの絶対パス名を、1行に1023バイト以内で指定します。
注意
本パラメタを省略した場合は、DBミラーリングシステムを運用しないものとみなします。
参照
RDB構成パラメタファイルの編集方法は、“セットアップガイド”を参照してください。
コントローラの動作環境は、BC構成パラメタファイルで定義します。
BC構成パラメタファイルは、UNIX系ファイルで作成します。
BC構成パラメタファイルは、両ノードで設定します。性能チューニングに関するパラメタ(RLC_BUFFパラメタ)は、両ノードで一致させてください。
BC構成パラメタファイルは、/opt/FJSVsymdx/demo/bccfg.envを複写し、作成したテキストファイルに定義します。このファイルの絶対パス名を、RDB構成パラメタファイルのRDBBCパラメタで指定してください。なお、BC構成パラメタファイルは、任意のディレクトリに任意のファイル名で作成することができます。ただし、/tmpのような一時領域には作成しないでください。
BC構成パラメタファイルに記述する定義種別と定義内容を以下に示します。
定義種別 | 定義内容 | 記述の省略 | |
|---|---|---|---|
複写元RLP | 複写先RLP | ||
RLP動作環境ファイルの格納先ディレクトリの絶対パス名 | 不可 | 不可 | |
RERUNログバッファ枚数 | 可 | - | |
BC管理DBの定義情報 | 不可 | 不可 | |
BCログ管理ファイルのローデバイス名またはファイルの絶対パス名 | 不可 | 不可 | |
-:指定不要
ポイント
パラメタ変更を行う場合、利用者業務やDBミラーリングサービスがすべて停止していることを確認してからBC構成パラメタファイルを編集し、Symfoware/RDBの再起動およびDBミラーリングサービスを再開してください。
パラメタファイルの記述形式
パラメタファイルの記述形式について説明します。なお、本形式は以下の各パラメタファイルで共通です。
BC構成パラメタファイル
RLP動作環境ファイル
RLP定義ファイル
記述形式は以下のとおりです。なお、行の先頭が番号記号“#”の場合、その行はコメント行として扱われます。また、行の途中に番号記号“#”が出現した場合、その番号記号“#”以降行末までがコメントとして扱われます。
定義指示文<改行>
:各行の定義指示文の記述形式は、次のとおりです。
定義種別 = [指定値1][,指定値2]・・・
注意
定義指示文は複数行にまたがって記述することはできません。
等号“=”前後に空白、タブを指定することができます。
コンマ“,”前後に空白、タブを指定することができます。
指定値がパス名の場合は、パス名中に空白、タブ、コンマ“,”、セミコロン“;”および番号記号“#”の指定はできません。
大文字と小文字は、区別して扱われます。
各パラメタの説明
RLPの動作環境を定義したRLP動作環境ファイルを指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLP_FILE_PATH = RLP動作環境ファイルの格納先ディレクトリの絶対パス名
RLP動作環境ファイルの格納先ディレクトリの絶対パス名を、256バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
RERUNログバッファ枚数を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLC_BUFF = RERUNログバッファ枚数
RERUNログバッファ枚数を、32~260000の範囲で指定します。
複写元RLPの場合、本パラメタは省略可能です。複写先RLPの場合、本パラメタは不要です。
省略時は128が指定されたものとみなします。
参照
本パラメタに指定する値の見積り方法は、“A.3.5.2 RERUNログバッファ枚数の見積り”を参照してください。
BC管理スキーマの定義で使用するデータベース名を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
BCMNDB = RDBシステム名_データベース名
BC管理スキーマの定義で使用するデータベース名を、英数字5文字以上36文字以内で指定します。
データベース名は、RDBシステム内で一意にしてください。
デフォルトのRDBシステムにBC管理DBを作成する場合は、“RDBII_データベース名”の形式としてください。
本パラメタは省略できません。
BCログ管理ファイルの配置先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
BCLOGMANAGE = {BCログ管理ファイルを配置するローデバイスの絶対パス名 |
BCログ管理ファイルの絶対パス名}BCログ管理ファイルを配置するローデバイスの絶対パス名またはBCログ管理ファイルの絶対パス名を、1023バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
BC構成パラメタファイルの記述例を、以下に示します。
ここでは、BCログ管理ファイルを、ローデバイスに配置しています。
![]() Solarisの場合
Solarisの場合
RLP_FILE_PATH = /opt/FJSVsymdx/etc RLC_BUFF = 1024 BCMNDB = rdbsys1_ManageDB BCLOGMANAGE = /dev/rdsk/c3t1d1s3
![]() Linuxの場合
Linuxの場合
RLP_FILE_PATH = /opt/FJSVsymdx/etc RLC_BUFF = 1024 BCMNDB = rdbsys1_ManageDB BCLOGMANAGE = /dev_symfomc/raw6
RLP動作環境ファイルは、主系RLPと従系RLPのそれぞれで設定します。
RLP動作環境ファイルは、UNIX系ファイルで作成します。
主系と従系の各RLPでは、複写元RLPと複写先RLPのそれぞれでRLP動作環境ファイルを作成します。
RLP動作環境ファイルは、/opt/FJSVsymdx/demo/rlp001.envを複写し、作成したテキストファイルに定義します。このファイル名を“RLP名.env”に変更し、BC構成パラメタファイルのRLP_FILE_PATHパラメタで指定してください。なお、RLP動作環境ファイルは、任意のディレクトリに作成することができます。ただし、/tmpのような一時領域には作成しないでください。
ポイント
RLP動作環境ファイルは、RLP種別が複写元RLPであるか、複写先RLPであるかによって有効なパラメタが異なります。
なお、RLPが主系であるか従系であるかによって、有効なパラメタが異なることはありません。
このため、主系RLPの複写元RLP環境と複写先RLP環境で作成したRLP動作環境ファイルを従系RLPに複写し、ファイル名およびディレクトリ名を含むパラメタのみを編集します。
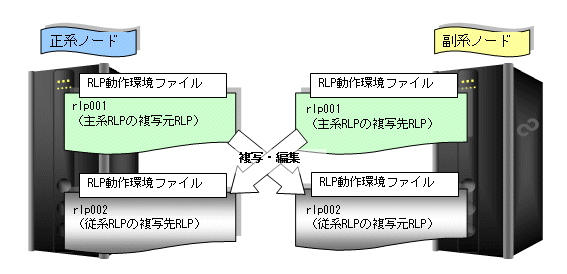
参照
RLP動作環境ファイルの記述形式は、“パラメタファイルの記述形式”を参照してください。
セキュリティ運用時にのみ有効なパラメタについては、“5.3.9.1 RLP動作環境ファイルのセキュリティパラメタ”を参照してください。
RLP動作環境ファイルに記述する定義種別と定義内容を以下に示します。
定義種別 | 定義内容 | 記述の省略 | |
|---|---|---|---|
複写元RLP | 複写先RLP | ||
正系ノードで空きRLCファイルの減少の警告契機 | 可 | - | |
RERUNログ抽出ファイルの作成先のディレクトリの絶対パス名 | - | 不可 | |
RERUNログ引継ぎファイルの配置先のローデバイス名またはディレクトリの絶対パス名 | - | 不可 | |
RERUNログ抽出作業域の獲得先ディレクトリの絶対パス名 | - | 可 | |
RERUNログ抽出作業域の作業域ファイルとして獲得するファイルサイズの割り当て量 (注1) | - | 可 | |
RERUNログ抽出作業域の作業域メモリとして獲得するメモリの大きさ (注1) | - | 可 | |
RERUNログ反映のコミット順序の保証単位、反映常駐スレッド数 (注1)、トランザクション結合数 (注1) | - | 可 | |
自動ログ破棄の有無 | - | 可 | |
EXT_FILE_CLEAR (注2) | RERUNログ抽出ファイルの削除時にRERUNログ抽出ファイルの初期化を行うか否か | - | 可 |
EXT_WORK_CLEAR (注2) | RERUNログ抽出作業域の作業域ファイルの削除時に作業域ファイルの初期化を行うか否か | - | 可 |
-:指定不要
注1) 主系RLPと従系RLPで同一値にしてください。
注2) セキュリティ運用時にのみ有効です。
注意
複写元RLPのRLP動作環境ファイルに設定する定義種別が無くても、ファイルは作成してください。
各パラメタの説明
正系ノードの空きRLCファイルの減少を通知する警告メッセージの出力契機を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLC_NOEMP_WARN = 正系ノードの空きRLCファイル個数
正系ノードの空きRLCファイルの減少を通知する警告メッセージの出力契機を、空きRLCファイルの個数(1~63の範囲)で指定します。
複写元RLPの場合、本パラメタは省略可能です。複写先RLPの場合、本パラメタは不要です。
省略時は、警告メッセージは出力されません。
ポイント
正系ノードの空きRLCファイル個数が本パラメタに指定した値以下になると、RLCファイルの交替時に警告メッセージが出力されます。
RERUNログ抽出ファイルの作成先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
EXT_FILE_PATH = 絶対パス名
RERUNログ抽出ファイルの作成先ディレクトリの絶対パス名を、511バイト以内で指定します。
複写元RLPの場合、本パラメタは不要です。複写先RLPの場合、本パラメタは省略できません。
RERUNログ引継ぎファイルの作成先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
CONT_FILE_PATH = 絶対パス名
RERUNログ引継ぎファイルの配置先のローデバイスまたはディレクトリの絶対パス名を、511バイト以内で指定します。
複写元RLPの場合、本パラメタは不要です。複写先RLPの場合、本パラメタは省略できません。
RERUNログを抽出するときに使用する、RERUNログ抽出作業域の獲得先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
EXT_WORK_PATH = 絶対パス名
RERUNログ抽出作業域の獲得先ディレクトリの絶対パス名を、220バイト以内で指定します。
複写元RLPの場合、本パラメタは不要です。複写先RLPの場合、本パラメタは省略可能です。
省略時は、絶対パス名として/tmpが指定されたものとみなします。
RERUNログを抽出するときに使用するRERUNログ抽出作業域として、作業域ファイルを作成または拡張する場合の1回の割当て量を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
EXT_WORK_SIZE = サイズ
RERUNログ抽出作業域として作業域ファイルを作成または拡張する場合の割当て量を1メガバイト~100メガバイトの範囲で、メガバイト単位で指定します。
複写元RLPの場合、本パラメタは不要です。複写先RLPの場合、本パラメタは省略可能です。
省略時は、サイズとして10(メガバイト)が指定されたものとみなします。
参照
本パラメタに指定する値の見積り方法は、“A.3.6.3 RERUNログ抽出作業域の見積り”を参照してください。
RERUNログを抽出するときに使用する、RERUNログ抽出作業域の作業域メモリの大きさを指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
EXT_WORK_MEM = サイズ
RERUNログ抽出作業域の作業域メモリの大きさを1メガバイト~2047メガバイトの範囲で、メガバイト単位で指定します。
複写元RLPの場合、本パラメタは不要です。複写先RLPの場合、本パラメタは省略可能です。
省略時は、サイズとして10(メガバイト)が指定されたものとみなします。
参照
本パラメタに指定する値の見積り方法は、“A.3.6.3 RERUNログ抽出作業域の見積り”を参照してください。
RERUNログ反映に関する以下の動作を指定します。
コミット順序の保証単位
反映常駐スレッド数
トランザクション結合数
記述形式は、以下のとおりです。
REF_APPLY_MODE = {DSI[,[反映常駐スレッド数][,[トランザクション結合数]]]
| LOGGROUP,反映常駐スレッド数[,[トランザクション結合数]]}RERUNログ反映でのコミット順序の保証単位として、正本のデータベースにおけるトランザクションのDSI単位、またはロググループ単位のどちらかを指定します。
DSI単位で、正本のデータベースにおけるトランザクションのコミット順にRERUNログを反映します。
本パラメタはRERUNログ反映の性能を優先する場合に選択します。
本パラメタを選択した場合には、RERUNログ反映はページ単位で占有します。
ロググループ単位で、正本のデータベースにおけるトランザクションのコミット順にRERUNログを反映します。
本パラメタは、Mirroring Controller利用時の副本のデータベースの参照業務で、RERUNログ反映中に正本のデータベースにおけるトランザクションを保証する必要がある場合に選択します。
本パラメタを選択した場合、RERUNログ反映は行単位で占有します。
RERUNログを反映するときに利用する反映常駐スレッド数を指定します。
反映常駐スレッド数は2~65535の範囲で指定します
本パラメタは省略可能です。
省略時は以下のいずれかの値が設定されたものとみなします。
・RDB構成パラメタファイルにRDBCPUNUMパラメタを指定している場合
RDBCPUNUMに指定したCPUコア数
・RDB構成パラメタファイルにRDBCPUNUMパラメタを指定していない場合
Symfoware/RDB起動時の稼動中のCPUコア数
ただし、値が1となる場合には2に繰り上げます。
反映常駐スレッド数に1を指定します。
本パラメタは省略できません。
当該RLPに含まれるDSIすべてに対して、デフォルトのトランザクション結合数を1~65535の範囲で指定します。
本パラメタは省略可能です。
省略時は1が指定されたものとみなします。
複写元RLPの場合、REF_APPLY_MODEは指定不要です。
複写先RLPの場合、REF_APPLY_MODEは省略可能です。省略時は以下が指定されたものとみなします。
コミット順序の保証単位にDSI
反映常駐スレッド数に上記の反映常駐スレッド数の省略時の値
トランザクション結合数に1
注意
コミット順序の保証単位にDSIを指定した場合でも、格納構造がSEQUENTIAL構造でDSO定義にPRECEDENCE(1)を指定しているDSIへのRERUNログ反映は、行単位の占有となります。
参照
本機能の利用方法については、“B.3.6 RERUNログ反映時のコミット順序の保証単位”を参照してください。
反映常駐スレッド数に指定する値の見積り方法は、“12.2.3 反映常駐スレッドの多重度数のチューニング”を参照してください。
トランザクション結合数に指定する値の見積り方法は、“12.2.4 トランザクション結合数のチューニング”を参照してください。
RERUNログ反映処理において、閉塞状態の資源や資源識別子が未登録の資源を検知した場合のRERUNログの破棄の有無を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
REF_LOG_PURGE = {DSI | MAP | ALL | NONE}DSI:RERUNログの反映が不可となったDSIのRERUNログを破棄し、その他のRERUNログの反映処理を行います。
MAP:資源識別子が未登録のRERUNログを破棄し、その他のRERUNログの反映処理を行います。
ALL:RERUNログの反映不可のDSIおよび資源識別子が未登録のRERUNログを破棄し、その他のRERUNログの反映処理を行います。
NONE:RERUNログ反映不可のDSIまたは資源識別子が未登録のRERUNログであっても破棄せず、RERUNログ反映処理を中断します。
複写元RLPの場合、本パラメタは不要です。複写先RLPの場合、本パラメタは省略可能です。
省略時はNONEが指定されたものとみなします。
注意
セットアップでは、本パラメタの指定を省略するか、指定する場合は必ずNONEを指定してください。
本パラメタの変更は、RERUNログ反映処理に異常が発生した場合に行います。
なお、本パラメタにDSI、MAP、ALLを指定した場合、ノード切替え不可状態となります。
参照
RERUNログの破棄の詳細については、“11.8.6.4 ログ破棄を利用したリカバリ”を参照してください。
例
RLP動作環境ファイルの記述例を以下に示します。
ここでは、RERUNログ引継ぎファイルを、ローデバイスに配置しています。
![]() Solarisの場合
Solarisの場合
RLC_NOEMP_WARN = 1 EXT_FILE_PATH = /work/tmp/extfile CONT_FILE_PATH = /dev/rdsk/c3t1d1s4 EXT_WORK_PATH = /tmp/extwork EXT_WORK_SIZE = 100 EXT_WORK_MEM = 200 REF_APPLY_MODE = DSI,15,10 REF_LOG_PURGE = NONE
![]() Linuxの場合
Linuxの場合
RLC_NOEMP_WARN = 1 EXT_FILE_PATH = /work/tmp/extfile CONT_FILE_PATH = /dev_symfomc/raw7 EXT_WORK_PATH = /tmp/extwork EXT_WORK_SIZE = 100 EXT_WORK_MEM = 200 REF_APPLY_MODE = DSI,15,10 REF_LOG_PURGE = NONE
RLP定義ファイルは、主系RLPと従系RLPのそれぞれで設定します。
RLP定義ファイルは、UNIX系ファイルで作成します。
主系と従系の各RLPでは、複写元RLPと複写先RLPのそれぞれでRLP定義ファイルを作成します。
RLP定義ファイルは、/opt/FJSVsymdx/demo/std/dxrlpenv.defを複写し、作成したテキストファイルに定義します。このファイル名を任意に変更し、セットアップスクリプトを実行する際に指定します。なお、RLP定義ファイルは、任意のディレクトリに任意のファイル名で作成することができます。ただし、/tmpのような一時領域には作成しないでください。
注意
RLP定義ファイルは、各ノードのRLPごとに設定する必要があります。
参照
RLP定義ファイルの記述形式は、“パラメタファイルの記述形式”を参照してください。
RLP定義ファイルに記述する定義種別と定義内容を以下に示します。
定義種別 | 定義内容 | 記述の省略 |
|---|---|---|
ロググループ名 | 可 | |
自側送信用RLMの絶対パス名 | 不可 | |
自側受信用RLMの絶対パス名 | 不可 | |
RERUNログの転送方式 | 不可 | |
RLCファイルの数 (注1) | 不可 | |
RLCファイルのサイズ (注1) | 不可 | |
RLC_OWN_DEVICEn (注2) | n個目の自側RLCファイルの絶対パス名 | 不可 |
RLP管理オブジェクトを作成するローデバイス名 | 不可 (注3) | |
RLP管理オブジェクトを作成するファイル名 | 不可 (注4) | |
RLP管理オブジェクトを作成するファイルのサイズ (注1) | 不可 (注5) | |
シェルスクリプトが使用する作業用ディレクトリの絶対パス名 | 不可 | |
削除モード | 可 |
注1) 主系RLP/従系RLPおよび、それぞれの複写元RLP/複写先RLPで一致させてください。
注2) RLC_NUMに設定した値の個数分定義してください。(n:1~RLC_NUMの設定値)
注3) ローデバイスに作成する場合に指定してください。“MNDB_FILE”と同時に指定することはできません。
注4) ファイルに作成する場合に指定してください。“MNDB_RAW_DEVICE”と同時に指定することはできません。
注5) ファイルに作成する場合に指定してください。
各パラメタの説明
RLPが属するロググループ名を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLP_LOGGRP = ロググループ名
本パラメタは省略可能です。
スケーラブルログ運用を行っていて本パラメタを省略した場合、または“system”を指定した場合は、システムロググループが対象になります。
注意
指定するロググループ名については、以下に留意してください。
DCU間で重複しないようにしてください。
主系RLPと従系RLPでは一致させる必要があります。
自側送信用RLMの作成先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLM_OWN_SEND_DEVICE=自側送信用RLMの作成先ファイル名
自側送信用RLMの作成先のファイル名を絶対パス名で指定します。
絶対パス名は、1023バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
自側受信用RLMの作成先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLM_OWN_RECV_DEVICE=自側受信用RLMの作成先ファイル名
自側受信用RLMの作成先のファイル名を絶対パス名で指定します。
絶対パス名は、1023バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
RERUNログの転送方式を指定します。
記述形式は以下のとおりです。
TRANS_MODE = NET
RERUNログを転送するための指定として、NETを指定します。
本パラメタは省略できません。
作成するRLCファイルの数を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLC_NUM = 作成するRLCファイルの数
作成するRLCファイルの数を、3以上64以下の値で指定してください。
本パラメタは省略できません。
注意
主系RLP/従系RLPおよび、それぞれの複写元RLP/複写先RLPで一致させてください。
RLCファイルの大きさを指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLC_SIZE = RLCファイルのサイズ
RLCファイルの大きさを、キロバイト単位またはメガバイト単位で指定します。
10メガバイト以上のサイズを、単位の“K”(キロバイト)または“M”(メガバイト)を付加した形式で指定します。
本パラメタは省略できません。
注意
主系RLP/従系RLPおよび、それぞれの複写元RLP/複写先RLPで一致させてください。
自側RLCファイルの作成先を指定します。
RLC_NUMに設定した値の個数分定義します。
記述形式は、以下のとおりです。
RLC_OWN_DEVICEn=自側RLCファイルの作成先ファイル名n個目の自側RLCファイルの作成先のファイル名を絶対パス名で指定します。(n:1~RLC_NUM)
絶対パス名は、1023バイト以内で指定します。
本パラメタは省略できません。
RLP管理オブジェクトの作成先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
MNDB_RAW_DEVICE = RLP管理オブジェクト作成先ローデバイス名
RLP管理オブジェクトの作成先ローデバイス名を指定します。
ローデバイス名は、255バイト以内で指定します。
本パラメタは、RLP管理オブジェクトの作成先をローデバイスとする場合のみ記述してください。
注意
主系RLPの複写元RLPと複写先RLPで一致させてください。また、従系RLPの複写元RLPと複写先RLPで一致させてください。
RLP管理オブジェクトの作成先を指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
MNDB_FILE = RLP管理オブジェクト作成先ファイル名
RLP管理オブジェクトの作成先のファイル名を絶対パス名で指定します。
絶対パス名は、255バイト以内で指定します。
本パラメタは、RLP管理オブジェクトの作成先をファイルとする場合のみ記述してください。
注意
主系RLPの複写元RLPと複写先RLPで一致させてください。また、従系RLPの複写元RLPと複写先RLPで一致させてください。
RLP管理オブジェクトの全体スペース量または作成サイズを指定します。
記述形式は、以下のとおりです。
MNDB_SIZE = {全体スペース量 | 作成サイズ}RLP管理オブジェクトの全体スペース量または作成サイズを、メガバイト単位またはギガバイト単位で指定します。
全体スペース量または作成サイズに指定できる値は、6メガバイト~999ギガバイトの範囲です。
この値に、単位の“M”(メガバイト)または“G”(ギガバイト)を付加した形式で指定します。
本パラメタは、RLP管理オブジェクトの全体スペース量となります。
RLP管理オブジェクトの作成先をファイルとする場合は省略できません。
注意
主系RLP/従系RLPおよび、それぞれの複写先RLP/複写元RLPで一致させてください。
参照
本パラメタに指定する値の見積り方法は、“A.3.3 RLP管理オブジェクトの見積り”を参照してください。
例
RLP定義ファイルの記述例を、以下に示します。
### Log Group definition ### RLP_LOGGRP=system ### RLM definition ### RLM_OWN_SEND_DEVICE=/home/rdbsys1/rlm1 RLM_OWN_RECV_DEVICE=/home/rdbsys1/rlm2 TRANS_MODE=NET ### RLC definition ### RLC_NUM=3 RLC_SIZE=10M # RLC_OWN definition RLC_OWN_DEVICE1=/home/rdbsys1/rlc1 RLC_OWN_DEVICE2=/home/rdbsys1/rlc2 RLC_OWN_DEVICE3=/home/rdbsys1/rlc3 ### MNDB definition ### MNDB_FILE=/symfo_dx/mndb/mndbspc001 MNDB_SIZE=10M ### OTHER definition ### WORK_DIR=/tmp DX_SECURITY_MODE=NORMAL