ここでは、本製品の導入に必要になる、ストレージ環境の構成と設定値の決定について説明します。
ここでは、ストレージの事前準備について説明します。
物理サーバや仮想マシンを構築する場合、ストレージ装置とストレージネットワークの設定が必要なため、迅速なサーバ提供の妨げになっていました。
本製品では、以下の機能を利用して迅速なサーバ提供を実現します。
仮想L-Serverに対するストレージの割当て
仮想L-Serverに対するストレージの割当て方法には、以下の2つがあります。
仮想ストレージリソース(データストアなど)から自動生成したディスクリソース(仮想ディスク)の割当て
VM管理製品との連携により、事前に作成した仮想ストレージリソース(VMゲスト用のファイルシステムなど)が本製品により自動検出されます。検出された仮想ストレージリソースの中から仮想L-Serverの仕様を満たす仮想ストレージリソースが、本製品により自動選択されます。
自動選択された仮想ストレージリソースから、指定された容量のディスクリソース(仮想ディスクなど)が自動生成され、仮想L-Serverに割り当てられます。
【Xen】
使用できる仮想ストレージは、GDSのシングルディスクです。
事前に作成したディスクリソース(rawデバイスまたはパーティション)の割当て【KVM】
ストレージ装置にLUNを作成します。
LUNは仮想L-Serverのディスクに対応します。必要なディスクの個数分LUNを作成してください。
LUNの大きさはディスクの大きさ以上にしてください。
手順1.で作成したLUNを、rawデバイスとしてVMホストに認識させます。
仮想L-Serverに対応するVMゲストをマイグレーションする場合、LUNが共有ディスクになるように、ゾーニング、アフィニティを設定してください。
パーティションも仮想L-Serverのディスクに対応します。必要なディスクの個数分パーティションを作成してください。パーティションの大きさはディスクの大きさ以上にしてください。
rawデバイスまたはパーティションをrcxadm diskコマンドでディスクリソースとして本製品に登録します。
仮想L-Serverに対応するVMゲストをマイグレーションする場合、複数のVMホストから共有されているrawデバイスまたはパーティションを、共有定義されたディスクリソースとして登録してください。
登録したディスクリソースの中から仮想L-Serverの仕様を満たすディスクリソースが本製品により自動選択され、L-Serverに割り当てられます。
仮想L-Serverを利用する場合に必要な定義ファイル
仮想L-Serverを利用する場合に必要な定義ファイルは、以下のとおりです。
ストレージプールにシン・プロビジョニング属性を設定する場合
「操作ガイド インフラ管理者編 (リソース管理) CE」の「12.2 リソースプールの操作」の「ストレージプールに対するシン・プロビジョニング属性の設定」を参照してください。
シン・プロビジョニングにおけるリソース選択の優先度を利用する場合
「E.1.1 定義ファイル」の「シン・プロビジョニングにおけるリソース選択の優先順の設定」を参照してください。
物理L-Serverに対するストレージの割当て
物理L-Serverに対するストレージの割当て方法には、以下の2つがあります。
仮想ストレージリソース(RAIDグループなど)から自動生成したディスクリソース(LUN)の割当て
ストレージ製品との連携により、事前に作成した仮想ストレージリソースを本製品が自動検出します。
検出された仮想ストレージリソースの中から物理L-Serverの仕様を満たす仮想ストレージリソースを本製品が自動選択します。
自動選択された仮想ストレージリソースから、指定された容量のディスクリソースを作成し、物理L-Serverに割り当てます。
事前に作成されたディスクリソース(LUNなど)の割当て
ストレージ製品との連携により、事前に作成したディスクリソースを本製品が自動検出します。
検出されたディスクリソースの中から物理L-Serverの仕様を満たすディスクリソースを本製品が自動選択してL-Serverに割り当てます。
利用するストレージ装置により、ストレージの割当て方法が異なります。
ストレージの割当て方法とストレージの種類については、「4.3.1.2 ストレージの構成」の「表4.10 物理L-Serverに対するストレージの割当て方法とストレージの種類」を参照してください。
物理L-Serverと接続できるストレージ装置については、「1.5 ハードウェア環境」の「表1.60 物理サーバ上のL-Serverと接続できるストレージ装置」を参照してください。
シン・プロビジョニングを利用したストレージの有効活用
シン・プロビジョニングとは、ストレージ容量を仮想化する技術です。
ストレージの効率的な活用を実現します。
事前に、必要な容量を確保する必要がなく、実際に利用している容量に応じて容量を確保し、必要に応じて拡張できる機能です。
シン・プロビジョニングの実現には、以下の方法があります。
ストレージ装置のシン・プロビジョニングを利用する方法
本製品では、ETERNUSストレージのシン・プロビジョニングと連携できます。
サーバ仮想化ソフトウェアのシン・プロビジョニングを利用する方法
本製品では、VMware vStorage Thin Provisioningと連携できます。
シン・プロビジョニングとの連携については、「4.3.1.2 ストレージの構成」を参照してください。
ストレージ自動階層制御を利用したストレージの有効活用
ストレージ自動階層制御は、ストレージへのデータアクセスを監視し、異種ドライブ混在環境で、データのアクセス頻度を検出し、設定したポリシーに応じて、ドライブ間で自動的にデータ再配置を行う機能です。
本製品では、ETERNUSストレージのストレージ自動階層制御と連携できます。ストレージ自動階層制御との連携については、「4.3.1.2 ストレージの構成」を参照してください。
物理L-Serverを作成する場合の前提条件
物理L-Serverを作成する場合の前提条件については、「4.3.1.2 ストレージの構成」の「物理L-Serverを作成する場合の前提条件」を参照してください。
物理サーバをL-Serverにする場合のストレージ構成について
物理サーバをL-Serverにする場合のストレージ構成については、「4.3.1.2 ストレージの構成」の「物理L-Serverを作成する場合のストレージ構成について」を参照してください。
ストレージリソースには、以下の2つがあります。
ストレージリソースの種類によってリソースの登録方法が異なります。
仮想ストレージリソース
本製品にストレージ管理製品を登録すると、ストレージ管理製品が制御するストレージ情報が自動的に取得され、仮想ストレージリソースとして検出されます。そのため、仮想ストレージリソースを個別にリソース登録する必要はありません。
ディスクリソース
LUNなどの事前に作成したディスクリソースは、ストレージ管理製品を登録するとストレージ情報が自動的に取得され、ディスクリソースとして検出されます。そのため、ディスクリソースを個別にリソース登録する必要はありません。
ストレージ管理製品で事前に作成したディスクを、ディスクリソースとして共通の操作で管理できます。
検出された仮想ストレージリソースとディスクリソースは、ストレージプールへの登録が必要です。
ストレージプールへの登録については、「操作ガイド インフラ管理者編 (リソース管理) CE」の「7.5 ストレージリソース」を参照してください。
ストレージリソースの自動検出
ストレージ管理製品やVM管理製品を操作してストレージの追加や変更を行った場合も、ストレージ管理製品やVM管理製品に対して定期的に問合せが行われ、ストレージの構成や状態の変化が検出されます。定期更新する間隔は、ストレージリソースの数によって変化します。
なお、RORコンソールのオーケストレーションツリーでストレージリソースを右クリックし、表示されたメニューで[更新]を選択すると、定期的な問合せを待たずに、ストレージ管理製品やVM管理製品からストレージの構成や状態をすぐに取得できます。
そのあと、ストレージプールへの登録を行ってください。
物理L-Serverを利用する場合に必要な定義ファイル
物理L-Serverを利用する場合に必要な定義ファイルは、以下のとおりです。
以下のストレージを利用する場合
ETERNUSストレージ
EMC CLARiXストレージ
EMC Symmetrix DMXストレージ
EMC Symmetrix VMAXストレージ
「6.1.1 SANストレージのポート組合せ定義ファイルの作成」を参照してください。
ストレージ管理製品としてESCを利用する場合
「D.5.1 定義ファイル」の「ESCで管理されている仮想ストレージリソース名、ディスクリソース名の形式の選択」を参照してください。
ストレージ管理製品としてEMC Navisphere ManagerまたはEMC Solutions Enablerを利用する場合
「D.5.1 定義ファイル」の「EMCストレージ用定義ファイル」を参照してください。
ストレージプールにシン・プロビジョニング属性を設定する場合
「操作ガイド インフラ管理者編 (リソース管理) CE」の「12.2 リソースプールの操作」の「ストレージプールに対するシン・プロビジョニング属性の設定」を参照してください。
シン・プロビジョニングおよびストレージ自動階層制御におけるリソース選択の優先度を利用する場合
「D.5.1 定義ファイル」の「シン・プロビジョニングおよびストレージ自動階層制御におけるリソース選択の優先順の設定」を参照してください。
ダイナミックLUNミラーリングを利用する場合
「D.5.1 定義ファイル」の「ダイナミックLUNミラーリングにおけるミラーリング定義ファイルの作成」を参照してください。
ここでは、本製品の導入に必要な、ストレージ環境の構成と設定値の決定について説明します。
ストレージの割当て方法とストレージの種類
利用するストレージ装置により、ストレージの割当て方法が異なります。
物理L-Serverに対するストレージの割当て方法とストレージの種類は、以下のとおりです。
割当て方法 | ストレージの種類 |
|---|---|
仮想ストレージリソースから自動生成したディスクリソースの割当て |
|
事前に作成されたディスクリソースの割当て |
|
ストレージの構成
システムに必要なストレージの構成を決定します。
本製品がサポートするストレージ構成は以下のとおりです。
サーバ(VMホスト)種別 | L-Serverのシステムディスク | L-Serverのデータディスク |
|---|---|---|
物理 | SANストレージ | SANストレージ |
iSCSIストレージ (*1、2) | iSCSIストレージ (*1、*3) | |
VMware | ESX/ESXiのデータストアとして構成されたストレージ(VMFSのVersion 3以降またはNFSマウント) | |
Hyper-V | MSFCのCluster Shared Volume(CSV)として構成されたストレージ | |
*1: ETERNUSストレージとNetAppストレージの場合、利用できます。
*2: 物理L-ServerがLinuxで、システムディスクがiSCSIストレージの場合、クローニングイメージを利用したL-Serverの作成はできません。
*3: L-Server作成時にiSCSIストレージはデータディスクとして割り当てられません。L-Serverが起動したあと、手動で割り当ててください。L-Serverに対するiSCSIストレージの増設や削減は本製品ではできないため、手動で行ってください。iSCSIストレージのデータディスクの割当てについては、「参考 iSCSIブートの物理L-Serverのデータディスク」を参照してください。
参考
iSCSIブートの物理L-Serverのデータディスク
ETERNUSストレージの場合
ストレージ管理製品を利用して、同じAffinityグループにiSCSIブートディスクのLUNとデータディスクのLUNを定義すると、管理対象サーバからデータディスクを利用できます。
NetAppストレージの場合
ストレージ管理製品を利用して、同じigroupにiSCSIブートディスクのLUNとデータディスクのLUNを定義すると、管理対象サーバからデータディスクを利用できます。
シン・プロビジョニングとの連携
本製品では、ストレージ装置やサーバ仮想化ソフトウェアのシン・プロビジョニングと連携できます。
ETERNUSストレージのシン・プロビジョニングとの連携
ETERNUSストレージでは、1つ以上のRAIDグループから構成される仮想的なリソースプールをThin Provisioning Pool(以降、TPP)と呼びます。
また、サーバに物理ディスク容量以上のボリュームを見せる仮想ボリュームをThin Provisioning ボリューム(以降、TPV)と呼びます。
TPPからTPVに対して容量が割り当てられます。
本製品では、TPPを仮想ストレージリソースとして管理できます。
TPPの仮想ストレージリソースを、シン・プロビジョニングの属性が設定された仮想ストレージリソースと呼びます。
RAIDグループの仮想ストレージリソースを、シック・プロビジョニングの属性が設定された仮想ストレージリソースと呼びます。
本製品では、ESCを利用してTPVを事前に作成し、TPVをディスクリソースとして管理できます。
TPVのディスクリソースをシン・プロビジョニングの属性が設定されたディスクと呼びます。
LUNのディスクリソースをシック・プロビジョニングの属性が設定されたディスクと呼びます。
VMware vStorage Thin Provisioningとの連携
VMwareでは、シン・プロビジョニングで構成された仮想ディスクを、シンフォーマットの仮想ディスクと呼びます。
本製品では、シンフォーマットの仮想ディスクをディスクリソースとして管理できます。
シンフォーマットの仮想ディスクをシン・プロビジョニングの属性が設定されたディスクと呼びます。
シックフォーマットのディスクリソースをシック・プロビジョニングの属性が設定されたディスクと呼びます。
ストレージリソースの管理
本製品では、ストレージリソース(仮想ストレージリソースとディスクリソース)をストレージプールで管理できます。ストレージプールは、シン・プロビジョニングの属性の有無を考慮する必要があります。
シン・プロビジョニングの属性が設定されたストレージプールには、以下のリソースを登録できます。
シン・プロビジョニングの属性が設定された仮想ストレージリソース
シン・プロビジョニングの属性が設定されたディスクリソース
シン・プロビジョニングの属性が設定されていないストレージプールには、以下のリソースを登録できます。
シック・プロビジョニングの属性が設定された仮想ストレージリソース
シック・プロビジョニングの属性が設定されたディスクリソース
【VMware】
VMwareのデータストアには、シン・プロビジョニングを設定できません。このため、本製品では以下のように設定します。
シン・プロビジョニングの属性が設定されたストレージプールに登録された仮想ストレージリソースからディスクリソースを切り出す場合、シンフォーマットを設定してディスクリソースとしてL-Serverに割り当てます。
シン・プロビジョニングの属性が設定されていないストレージプールに登録された仮想ストレージリソースからディスクリソースを切り出す場合、シックフォーマットを設定してディスクリソースとしてL-Serverに割り当てます。
ストレージプールに対するシン・プロビジョニング属性の設定方法については、「操作ガイド インフラ管理者編 (リソース管理) CE」の「12.2 リソースプールの操作」の「ストレージプールに対するシン・プロビジョニング属性の設定」を参照してください。
注意
【VMware】
クローニングイメージを指定した仮想L-Server作成時、ストレージプールのプロビジョニング属性よりもクローニングイメージのプロビジョニング属性が優先されます。
ストレージ自動階層制御との連携
本製品では、ストレージ装置のストレージ自動階層制御と連携できます。
ETERNUSストレージのストレージ自動階層制御との連携
ETERNUSストレージでは、自動階層制御機能によって作成された物理ディスクのプールをFlexible Tier Pool(以降、FTRP)と呼びます。また、自動階層制御機能によって作成された仮想ボリュームをFlexible Tier Volume(以降、FTV)と呼びます。FTRPからFTVが割り当てられます。
本製品では、FTRPを仮想ストレージリソースとして管理できます。FTRPの仮想ストレージリソースは、TPPと同様にシン・プロビジョニングの属性が設定された仮想ストレージリソースと呼びます。
本製品では、ESCを利用してFTVを事前に作成し、FTVをディスクリソースとして管理できます。FTVのディスクリソースは、TPVと同様にシン・プロビジョニングの属性が設定されたディスクと呼びます。
FTRP、FTVの管理
本製品では、FTRP、FTVはストレージリソースとしてストレージプールで管理できます。
FTRP、FTVは、それぞれシン・プロビジョニングのTPP、TPVと同じ扱いです。詳細は、「シン・プロビジョニングとの連携」を参照してください。
注意
FTRP、FTVを登録するストレージプールと、TPP、TPVを登録するストレージプールは同一にせず、異なるストレージプールとして運用することをお勧めします。
同一のストレージプールで運用した場合、ディスク割当て時の空き容量によって選択される仮想ストレージが変わってしまうため、それぞれの特性を活かしたストレージ運用ができなくなります。
物理L-Serverを作成する場合のストレージ構成について
物理L-Serverを作成する場合のストレージ構成は、以下のとおりです。
1台のL-Serverに接続できるストレージ装置は、ファイバーチャネル接続の場合は複数台(VIOMを利用した接続がサポートされていない場合は1台)、iSCSI接続の場合は1台です。
複数のL-Serverによるストレージの共有をサポートします。
注意
ローカルディスクはサポートしていません。ローカルディスクを接続しないでください。
必須になるVM管理製品、ストレージ管理製品などについては、「1.4.2.2 必須ソフトウェア」を参照してください。
サポートするストレージ装置やファイバーチャネルスイッチについては、「1.5 ハードウェア環境」を参照してください。
物理L-Serverを作成する場合の前提条件
L-ServerはSANブート構成とiSCSIブート構成をサポートします。
物理サーバをL-Serverにするには、VIOMまたはHBA address renameを利用した接続がサポートされている必要があります。VIOMまたはHBA address renameを利用した接続については、「4.3.1 ストレージ環境の決定」と「4.3.2 ストレージ環境の設定」を参照してください。
VIOMとHBA address renameの利用は、物理L-Serverを構築する管理対象サーバのハードウェアによって異なります。
ブレードサーバ
VIOMを利用します。
ラックマウント型サーバ
HBA address renameを利用します。
L-ServerのSANストレージとiSCSIストレージへのパスは、マルチパス(2パス)をサポートしています。
管理対象サーバのHBAのポートが合計2ポート以下の構成をサポートしています。
ブレードサーバでファイバーチャネルカードの情報が取得できないMMBファームの場合、ファイバーチャネルカードは拡張スロット2に搭載する構成だけサポートします。なお、ファイバーチャネルカードの情報が取得できるのは以下のとおりです。
PRIMERGY BX900シリーズ
4.70以降
PRIMERGY BX400シリーズ
6.22以降
ブレードサーバの場合、VIOMのセットアップ時に、以下の項目を設定しないでください。
WWN Address Range
MAC Address Range
HBAとストレージ装置の設定値
サーバでは物理サーバとHBAのWWN、ストレージではHBAのWWNとストレージのボリュームとの関係を定義し、システムを設計します。
SANストレージ環境の設定
利用するL-Serverが物理L-Serverか仮想L-Serverかによって、SANストレージ環境の事前設定が異なります。
物理サーバをL-Serverとして利用する場合、「付録D 物理L-Server作成のための設計と設定」を参照してください。
サーバ仮想化ソフトウェアを利用する場合、「付録E 仮想L-Server作成のための設計と設定」のうち、利用するサーバ仮想化ソフトウェアを参照してください。
iSCSIストレージ環境の設定
物理L-Serverで、iSCSIブートを利用する場合、L-Serverに接続できるLUNを事前に作成してください。
詳細は、「D.3.1 ETERNUSストレージを利用する場合」と「D.3.2 NetApp FASストレージを利用する場合」を参照してください。
ダイナミックLUNミラーリングの設定
物理L-Serverで、ダイナミックLUNミラーリングを利用する場合は、ETERNUSストレージで筐体間コピーが利用できるように設定してください。
設定方法は、「ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書 Copy Control Module編」を参照してください。
サーバ側では物理サーバとHBAのWWN、ストレージ側ではHBAのWWNとストレージのボリュームとの関係を定義し、システムを設計します。
以下にHBAの2ポートを使いマルチパスでストレージに接続するときの例を示します。
詳細は、各ストレージ製品のマニュアルを参照してください。
注意
管理対象サーバにHBAのポートが合計3ポート以上搭載されている構成は、サポートしていません。
図4.21 WWNのシステム設計
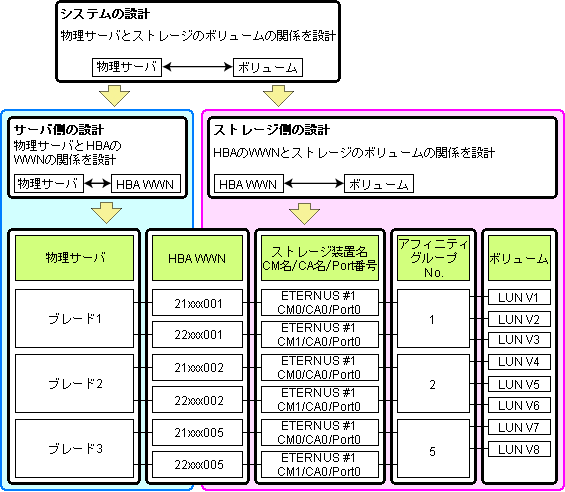
使用するWWNの決定
HBA address renameまたはVIOM利用時には、使用するWWNを決定します。
HBA address renameまたはVIOMで使用するWWNを決定し、サーバ側にはOS(業務)と物理サーバを関連付け、ストレージ側にはボリュームを関連付けます。
HBA address renameまたはVIOMを利用することで、サーバに搭載されたHBAのWWNを意識しなくても、仮想化されたWWNを利用してサーバとストレージの設計が行えます。物理サーバが存在しないなどの、サーバに搭載されたHBAのWWNが把握できない場合でも、サーバとストレージを設計できます。
HBA address renameを利用する場合、WWNは"I/O仮想化オプション"で提供された値を使用します。
VIOMを利用する場合、WWNは以下のどれかの値を使用します。
"I/O仮想化オプション"で提供された値
VIOMインストール時に選択するアドレス範囲から自動的に選択される値
WWNの衝突によるデータの破損を防ぐため、"I/O仮想化オプション"で提供された値を使用することをお勧めします。
参考
"I/O仮想化オプション"は、全世界で一意のWWNを提供します。これにより予期しないWWNの衝突を防ぐことができます。
注意
HBA address renameとVIOMで同じWWNを使用しないでください。同じWWNを使用した場合、データが破損する危険性があります。
HBA address renameまたはVIOMで使用するWWNの形式を、以下に示します。
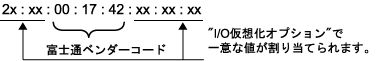
提供されたWWNの先頭"2x"を以下のようにWWNNとWWPNに割り当てて利用します。
20: WWNNとして利用
2x: WWPNとして利用
HBA address renameでは、xはHBAのI/Oアドレスの降順に割り当てられます。
なお、HBAのI/Oアドレスは、HBAのBIOS上またはHBAベンダーが提供しているツールで確認してください。
注意
HBA address renameでは、HBAのI/Oアドレスの降順にWWNを割り当てるため、HBAに記載されているポート番号順と一致しない場合があります。
詳細は、「C.2 HBA address rename設定時のWWNの割当て順序」を参照してください。
決定したWWNは、サーバ側の設計とストレージ側の設計で使用します。
サーバ側の設計
サーバごとに利用するWWNを割り当て、サーバ側の設計で使用します。
ストレージ側の設計
サーバごとに接続するボリュームを決定し、サーバに割り当てたWWNと同じWWNを、ストレージ側の設計で使用します。
使用するWWNの決定(VIOM利用時)
VIOMを利用する場合、VIOMの設定を先に行います。それによって決定したWWNと同じ値をストレージ側にも設定します。
サーバ側では物理サーバとiSCSIアダプターのIQN、ストレージ側ではiSCSIアダプターのIQNとストレージのボリュームとの関係を定義し、システムを設計します。
以下にiSCSIインターフェースの2ポートを使い、マルチパスでストレージに接続するときの例を示します。
詳細は、各ストレージ製品のマニュアルを参照してください。
図4.22 IQNのシステム設計
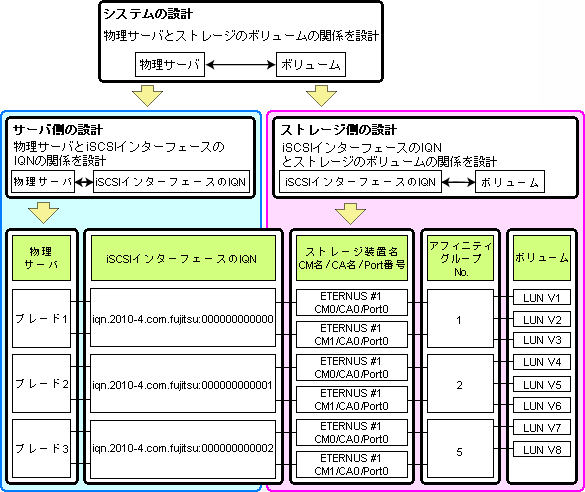
使用するIQNの決定
iSCSIを利用するには、使用するIQNを決定します。
iSCSIで使用するIQNを決定し、サーバ側にはOS(業務)と物理サーバを関連付け、ストレージ側にはボリュームを関連付けます。
IQNは以下で構成されます。
タイプ識別子"iqn."
ドメイン取得日
ドメイン名
ドメイン取得者が付けた文字列
IQNは、一意である必要があります。
サーバ名や、"I/O仮想化オプション"で提供された該当するサーバのネットワークインターフェースに割り当てる予定のMACアドレスなどを、IQNの一部として使用することで、一意のIQNを作成してください。
IQNが重複している状態で、同時にアクセスを行うとデータが破損する危険性があります。
"I/O仮想化オプション"で提供された仮想MACアドレスを使用する場合の例を以下に示します。
例
MACアドレスが00:00:00:00:00:FFの場合
IQN iqn.2010-04.com.fujitsu:0000000000ff
決定したIQNは、サーバ側の設計とストレージ側の設計で使用します。
サーバ側の設計
サーバごとに利用するIQNを割り当て、サーバ側の設計で使用します。
ストレージ側の設計
サーバごとに接続するボリュームを決定し、サーバに割り当てたIQNと同じIQNを、ストレージ側の設計で使用します。