

| Symfoware Active DB Guard 解説書 |
目次
索引
 
|
| 第1章 概要 |
Active DB Guardの概要について、説明します。
社会基盤システムや企業の情報システムが扱うデータは、年々、その種類やデータ量が増え続けています。また、インターネットの普及に伴い、ビジネスやサービスの多様化が進み、24時間365日稼働のニーズが高まりつつあります。このようなミッションクリティカルなシステムでは、業務の継続といった高可用性と同時に業務で利用するデータのバックアップが重要視されています。
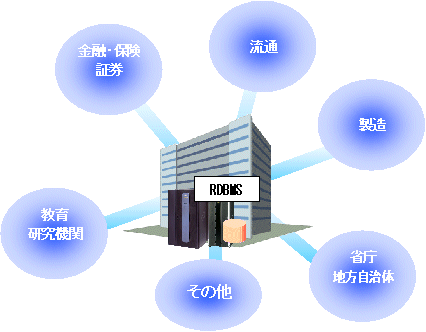
このような情報システムでは、業務で利用するさまざまなデータをRDBMS(Relational DataBase Management System)で管理します。そのため、RDBMSに対する要求は厳しく、高水準での信頼性を求められます。
近年、業務の継続という観点から、大地震などの災害に対する情報システムの高可用性が求められるようになりました。大地震などにより情報システムが被災した場合には、情報センタそのものが被害を受けるため、一般的なローカルなクラスタシステムでは、業務の継続が困難になる場合があります。
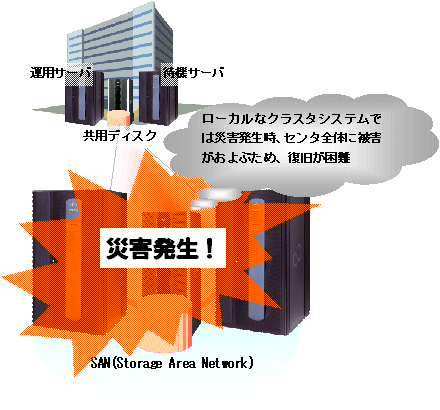
上記のような事態に備えて、被災した情報システムセンタとは別に、災害対策システムを遠隔地に用意しておくことで、業務の運用継続が可能になります。このように、災害発生時の業務継続を目的にしたシステムを、ディザスタリカバリシステムと呼びます。
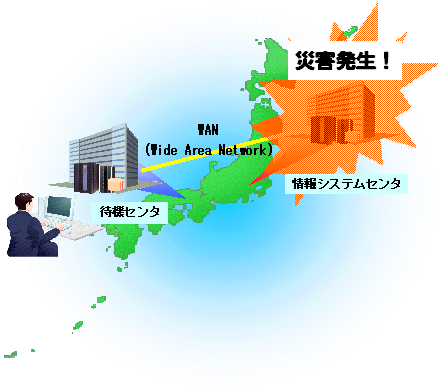
ディザスタリカバリシステムは、情報システムの業務継続を目的としたシステムです。そのため、情報システムセンタの業務を継続するために必要な資産を待機センタですべて用意する必要があります。業務継続に必要な資産には、ハードウェアやソフトウェアの物的資産、オペレータやシステム管理者といった人的資産、そして、業務で利用するデータがあります。これらの資産の中で、特に業務で利用するデータについては、業務の運用中に随時更新が入るため、待機センタで利用するには、データの更新に応じてバックアップを行う必要があります。そして、有事の際にはバックアップしたデータを利用できるように準備する必要があります。
一般的にディザスタリカバリシステムでは、業務の継続に向け2つの目標を設定します。1つは、災害発生時にシステムがダウンした場合、ダウンしたシステムの業務が再開できるまでの目標時間を設定します。これをRTO(Recovery Time Objective)と呼びます。もう1つは、災害発生時にシステムダウンが発生した場合、データの状態をシステムダウンからどこまでさかのぼって復旧するかの目標を設定します。これをRPO(Recovery Point Objective)と呼びます。
また、システムの稼働再開を目標としてRTOとRPOを設定し、それを実行するために計画を立てます。このような計画を事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)と呼びます。BCPは、復旧目標を実行に移すための具体的な手順を示したもので、その計画はPDCA(Plan-Do-Check-Action)によってマネージメントを行います。
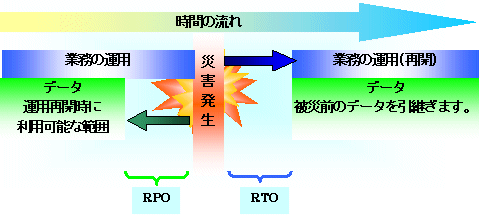
RTOとRPOは、運用している情報システムの重要度にあわせて設定する必要があります。例えば、企業の運用システムの場合、そのシステムの停止で損失するビジネスの機会や金額に応じた設定を行います。また、社会基盤システムでは、ライフラインなどの復旧時間に応じて設定を行います。特に、情報システムの中核に位置する基幹情報システムでは、ディザスタリカバリシステムに対しても高可用性が必要なため、迅速な業務の復旧が要求されます。
Active DB Guardは、RTO、RPOへの要求が厳しい企業の基幹情報システムや社会基盤システムにおいて、ディザスタリカバリシステムの中核を担い、災害発生時に業務の運用継続を強力に支援します。
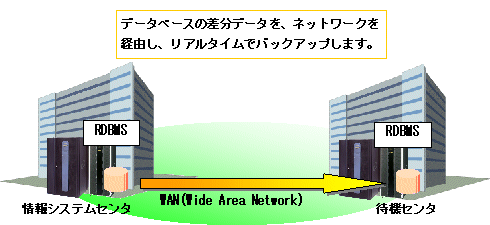
Active DB Guardを導入することにより、情報システムで利用中のデータベースのバックアップを待機センタでリアルタイムに行い、データベースの複製を作成することが可能になります。そして、有事には待機センタでデータベースの複製を利用し、被災した情報システムセンタに替わり、運用継続を実現します。
目次
索引
 
|