RMSは、ノード、ユーザアプリケーション、システム資源に対して直接処理を行うのではなく、RMS構成で定義された仮想のオブジェクト間でのみ通信を行います。以下の図は、オペレーティングシステム環境における実際のユーザアプリケーションと対応するRMS構成のuserApplicationオブジェクトとの関係を示しています。
図1.2 RMSとオペレーティングシステム間のインタフェース
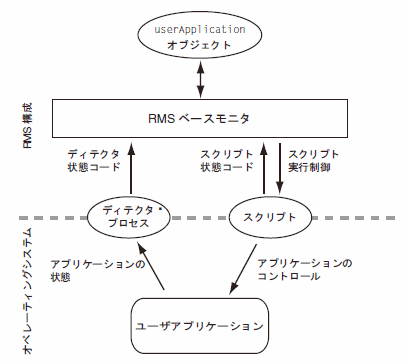
RMS仮想オブジェクトと実システム間のインタフェースは、RMSウィザードの提供するスクリプトとディテクタがすべて行います。スクリプトは、自らの処理が正しく終了したかどうかを復帰値によって通知し、RMSは、オブジェクトのディテクタから送られてきた状態コードと照らし合わせてオブジェクトの状態を判別します。RMSが、オペレーティングシステム環境 (図中点線より下の部分) でユーザアプリケーションに何が発生したかを認識する方法はこれ以外にありません。
たとえば userApplicationオブジェクトのOnlineスクリプトから成功が通知されると、実際のユーザアプリケーションの状態に関係なくRMSは、オブジェクトがOnline状態にあるものと判断します。逆に、リソースオブジェクトのディテクタからOffline状態の通知があっても、必ずしもその物理資源が使用不可であるとは限りません。
ポイント
高可用性を確保するには、対応する現実の機器を正しく制御するスクリプトと、機器の状態を正確に通知するディテクタがRMSに必要です。
RMS構成で使用する用語
このマニュアルでは、RMS側 (図の点線から上部分) での構成手順について説明しています。厳密に言うと、本書の主目的はSysNodeオブジェクト、userApplicationオブジェクト、およびその他のRMSエンティティの説明であり、それらが表している現実の機器の説明ではありません。
しかしながら、「SysNodeオブジェクト」よりも「ノード」、「userApplicationオブジェクト」よりも「アプリケーション」という用語を使用するほうが、直観的に分かりやすいと思われます。両者の関係は非常に密接で、かつ、われわれが常にRMSの概念を基に議論していることがはっきりしているからです。これにはさらに、技術的な議論の多くを単純化できるという利点もあります。このため、特にRMSオブジェクトとそれが表す実体との区別が必要となる場面をのぞき、本書およびRMSウィザードでは、以下の各用語は同じ意味で使用します。
「ノード」、「SysNodeオブジェクト」、「SysNode」
「アプリケーション」、「userApplicationオブジェクト」、「userApplication」
「リソース」、「gResourceオブジェクト」、「gResource」
オブジェクトの状態と属性の記述は同様に簡略化されます。たとえば、「マウントポイントxyzを監視するgResourceオブジェクトは、Offline状態にある」という言い方は非常に正確ではありますが長々しいため、通常は、「xyzファイルシステムはOfflineである」といいます。また、スクリプト名も、「PreOnlineScript属性で指定されたスクリプト」という代わりに、簡略化して「PreOnlineScript」と呼ぶのが普通です。
なお、RMSが扱う、すべてのオブジェクトを総称して、「RMSリソース」と記載します。