SnapOPC/SnapOPC+の複製先ディスクに対して設定可能なセッションは1つです。
図7.11 複製先ディスクに対してセッションを1つ設定した場合
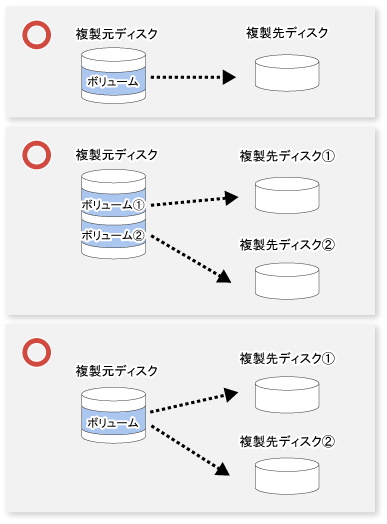
以下の図のように、1つの複製先ディスクに対して複数のセッションは設定できません。
図7.12 複製先ディスクに対して複数のセッションを設定した場合
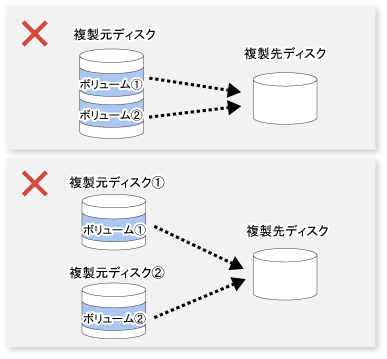
SnapOPCの複製元ディスクに対して、SDVの複製先ディスクとTPV/FTVの複製先ディスクが混在するセッションは設定可能です。一方、SnapOPC+の複製元ディスクに対して、SDVの複製先ディスクとTPV/FTVの複製先ディスクが混在するセッションは設定できません。
図7.13 複製先ディスクにSDVとTPVが混在する複数のセッションを設定した場合
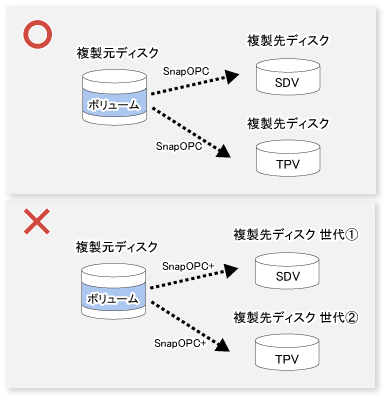
複製先ディスクの物理容量が不足すると、複製先ボリュームへアクセスできなくなります。このため、以下の手順のとおり、複製先ボリュームに必要な物理容量を見積もってから、複製先ディスクを作成してください。
複製先ボリュームに必要な容量の見積り
複製先ボリュームに必要な物理容量を見積もるには、複製元ボリュームの更新量の測定が必要です。測定方法は、運用によって異なります。
1対1のレプリケーション運用の場合(SnapOPC/SnapOPC+)
ペアに対して、セッションを開始し、停止または新たにセッションを開始するまでの間に複製元ボリュームに対して発生した更新量を測定します。
1対Nのレプリケーション運用の場合(SnapOPC)
すべてのペアに対して、セッションを開始し、停止または新たにセッションを開始するまでの間に複製元ボリュームに対して発生した更新量を測定し、すべての更新量を合算します。
1対Nのレプリケーション運用の場合(SnapOPC+)
すべてのペアに対して、セッションを開始し、次の世代へSnapOPC+を行うまでの間に複製元ボリュームに対して発生した更新量を測定し、すべての更新量を合算します。
複製元ボリュームの更新量は、swstestupdateコマンドを利用して、以下の手順で測定してください。
複製元ボリュームに対してモニターセッションを設定し、更新量の測定を開始します。
# /opt/FJSVswsts/bin/swstestupdate start /dev/sda1 /dev/sda1 swstestupdate completed #
業務を開始します。
業務によって発生した更新ブロックがハードウェアに記録されます。
測定期間が経過したあと、更新ブロック数を確認します。
# /opt/FJSVswsts/bin/swstestupdate status /dev/sda1 Volume-Name Update /dev/sda1 644333 #
測定完了後、モニターセッションを解除します。
# /opt/FJSVswsts/bin/swstestupdate stop /dev/sda1 /dev/sda1 swstestupdate completed #
見積り式を以下に示します。
(複製元ボリュームの更新量) × (安全係数) < (複製先ボリュームの物理容量)
ポイント
事前の見積りが難しい場合、複製先ボリュームの物理容量はコピー元総容量の30~50%を推奨します。推奨値のため、運用状況に合わせて変更が必要です。
複製先ディスクの作成
複製先ディスクは、Storage CruiserまたはETERNUS Web GUIを使用して作成してください。
ポイント
複製先ディスクの論理容量は、複製元ディスクと同じ容量に設定してください。
複製先ボリュームに必要な物理容量からディスク増設を検討してください。
TPVを複製先ボリュームにする場合
Storage CruiserまたはETERNUS Web GUIを使用してシン・プロビジョニングプールの状態を確認し、シン・プロビジョニングプールの容量を拡張してください。
Storage Cruiserを利用する場合の作業手順は、『ETERNUS SF Webコンソール説明書』の「シン・プロビジョニングプールの表示」および「シン・プロビジョニングプールの容量拡張/フォーマット/閾値変更/削除」を参照してください。
FTVを複製先ボリュームにする場合
Storage CruiserまたはETERNUS Web GUIを使用してTierプールの状態を確認し、Tierプールのサブプール容量を拡張してください。
Storage Cruiserを利用する場合の作業手順は、『ETERNUS SF Webコンソール説明書』の「Tierプールの表示」および「Tierプールのサブプール容量拡張」を参照してください。
SDVを複製先ボリュームにする場合
swstsdvコマンドまたはETERNUS Web GUIを使用してSDPの状態を確認し、SDPの容量を拡張してください。
SDPはSDPV(Snap Data Pool Volume)という専用のボリュームを作成することで有効となり、作成したSDPVは自動的にSDPに組み込まれます。SDPの容量は、複製先ボリュームに割り当てる物理容量のSDPVを作成することで拡張します。
swstsdvコマンドを利用する場合の作業手順は、以下のとおりです。
"poolstat"サブコマンドを指定してコマンドを実行し、SDPの状態を確認します。
ETERNUS Web GUIからSDPVを作成します。
SDVを複製先ボリュームにする場合は、そのSDVを初期化してください。SDVの物理容量を無駄に消費することを避けるため、SDVを初期化したあとの更新は、ファイルシステムの作成など必要最低限にしてください。
参照
Storage Cruiserを利用したTPV/SDV/SDPVの作成手順は、『ETERNUS SF Webコンソール説明書』の「ボリュームの作成」を参照してください。FTVの作成手順は、『ETERNUS SF Webコンソール説明書』の「FTVの作成」を参照してください。
コピー先ボリュームの物理容量が不足すると、コピー先ボリュームへアクセスできなくなります(コピー先ボリュームのデータを読み出すこと、コピー先ボリュームへデータを書き込むことができない状態になります)。SnapOPC+の場合、読み書きできなくなったコピー先ボリュームだけでなく、それ以前の世代のコピー先ボリュームも読み書きできなくなります。
このため、運用時はコピー先ボリュームの物理容量が不足しないように監視する必要があります。
TPV/FTVを複製先ボリュームにする場合の監視
TPV/FTVの物理容量は、ブロック単位で割り当てられます。このため、見積りより多くの物理容量を必要とする可能性があります。複製先ボリュームの物理容量が不足しないように、Storage Cruiserを利用して、必要に応じて容量閾値の設定変更を行い、使用量を監視してください。
TPVの監視に関する詳細は、『ETERNUS SF Storage Cruiser 運用ガイド』の「シン・プロビジョニング管理」を参照してください。
FTVの監視に関する詳細は、『ETERNUS SF Storage Cruiser 運用ガイド』の「ストレージ自動階層制御管理」を参照してください。
ポイント
TPV/FTVを複製先ボリュームにした場合、複製先のTPV/FTVを作成したプール(TPVの場合はシン・プロビジョニングプール、FTVの場合はTierプール)の空き容量が不足したときも複製先ボリュームへアクセスできなくなります。このため、TPV/FTVを複製先ボリュームにした場合は、複製先のTPV/FTVの空き容量、および複製先のTPV/FTVを作成したプールの空き容量が不足しないように監視してください。
SDVを複製先ボリュームにする場合の監視
SDVだけを使用する場合(SDPを設定しない場合)
定期的に、"stat"サブコマンドを指定してswstsdvコマンドを実行し、SDVの容量が不足していないかを監視してください。
SDPを使用する場合(SDPを設定した場合)
定期的に、"poolstat"サブコマンドを指定してswstsdvコマンドを実行し、SDPの容量が不足していないかを監視してください。
SDPの領域において、暗号化に関係なく使用率が50%を超える領域が存在した場合は、SDPVの追加を検討してください。また、SDPの監視頻度を高くしてください。
SDPの領域において、暗号化に関係なく使用率が70%を超える領域が存在した場合は、直ちにSDPVを追加してください。
ポイント
コピー先ボリュームの容量が不足した場合は、「10.4.2.3 複製先ボリュームに物理容量不足が発生した場合の対処方法」を参照して対処してください。
アクセスボリュームの作成
SDVまたはSDPの容量が不足すると、コピー先ボリュームへアクセスできなくなります。また、SDVおよびSDPの容量不足以外でも、以下の場合は、コピー先ボリュームへアクセスできなくなります。
SDVを初期化したあとの、SDVへのアクセス
ディスクの管理情報を初期化したあとの、SDVへのアクセス
このため、事前に、SDVとは別のボリューム(アクセスボリューム)を準備しておくことを推奨します。
アクセスボリュームとして利用するボリュームは、SDVと同じETERNUS ディスクアレイに作成してください。アクセスボリュームはデータの格納に使用しないボリュームのため、容量は少なくても問題ありません。任意のサイズで作成してください。
アクセスボリュームを作成することで、以下の操作が可能となります。
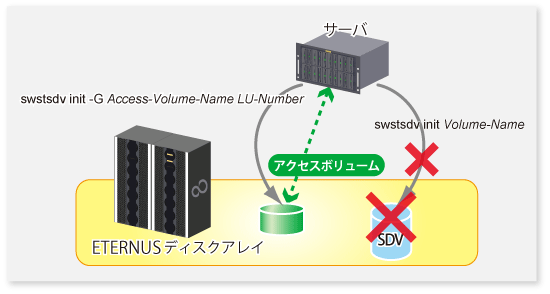
SnapOPC/SnapOPC+の複製先ボリュームを、クラスタシステムの共用ディスクとして利用しないでください。物理容量が不足した際にクラスタシステムがフェイルオーバすることを回避するためです。
クラスタ運用の場合は、以下のどちらかの方法によって、SnapOPC/SnapOPC+の複製先ボリュームを共用ディスクにしない必要があります。
SnapOPC/SnapOPC+の複製先ボリュームをクラスタシステムの全ノードから参照できるようにする
クラスタシステムと非クラスタシステムのサーバ間レプリケーション運用にする