1つの仮想インタフェースに対して、論理的なインタフェースを作成することができます。これを論理仮想インタフェースと呼びます。この機能により、アプリケーション単位に異なる仮想IPアドレスを使用することができます。
注意
論理仮想インタフェースに割付ける仮想IPアドレスは、仮想インタフェースと同じサブネットである必要があります。
以下の図2.26 論理仮想インタフェース定義例に、仮想インタフェースsha0に論理仮想インタフェースを2つ定義した場合の例を示します。sha0,sha0:2,sha0:3には、すべて同じサブネットのIPアドレスを設定します。
図2.26 論理仮想インタフェース定義例
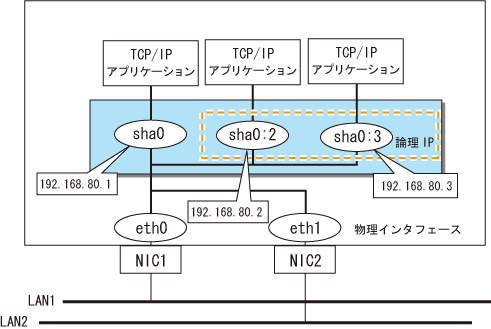
論理仮想インタフェースとして作成できるインタフェースの数は、論理番号が2から64までの63個になります。なお、65番以降の論理番号をもつ論理仮想インタフェースは、クラスタ構成時の引継ぎ仮想インタフェースとして使用されます。
クラスタ構成のGS連携方式の場合、論理仮想インタフェースを使用することで、同じネットワークに属する仮想IPアドレスをクラスタ間で引き継ぐことができます。
図2.27 論理仮想インタフェース定義例(クラスタ構成のGS連携方式)

注意
本機能は、高速切替方式、仮想NIC方式、およびGS連携方式の場合に使用できます。
NIC切替方式の場合は、物理インタフェース共有機能を使用することにより、本機能と同等の処理(1つの物理インタフェースに複数のIPアドレスを割当てる処理)を行うことができます。
仮想NIC方式の場合、GLSのコマンドではなく、OSの定義ファイル(/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-sha0:2)を作成して設定します。定義ファイルには、"DEVICETYPE=sha"を設定しないでください。