仮想インタフェースを複数定義し、各々のリソースを別クラスタアプリケーションとして設定することにより、相互待機運用を行うことができます。
起動時の動作については、クラスタアプリケーションが複数ある点以外は、運用待機の場合と同様です。詳細は“5.4.2.1 起動”を参照してください。
通常運用時は、それぞれのノード上の仮想インタフェースを使用して相手システムと通信を行います。運用ノード上で異常発生時(パニック、ハングアップまたは伝送路異常)は、その運用ノードに含まれる仮想インタフェースが待機ノードに引き継がれます。アプリケーションがコネクション再接続を行うことによって運用ノードの通信を引き継ぎます。
図5.21 NIC切替方式による相互待機構成(NIC共用なし)に、NIC切替方式(NIC共有なし)による相互待機構成図を示します。
アドレスの引継ぎ方法などは、運用待機構成と同様です。詳細は、“5.4.2.2 切替え”を参照してください。
図5.21 NIC切替方式による相互待機構成(NIC共用なし)
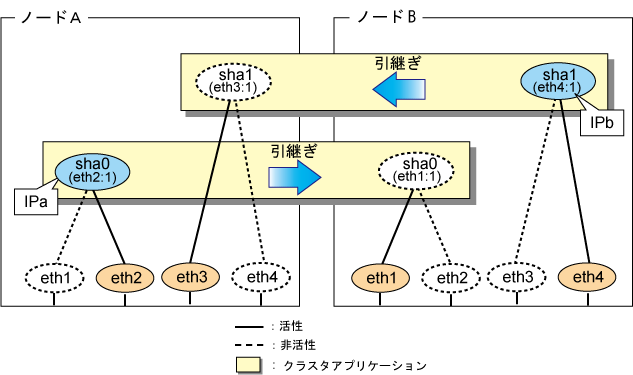
図5.22 NIC切替方式による相互待機構成(NIC共用あり)に、NIC切替方式(NIC共有あり)による相互待機構成図を示します。
アドレスの引継ぎ方法などは、運用待機構成と同様です。詳細は、“5.4.2.2 切替え”を参照してください。
図5.22 NIC切替方式による相互待機構成(NIC共用あり)
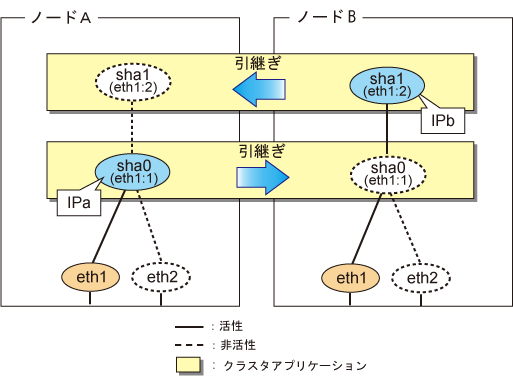
切戻しの手順は高速切替方式の場合と同様です。詳細は“5.4.1.3 切戻し”を参照してください。
停止時の動作は運用待機の場合と同様です。詳細は“5.4.2.4 停止”を参照してください。