ディスク装置に異常が発生した場合は、当社技術員 (CE) に連絡し、ディスク装置を交換する必要があります。
GDS では、活性交換か非活性交換かによらず、ディスク装置交換作業の前後に以下の処理が必要です。
物理ディスク交換
物理ディスク復旧
注意
異常が発生したディスク装置の特定
ディスク装置のハードウェア的な異常箇所は、/var/adm/messages ファイルに記録されるディスクドライバのログメッセージなどをもとにして特定してください。詳細については、「F.1.11 ディスク装置の異常」を参照してください。
注意
FC-AL 内蔵ディスクの交換
FC-AL 内蔵ディスクは、本手順では交換できません。詳細については、「A.2.31 内蔵ディスクの交換 (FC-AL) 」を参照してください。
注意
SPARC T3-1 / T3-2 / T3-4 内蔵ディスクの交換
SPARC T3-1 / T3-2 / T3-4 内蔵ディスクは、本手順では交換できません。詳細については、「A.2.32 内蔵ディスクの交換 (SPARC T3-1 / T3-2 / T3-4) 」を参照してください。
注意
物理ディスク交換時の注意事項
「A.2.16 物理ディスクの交換」を参照してください。
物理ディスク交換
ディスク装置の交換を行うために、物理ディスクを切り離します。
手順を以下に示します。
対象の物理ディスクの状態表示
メイン画面中に交換対象の物理ディスクを表示し、そのアイコンをクリックして対象の物理ディスクを選択します。
[物理ディスク交換] メニューの選択
メイン画面の [操作]:[物理ディスク交換] を選択します。
図5.86 物理ディスク交換
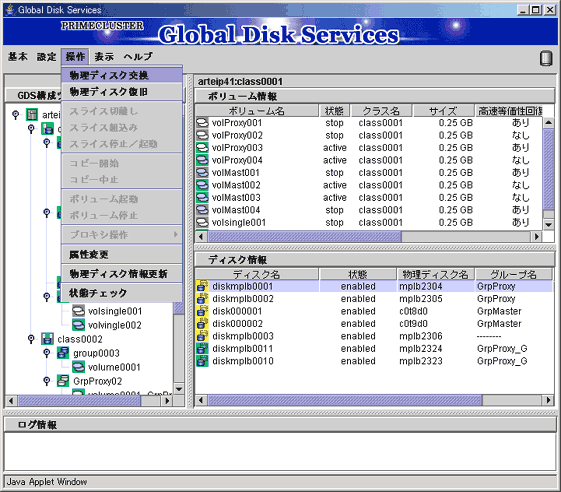
以下の確認画面が表示されます。
処理を続ける場合は、<はい> をクリックします。<いいえ> をクリックすると、物理ディスク交換処理を取り消します。
図5.87 物理ディスク交換確認画面
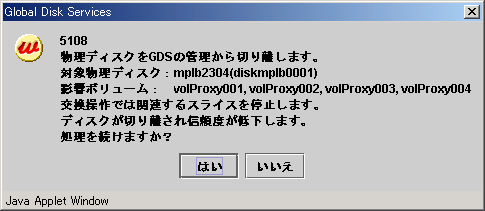
物理ディスク交換の依頼
<はい> をクリックすると、以下の切離し完了通知画面が表示されます。
<確認> をクリックし、当社技術員 (CE) にディスク装置の交換を依頼してください。
図5.88 切離し完了通知画面
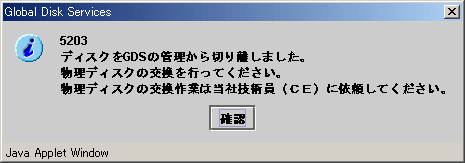
注意
新しいディスクに交換した場合
交換したディスクにラベルが作成されていない場合、「物理ディスク復旧」を行う前に、format(1M) コマンドを使用してラベルを作成する必要があります。ラベルの有無は、format(1M)コマンドのverifyメニューで確認できます。
物理ディスク復旧
ディスク装置の交換作業が完了すると、交換した物理ディスクを組み込みます。
手順を以下に示します。
復旧する物理ディスクの選択
復旧する物理ディスクを選択します。
[物理ディスク復旧]メニューの選択
メイン画面の [操作]:[物理ディスク復旧] を選択します。
図5.89 物理ディスク復旧
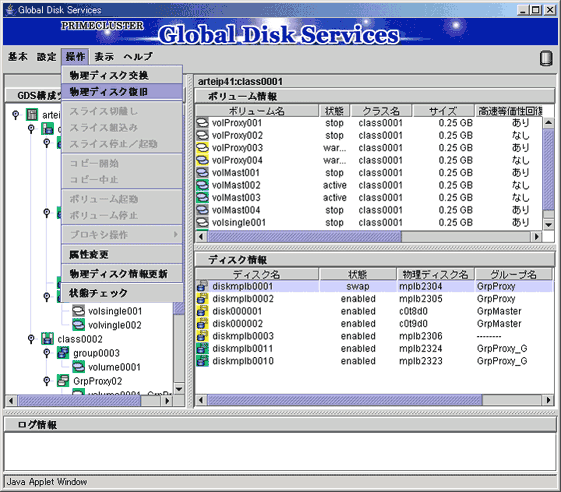
以下の確認画面が表示されます。
処理を続ける場合は、<はい> をクリックします。<いいえ> をクリックすると、物理ディスク復旧処理を取り消します。
図5.90 物理ディスク復旧確認画面
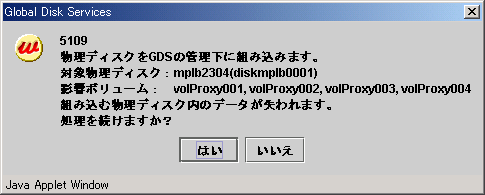
組込み完了通知
<はい> をクリックすると、以下の組込み完了通知画面が表示されます。
図5.91 組込み完了通知画面
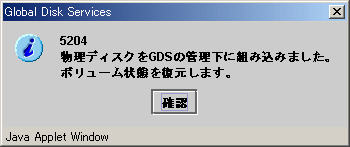
注意
クラスタシステムの場合
PRIMECLUSTER のリソースデータベースにディスクリソースが登録されている物理ディスクを交換した場合、物理ディスク復旧が完了した後、クラスのタイプに関わらず、自動リソース登録を実行する必要があります。これは、PRIMECLUSTER のリソースデータベースに登録されている、交換前のディスクの VTOC のボリューム名を、交換後のディスクの VTOC に反映するためです。自動リソース登録を行わなかった場合、ノード起動時に、ディスク装置の結線誤りを示すメッセージの出力や、フェイルオーバが発生することがあります。自動リソース登録の詳細については、「PRIMECLUSTER 導入運用手引書」を参照してください。