管理対象機器の棚卸を支援するための機能で、操作として以下があります。
部門別/分類別/場所別による棚卸状況の確認
棚卸の状態変更
棚卸の運用設定
棚卸状況の台帳保存
設置場所の補正
さらに、ATと連携する場合には、以下の操作ができます。
ATと連携した棚卸
ユーザーの操作要件にあった棚卸状況を表示します。
棚卸状況の検索が簡単にでき、用途にあった検索結果を表示できます。
管理対象機器の棚卸対象台数や棚卸状況などを、部門別/分類別/場所別に表示します。
たとえば、部門別に集計情報を表示した場合、以下のように表示されます。
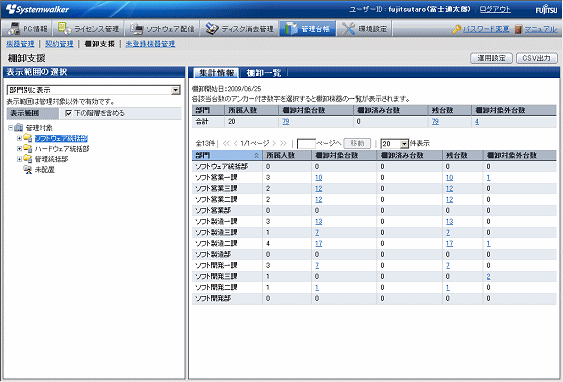
管理対象機器の棚卸対象機器の一覧を、部門別/分類別/場所別に表示します。
たとえば、部門別に一覧表示した場合、以下のように表示されます。
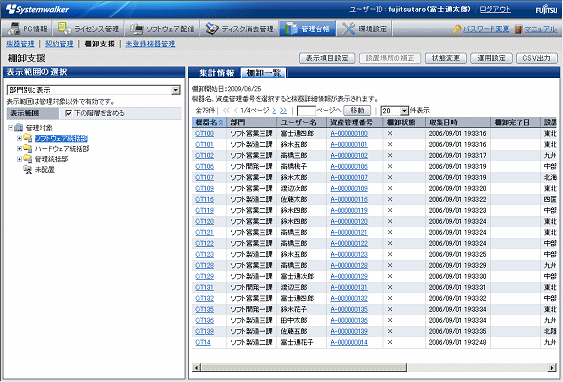
棚卸対象の機器に対して、管理者が手動により棚卸の状態を変更することができます。設定できる内容は以下のとおりです。
棚卸済みに設定
棚卸未完に設定
棚卸対象外に設定
棚卸実施済みかどうかの設定のほか、棚卸対象としない機器については、棚卸対象外に設定することができます。
棚卸対象の機器に対して、以下の運用設定を行います。
棚卸開始日の設定
棚卸状態の判定方法
設置場所の補正結果
棚卸対象の機器に棚卸開始日を設定すると、この設定日から現在日時の間に機器の存在を確認できた場合に、自動的に棚卸済みとなります。たとえば、Systemwalker Desktop Patrolでインベントリ情報が収集された場合や、ATと連携した棚卸が行われた場合は、棚卸済みとなります。
棚卸開始日を設定することで、Systemwalker Desktop Patrolで収集されたインベントリ情報でPCの棚卸確認、また機器情報の自動検知による棚卸確認ができます。この結果、棚卸の確認作業を削減することができ、確実に管理を実施できます。
なお、Systemwalker Desktop Patrolでインベントリ情報が収集されたことを契機に棚卸済みとするには、棚卸状態の判定方法を設定する必要があります。
棚卸対象の機器が遠隔地にあるなどの理由で、Systemwalker Desktop Patrolによるインベントリ収集やATと連携した棚卸ができない場合には、棚卸状況の一覧表示の画面でシステム管理者が対象機器を棚卸済みと設定できます。逆に、棚卸済みとなった機器を棚卸未完に戻すことも可能です。
このように、棚卸済み/棚卸未完の設定をシステム管理者が変更でき、さまざまな運用要件に対応できます。
棚卸状況(集計情報、棚卸一覧)をそれぞれCSVファイルに保存します。
保存したデータは、ほかのドキュメントへの活用や、ほかのシステムとの情報連携やデータ比較などに利用できます。
設置場所の補正
インベントリ収集や、ユーザー手動入力によって、資産台帳に登録された機器のIPアドレスと、管理者があらかじめ登録したセグメント管理情報を用いて、設置場所の補正を行います。機器の移設などにより、機器のIPアドレスが変更された場合は、棚卸時に設置場所の補正を行うことで、容易にかつ正確に設置場所を資産台帳に反映することができます。
棚卸対象の機器に対してバーコードラベルを作成し、ATと連携して棚卸を行います。
Systemwalker Desktop Patrolで管理している資産情報からバーコードラベルを作成し、現地でATを使用してバーコードを読み込み、その結果を資産情報に反映する作業を体系化することで、棚卸業務を確実に行うことができ、管理作業を軽減できます。
棚卸対象の機器に対して以下のようなバーコードラベルを作成します。対応するバーコードの規格は「Code-39」です。
バーコードラベルは棚卸対象の機器に貼り、ATで棚卸を行うときに使用します。
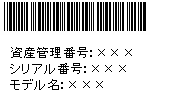
棚卸対象の機器に貼ったバーコードラベルをATで読み込み、棚卸結果をSystemwalker Desktop Patrolで管理する資産情報へ反映します。この作業を行うために、棚卸を行う機器情報のATへの抽出と、ATで棚卸を実施した結果の取り込みを行います。