IT(Information Technology)を活用した社会システムが、生活の様々なシーンで利用されています。例えば、コンビニエンスストアにおけるチケット予約や ATM による現金引出し、携帯電話でのeメール、写真メール、インターネット接続、インターネット経由の宅配便の配達状況確認などがあります。これらの社会システムは24時間、365日止まることなく、突発的なアクセス集中にも迅速に追随することが求められています。
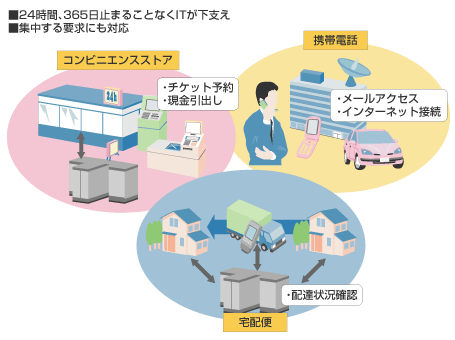
IT が生活シーンの隅々まで浸透することで、これらのシステムを支えるストレージのデータ量が増大し、管理負担が増す傾向にあります。また、ビジネスで重要な情報の蓄積によって、データへの常時アクセスが必須となったため、問題発生時は早急な復旧が要求されます。この裏付けとして、ストレージ投資の判断基準で、運用管理とシステムの信頼性を重視するお客様が多いというアンケート結果(以下のグラフ)もあります。
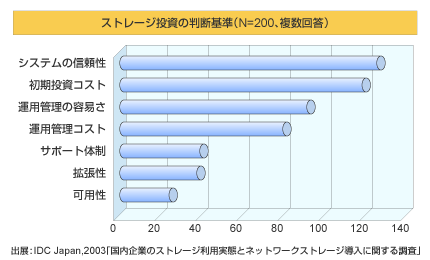
このような背景から、サーバノード直結ストレージ(DAS)に代わる技術として、ストレージをサーバノードから独立させ、複数サーバノードに分散していたデータを集約するネットワークストレージ(SAN や NAS)の導入が進んでいます。DAS の場合はサーバノードごとのストレージ管理が必要で、その結果、未使用領域が多数のストレージ装置に散在することもしばしばですが、ストレージ装置を集約することで、管理の一元化による運用管理コストの削減や、ストレージ容量の有効活用が可能になりました。この意味で、SAN などのネットワークストレージはシステムの全体最適化をストレージの面から推進するものと言えます。
しかし、ストレージ装置やサーバが増加して SAN 構成が複雑になるのに伴い、信頼性や性能が最適の構成を設計するには高度なノウハウが要求されるとともに、問題が発生した際に原因箇所を特定し、どの業務のどのデータに影響するかの把握が困難になってきました。これは、サーバノードとストレージ間の接続構成が複雑になり、データを格納するストレージとアプリケーションとの対応関係を人手で管理できなくなってきたことを意味しています。言い換えれば、従来の管理手法の延長では、システムとして一定のサービスレベルを維持することが難しくなっています。