性能管理ウィンドウのメニューバーの1つの機能である[閾値監視]から選択される機能説明を以下に記述します。ただし、機能を有効にするにはツリーから対象装置を選択する必要があります。また、対象装置はすでに性能監視指示が行われている必要があります。
閾値監視有効/無効
これを選択することで、対象装置の閾値監視機能の有効/無効を指示できます。選択すると、現在の閾値監視状態の逆の状態を指示することになり、その旨のダイアログが表示されます。以下の画面例は、上が無効状態から有効にする場合、下がその逆のダイアログ表示です。
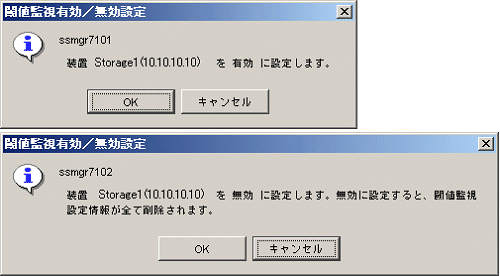
閾値監視時間設定
これを選択することで、下図のダイアログが表示されます。対象装置の閾値監視時間帯およびアラーム発生時のイベントログへの表示時間帯を指定できます。
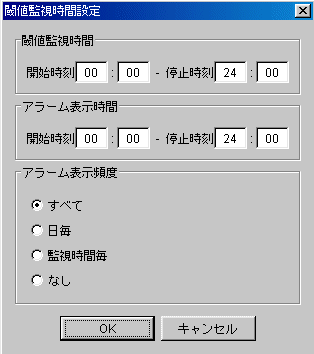
閾値監視時間 | 開始時刻と停止時刻を指定できます。指定は24時内となります。 | |
アラーム表示時間 | 閾値監視時間内の中で、さらにイベントログ表示を行う開始時刻と停止時刻を指定します。指定は24時内となります。 | |
アラーム表示頻度 | 『アラーム表示頻度』は閾値条件が発生した場合に作成されるイベントログへの表示の仕方を定義します。 | |
すべて | アラームログが作成されるたびにイベントログ表示を行うことを意味します。 | |
日毎 | アラームログが発生しても1日に1回しかイベントログ表示を行いません。 | |
監視時間毎 | 下図[閾値設定/監視開始/監視停止]で指定する閾値監視単位時間ごとに1回のイベントログ表示となります。 | |
なし | アラームログを作成してもイベントログ表示を行わないことを意味します。[閾値監視アラームログ]ではすべてのアラームログを確認できます。 | |
注意
設定を行わない場合は、監視時間帯およびイベントログへの表示時間帯は0時0分から24時0分の1日となり、イベントログへの表示は発生のたびに常に報告するモード設定となります。
『アラーム表示頻度』で『日毎』『監視時間毎』『なし』を指定した場合は、装置単位でのイベントログ表示を抑止することになります。
閾値設定/監視開始/監視停止
これを選択することで、図のダイアログが表示されます。対象装置の閾値監視の閾値条件を設定するダイアログです。下図はLogicalVolumeレスポンスタイムとRAIDGroupビジー率とCMビジー率を指定し、<監視開始>ボタンを指示した例です。
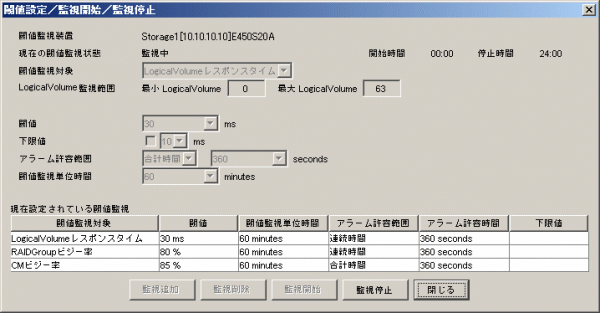
<監視追加>ボタン | 選択/設定した閾値監視の閾値条件をリストに表示・登録します。すでに「閾値監視対象」がある場合は、変更指示とみなし、更新します。 |
<監視削除>ボタン | 現在設定されている閾値監視のリストに表示されている閾値条件をすべて削除します。ただし、以前に監視開始を指示した内容は削除されません。 |
<監視開始>ボタン | 現在設定されている閾値監視のリストに表示されている閾値条件で閾値監視が開始されます。また、設定された閾値条件は保持されます。 |
<監視停止>ボタン | 閾値監視を停止します。閾値監視の閾値条件修正が可能となります。 |
<キャンセル>または<閉じる>ボタン | 「閾値設定/監視開始/監視停止」ダイアログを閉じます。ただし、閾値監視の閾値条件の入力中は入力内容を破棄します。 |
以下に閾値監視の閾値条件の各項目について説明します。
「閾値監視装置」 | 対象とした装置のニックネームとIPアドレスおよびタイプを表示します。 | |
「現在の閾値監視状態」 | 監視状態と[閾値監視時間設定]で設定した監視時間帯が表示されます。監視中はすでに<監視開始>ボタンが押され、監視中であることを示します。監視停止はその逆で監視停止状態にあることを示します。また、監視待機中は監視開始状態にあるが、現時刻が監視時間帯外の時間帯であるため、一時監視を停止していることを表しています。 | |
「閾値監視対象」 | LogicalVolume レスポンスタイム | Read/Write I/Oの平均処理時間を監視する場合に選択します。 |
RAIDGroupビジー率 | RAIDGroupを構成しているドライブ(DISK)の平均ビジー率を監視する場合に選択します。例えばRAID1+0(4+4)構成の場合、8本の平均を監視します。 | |
CMビジー率 | 装置内のCMの使用率を監視するときに選択します。 | |
LogicalVolume監視範囲 | 性能管理で指定した対象LogicalVolumeの範囲が表示され、閾値監視の対象LogicalVolumeになります。RAIDGroup、CMは閾値監視対象の装置に構成されている最大数を自動的に対象範囲としますので設定はありません。 | |
「閾値」 | 「閾値監視対象」で選択された項目に対する閾値を設定します。閾値監視中に性能値が閾値以上になった場合アラームとして検出されます。「閾値監視対象」で選択された項目に対してそれぞれのデフォルト値がリストから選択可能ですが、デフォルト値以外の値も入力できます。 | |
「下限値」 | 「アラーム許容範囲」の「合計時間」を設定した場合、かつチェックボックスを有効にした場合に下限値の設定が有効になります。リスト選択と値の入力が可能です。下限値を指定した場合、性能値がこの値以下になった場合、「合計時間」方式によるカウントがリセットされ、その時点から閾値超えをカウントし直します。 | |
「アラーム許容範囲」 | 合計時間 | 閾値監視単位時間内に閾値を超えた事象の時間の合計がこれで指定した時間に到達したときにアラームログが作られることを意味します。 |
連続時間 | 閾値監視単位時間内にこれで指定した時間、連続で閾値を超えている事象が検出されたときにアラームログが作られることを意味します。 | |
「閾値監視単位時間」 | 閾値を超えた時点から何時間までアラーム監視を行うかの単位時間を指定します。 | |
各パラメーターの関係を図に示します。
以下のような条件(アラーム許容範囲が『合計時間』)の場合、
閾値監視時間 | 0時0分から23時0分 | ||
アラーム表示時間 | 0時0分から14時0分 | アラーム表示頻度 | すべて |
閾値監視対象 | RAIDGroupビジー率 | 閾値 | 80% |
下限値 | 10% | ||
アラーム許容範囲 | 合計時間 360秒 | ||
閾値監視単位時間 | 60分 | ||
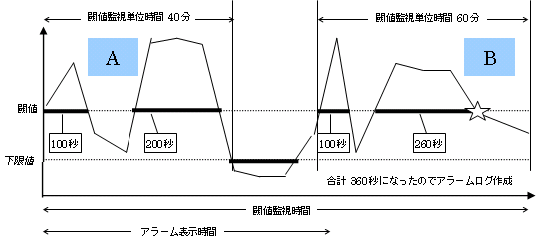
『閾値監視時間』の中で、Aでは性能値が閾値以上になった時間が300秒まで累計されていましたが、『閾値監視単位時間 60分』に満たないうちに下限値以下になったので情報がリセットされ、監視再スタートとなります。
『閾値監視時間』の中で、Bでは『閾値監視単位時間 60分』内で、性能値が閾値以上になった時間が 360秒まで累計されたので、アラームログが作成されます。『アラーム表示時間』で指定した時間外であるため、アラーム通知はイベントログには表示されません。
以下のような条件(アラーム許容範囲が『連続時間』)の場合、
閾値監視時間 | 0時0分から23時0分 | ||
アラーム表示時間 | 0時0分から23時0分 | アラーム表示頻度 | すべて |
閾値監視対象 | RAIDGroupビジー率 | 閾値 | 80% |
アラーム許容範囲 | 連続時間 360秒 | ||
閾値監視単位時間 | 60分 | ||
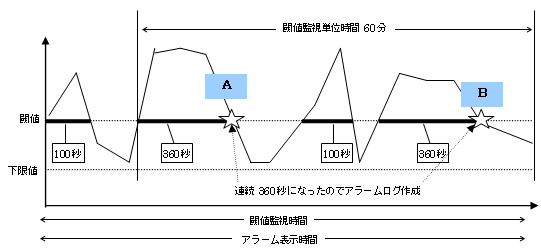
『閾値監視時間』の中で、A、Bとも連続360秒を超えたのでアラームログが作成されます。ただし、『アラーム表示頻度』が「監視時間毎」であるため、イベントログ通知へのアラーム表示は『A』のアラームだけとなります。
また、次図はスイッチのPortスループットを指定し、<監視開始>ボタンを指示した例です。
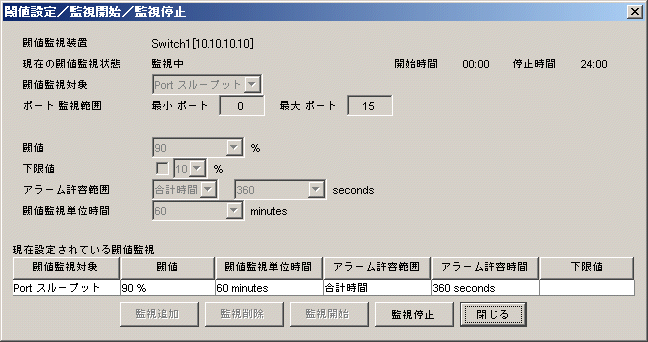
「閾値監視装置」 | 対象とした装置のニックネームとIPアドレスおよびタイプを表示します。 | |
「現在の閾値監視状態」 | 監視状態と[閾値監視時間設定]で設定した監視時間帯が表示されます。監視中はすでに<監視開始>ボタンが押され、監視中であることを示します。監視停止はその逆で監視停止状態にあることを示します。また、監視待機中は監視開始状態にあるが、現時刻が監視時間帯外の時間帯であるため、一時監視を停止していることを表しています。 | |
「閾値監視対象」 | Portスループット | 各ポートの受信・送信の合計スループットで監視する場合に選択します。 |
「ポート監視範囲」 | 性能管理で指定した対象スイッチが実装する全ポートが閾値監視の対象となります。 | |
「閾値」 | 「閾値監視対象」で選択された項目に対する閾値を設定します。閾値監視中に性能値が閾値以上になった場合アラームとして検出されます。「閾値監視対象」で選択された項目に対してそれぞれのデフォルト値がリストから選択可能ですが、デフォルト値以外の値も入力できます。 | |
「下限値」 | 「アラーム許容範囲」の「合計時間」を設定した場合、かつチェックボックスを有効にした場合に下限値の設定が有効になります。リスト選択と値の入力が可能です。下限値を指定した場合、性能値がこの値以下になった場合、「合計時間」方式によるカウントがリセットされ、その時点から閾値超えをカウントし直します。 | |
「アラーム許容範囲」 | 合計時間 | 閾値監視単位時間内に閾値を超えた事象の時間の合計がこれで指定した時間に到達したときにアラームログが作られることを意味します。 |
連続時間 | 閾値監視単位時間内にこれで指定した時間、連続で閾値を超えている事象が検出されたときにアラームログが作られることを意味します。 | |
「閾値監視単位時間」 | 閾値を超えた時点から何時間までアラーム監視を行うかの単位時間を指定します。 | |
「閾値」、「下限値」は対象スイッチのタイプ(1Gbps、2Gbps、または4Gbps)を判断し、1Gbpsであれば100MB/s、2Gbpsであれば200MB/s、4Gbpsであれば400MB/sを基準とし、基準値に対して何%を使用しているかを指定します。 例えば、スイッチのタイプが2Gbps、「閾値」が90%と設定されている場合、180MB/s(受信・送信の合計)が閾値となります。
閾値監視アラームログ
これを選択することで、次のダイアログが表示されます。すべての対象装置で検出された閾値監視アラームログ一覧が表示されます。表示内容はレポートID、日付、時間、重大度、確認、装置名とタイトルからなります。アラームログ一覧がすでに表示されている場合は新たなアラームログ一覧表示は行われず、すでに表示されているアラームログ一覧の内容が最新情報に更新され表示されます。
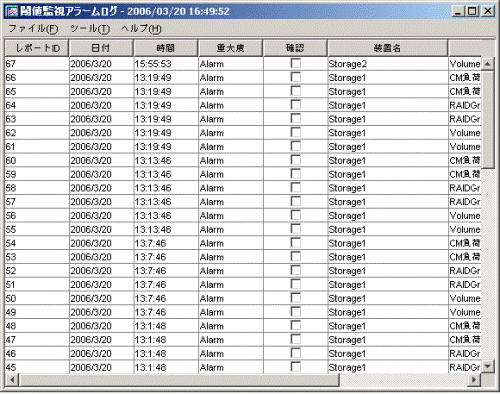
「レポートID」はアラームログの検出順に割り当てた管理番号です。最大で1000となります。
「日付」「時間」はアラームログが作成された日時を表示します。
「重大度」はアラームログの重要度が表示されます。現在はAlarmだけです。
「確認」はアラームログ詳細内の確認チェックボックスを指示し、保存を行ったことを示します。
「装置名」は対象装置を登録したときに付けられた装置のニックネームが表示されます。
「タイトル」はアラームログを作成した事象の題名を表示します。
このダイアログにはメニューバーがあり、[ツール]からアラームログ一覧の[検索]、[並べ替え]、[削除]、[最新情報に更新]の機能を選択できます。[削除]は複数指定できます。複数選択は[Ctrl]キーや[Shift]キーでWindows操作と同様に行えます。
また、メニューバーの[ファイル]から閾値監視アラームログ一覧の[印刷]、[選択行の印刷]の機能を選択できます。[印刷]は表示される閾値監視アラームログ一覧のすべてが印刷されます。[選択行の印刷]は表示される閾値監視アラームログ一覧から印刷したい行を選択した後に機能選択を行うことで選択行だけを印刷できます。行選択は複数指定が可能で、複数選択は[Ctrl]キーや[Shift]キーでWindows操作と同様に行えます。なお、印刷される作成日時は閾値監視アラームログ一覧が表示された日時となります。ただし、[削除]機能が選択された場合は閾値監視アラームログ削除後に閾値監視アラームログが再表示された日時が作成日時として印刷されます。
なお、アラームログの行でダブルクリックを行うと次のような指定レポートIDの詳細情報がダイアログに表示されます。この例はRAIDGroup負荷異常のレポートです。
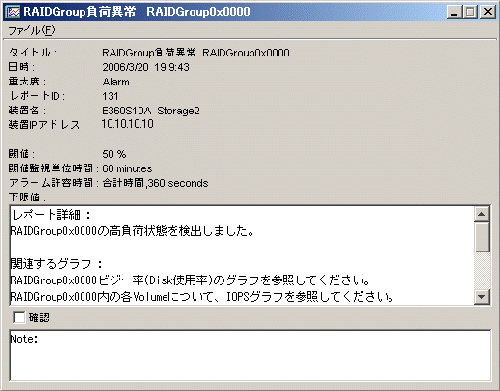
レポートの内容には、閾値設定で指定した閾値、閾値監視単位時間、アラーム許容時間、下限値などが表示されます。また、アラームログが作成された日時や当該装置情報が表示されます。
確認チェックボックスと簡単なメモ入力が可能です。アラーム内容を認識した確認マークの意味や連絡用のコメントなどにご利用ください。
チェックおよびコメントを入力した場合は[ファイル]を選択して保存を選択してください。記入した内容が保存されます。
Note:には最大400文字を保存できます。
表示されたレポートをメニューバーの[ファイル]-[印刷]で印刷できます。
なお、レポートに入力されたコメントは最大10行まで印刷されます。また、確認チェックボックスはチェックがあれば、OKと印字されます。
アラーム削除設定
これを選択することで、次のダイアログが表示されます。閾値監視機能で作成されるアラームログデータの管理保持期限を設定するダイアログです。これで自動的に期間を過ぎたアラームログデータが削除されます。本製品の管理開始時と日替わりを検出した時点で機能が働き、期限を過ぎたデータが削除されます。

0 を指定した場合、自動削除機能は動作しません。
指定期限内にアラームログ数が最大数 1000 に到達した場合は最古のアラームログデータが最新アラームログデータに置き換えられます。最大数 1000 は固定となっています。