ここでは、レプリケーションを運用するための基本操作について説明します。
Symfoware ServerまたはEnterprise Postgresのインスタンスの起動と停止
Linkexpressの起動と停止
レプリケーションサービスの開始と停止
差分ログの取得開始と取得終了
業務の操作
差分ログの操作
Symfoware ServerまたはEnterprise Postgresのインスタンスの起動と停止の操作は、複写元システムと複写先システムの両方で行います。
参照
詳細は、“Symfoware Server 運用ガイド”または“Enterprise Postgres 運用ガイド”を参照してください。
Linkexpressは複写元システムと複写先システムの両方で実施します。
Linkexpressの起動には、以下の方法があります。
![]()
![]() LinuxまたはSolarisの場合
LinuxまたはSolarisの場合
シェルスクリプトによる自動起動
コマンドによる起動
![]() Windowsの場合
Windowsの場合
サービスによる起動
コマンドによる起動
アイコンによる起動
また、Linkexpressの起動オプションにより、以下に示す起動時の状態を選択できます。
前回のレプリケーションの運用を継続して起動する(WARMモード)
レプリケーション運用での推奨モードです
前回のレプリケーションの運用を無効にして起動する(COLDモード)
参照
詳細は、“Linkexpress 導入ガイド”を参照してください。
Linkexpressの停止には、以下の方法があります。
![]()
![]() LinuxまたはSolarisの場合
LinuxまたはSolarisの場合
コマンドによる停止
システム停止時の自動停止
![]() Windowsの場合
Windowsの場合
サービスによる停止
コマンドによる停止
アイコンによる停止
また、Linkexpressの停止オプションにより、以下に示す停止時の状態を選択できます。
実行中の全業務の完了を待って停止する(NORMALモード)。
レプリケーション運用での推奨モードです
実行中の全イベントの完了を待って停止する(QUICKモード)。
実行中の業務・イベントの完了を待たずに停止する(FORCEモード)。
システムをシャットダウンする。
参照
詳細は、“Linkexpress 導入ガイド”を参照してください。
Linkexpressの起動と停止の操作は、複写元システムと複写先システムの両方で行います。
レプリケーション運用での、Linkexpressの起動と停止の推奨モードを以下に示します。
| 起動モード | ||
|---|---|---|---|
WARM | COLD | ||
停止モード | NORMAL | ○ | ○ |
QUICK | ○ | × | |
FORCE | × | × | |
○:レプリケーション運用で推奨します。
×:レプリケーション運用で使用する場合は、起動後に全複写業務を実施する必要があります。
![]() Windowsの場合は、レプリケーションサービスの開始は複写元システムでレプリケーションサービスの開始コマンド(lxrepstrコマンド)、またはWindowsサービスにより実施します。
Windowsの場合は、レプリケーションサービスの開始は複写元システムでレプリケーションサービスの開始コマンド(lxrepstrコマンド)、またはWindowsサービスにより実施します。
レプリケーションサービスの停止は複写元システムでレプリケーションサービスの停止コマンド(lxrepstpコマンド)、またはWindowsサービスにより実施します。
コマンドにより停止する場合はオプションにより、以下に示す停止時の状態を選択することができます。Windowsサービスにより停止する場合はNORMALモードによる停止になります。
NORMALモード(-m n 指定で停止した場合)
トランザクションログテーブルに蓄積されている差分ログの差分ログファイルへの追い出しと、実行中のレプリケーションコマンドの処理が終了してから停止します。ただし、新たなレプリケーションコマンドの実行は受け付けません。通常の運用での推奨モードです。
参照
起動コマンドの詳細は、“コマンドリファレンス”の“lxrepstrコマンド”を参照してください。
停止コマンドの詳細は、“コマンドリファレンス”の“lxrepstpコマンド”を参照してください。
Windowsサービスによる開始または停止については、“Windowsサービスにより行う場合”を参照してください。
ここでは、差分ログの取得開始および取得終了の方法について説明します。
この操作は、複写元システムで行います。
差分ログの取得開始
差分ログの取得終了
参考
Linkexpress、レプリケーションサービス、Symfoware ServerまたはEnterprise Postgresのインスタンスの停止、またはシステムの停止で、差分ログの取得可能状態が解除されることはありません。
Linkexpress、レプリケーションサービス、Symfoware ServerまたはEnterprise Postgresのインスタンスの停止、またはシステムの停止で、トランザクションログテーブルおよび差分ログファイル中の差分ログが削除されることはありません。
以下に、差分ログの取得状態と各コマンドの関係を示します。
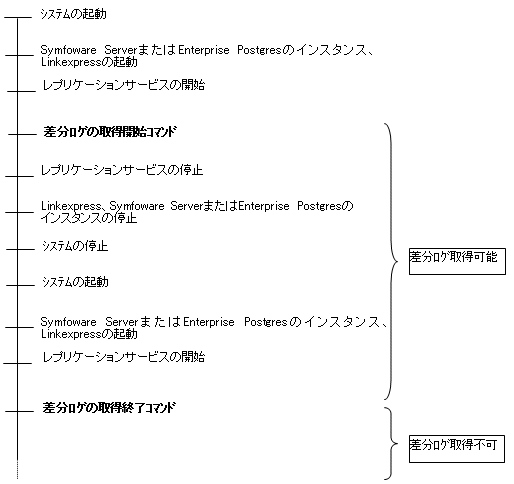
説明
指定した抽出定義またはレプリケーショングループに対して差分ログの取得を開始します。本コマンドを実行すると、差分ログが取得されるようになります。
本コマンドは、レプリケーション運用の対象となる利用者プログラムのトランザクション開始より前に実行します。
操作方法
lxrepena { -r 抽出定義名 | -g レプリケーショングループ名 }
[ -u ユーザ名 [ -w ] ]参照
“コマンドリファレンス”の“lxrepenaコマンド”
説明
指定した抽出定義、またはレプリケーショングループに対する差分ログの取得を終了します。本コマンドを実行すると、差分ログの取得が終了し、差分ログが取得されなくなります。
本コマンドは、実行中のトランザクションが存在する場合、そのトランザクションの終了を待って実行します。
操作方法
lxrepdis { -r 抽出定義名 | -g レプリケーショングループ名 }
[ -u ユーザ名 [ -w ] ]参照
“コマンドリファレンス”の“lxrepdisコマンド”
業務の操作には、以下の方法があります。詳細は、“Linkexpress 運用ガイド”を参照してください。
業務の操作には、以下に示すものがあります。
業務の開始
業務の中止
業務の再開
業務の保留
業務の保留解除
この操作は、押出し型業務(複写元システム主導の業務)の場合は、複写元システムで行い、取込み型業務(複写先システム主導の業務)の場合は、複写先システムで行います。
また、制御サーバから行うこともできます。この場合は、業務サーバ名の指定が必要です。制御サーバについては、“Linkexpress 導入ガイド”を参照してください。
説明
選択したレプリケーション業務を開始します。
開始する業務の業務スケジュールに“随時”または“一定時間間隔繰り返し”が定義されている場合は、本操作が必要です。
“日時”、“週次”、“月次”または“年次”が定義されている場合は、本操作は不要です。
本操作は、処理中の業務に対しては、操作することはできません。
操作方法
説明
選択したレプリケーション業務を中止します。
中止のモードには、以下があります。
通常モード:実行中のイベントが完了した時点で停止します。
強制モード:実行中のイベントの完了を待たずに停止します。
中止した業務は、“業務の開始”により、業務を再開することができます。
本操作は、全複写業務(初期複写業務を含みます)が正常に完了し、複写元データベース、複写先データベースの同期がとれた後に行います。
操作方法
説明
異常完了(中止による異常完了は含みません)により、オペレータの指示待ち状態になっているレプリケーション業務を再実行します。
なお、再開する業務の業務スケジュールに“随時”以外のスケジュールが定義されている場合、それらのスケジュールは有効にはなりません。
再開のモードには、以下があります。
先頭のイベント :業務の先頭から再実行します
異常完了したイベント :異常が発生したイベントから再実行します
異常完了した次のイベント:レプリケーション業務では、使用しないでください
操作方法
説明
選択したレプリケーション業務を一時的に保留します。
保留した業務を再開するには、“業務の保留解除”の操作を行ってください。
操作方法
説明
レプリケーション業務の保留状態を解除し、再開します。
操作方法
ここでは、差分ログに関する操作のうち、以下の操作方法について説明します。
この操作は、複写元システムで行います。
差分ログの破棄
差分ログの追出し
説明
指定した抽出定義またはレプリケーショングループに対する差分ログを、差分ログファイルから削除します。
本コマンドは、指定した抽出定義またはレプリケーショングループに対する差分ログの取得が終了されている状態で実行します。
なお、確定処理が実行される前に中止したレプリケーション業務における、抽出データ格納ファイルも破棄の対象になります。
操作方法
lxreplog -I { -r 抽出定義名 | -g レプリケーショングループ名 }参照
“コマンドリファレンス”の“lxreplog(差分ログの破棄)”
説明
トランザクションログテーブルの差分ログを差分ログファイルに移動します。
通常の運用では、差分ログの追出しは、差分ログ収集スケジュールによって自動的に行われる処理であるため、本コマンドは、主に利用者が利用者プログラムの更新結果を即時に差分ログファイルに書き込みたい場合に使用します。
なお、本コマンドは、抽出定義やレプリケーショングループ定義単位に実行することができますが、データベース名の単位で処理は行われます。そのため、レプリケーション業務内で一定時間ごとに自動で実行するような使用方法は避けてください。
操作方法
lxreplog -F
{ -r 抽出定義名 | -g レプリケーショングループ名 | -a }参照
“コマンドリファレンス”の“lxreplog(差分ログの追出し)”