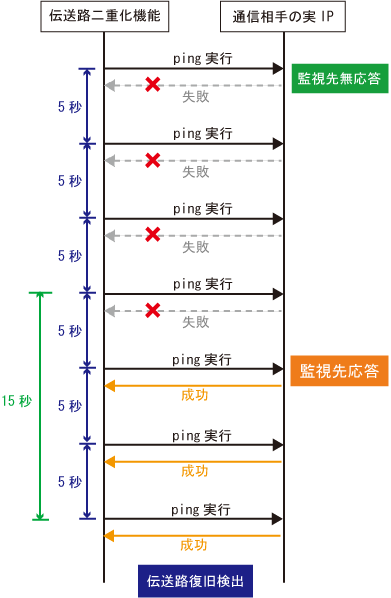GS連携方式では以下の監視先を設定する必要があります。監視先の設定には、hanetobserv createコマンドを使用します。設定方法については“7.15 hanetobservコマンド”を参照してください。
通信相手の仮想IPアドレスと実IPアドレス
クラスタを構成する他ノードの物理IPアドレスと引継ぎ仮想IPアドレス(PCLを使用したクラスタ構成の場合のみ)
1) 通信相手先に対する監視の設定
通信相手の実IPアドレスと仮想IPアドレスを設定します。GLSは設定した実IPアドレスをpingで監視します。また、これらの設定を元に、通信相手とGLS間で仮想IPアドレスを使用した通信を行います。
通信相手先が以下の構成である場合の設定について説明します。
シングル構成の場合
ホットスタンバイ構成の場合(仮想IPが1つの場合)
ホットスタンバイ構成の場合(仮想IPが2つの場合)
ロードシェア構成の場合(すべてのGSで仮想IPが活性化されている場合)
ロードシェア構成の場合(仮想IPが活性化されていないGSがある場合)
注意
通信相手ホストがホットスタンバイ構成の場合
通信相手先の仮想IPアドレスは、標準で4ノード間を移動できます。設定により、最大で16ノード間の移動が可能です。設定方法は、“3.1.2.6 設定項目の上限値”を参照してください。
hanetobservコマンドで通信相手先の仮想IPアドレスと実IPアドレスを登録します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.110.10 -t 192.168.10.10,192.168.20.10 |
設定を確認します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv print [ Standard Polling Parameter ] interval(s) = 5 sec times(c) = 5 times idle(p) = 60 sec repair_time(b) = 5 sec fail over mode(f) = YES Destination Host Virtual Address (Router Address+)NIC Address +----------------+-------------------+--------------------------------+ GS 192.168.110.10 192.168.10.10,192.168.20.10 |
hanetobservコマンドで通信相手先の仮想IPアドレスと実IPアドレスを登録します。-nオプションには、クラスタを構成するノードを設定する場合はノード単位に異なる名前ではなく同じ名前を設定します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.110.10 -t 192.168.10.10,192.168.20.10 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.110.10 -t 192.168.10.20,192.168.20.20 |
設定を確認します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv print
[ Standard Polling Parameter ]
interval(s) = 5 sec
times(c) = 5 times
idle(p) = 60 sec
repair_time(b) = 5 sec
fail over mode(f) = YES
Destination Host Virtual Address (Router Address+)NIC Address
+----------------+-------------------+--------------------------------+
GS 192.168.110.10 192.168.10.10,192.168.20.10
192.168.10.20,192.168.20.20 |
図3.19 ホットスタンバイ構成の場合(仮想IPが2つの場合)
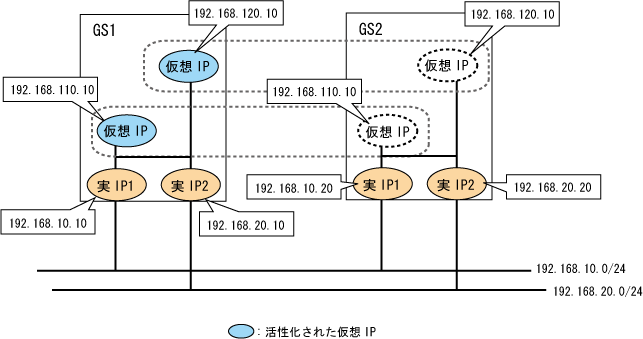
hanetobservコマンドで通信相手先の仮想IPアドレスと実IPアドレスを登録します。-nオプションには、クラスタを構成するノードを設定する場合はノード単位に異なる名前ではなく同じ名前を設定します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.110.10 -t 192.168.10.10,192.168.20.10 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.110.10 -t 192.168.10.20,192.168.20.20 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.120.10 -t 192.168.10.10,192.168.20.10 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.120.10 -t 192.168.10.20,192.168.20.20 |
設定を確認します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv print
[ Standard Polling Parameter ]
interval(s) = 5 sec
times(c) = 5 times
idle(p) = 60 sec
repair_time(b) = 5 sec
fail over mode(f) = YES
Destination Host Virtual Address (Router Address+)NIC Address
+----------------+-------------------+--------------------------------+
GS 192.168.110.10 192.168.10.10,192.168.20.10
192.168.10.20,192.168.20.20
192.168.120.10 192.168.10.10,192.168.20.10
192.168.10.20,192.168.20.20 |
hanetobservコマンドで通信相手先の仮想IPアドレスと実IPアドレスを登録します。各仮想IPアドレスが活性化されているGSの単位で、仮想IPアドレスと物理IPアドレスをペアとして設定します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS1 -i 192.168.100.10 -t 192.168.10.10,192.168.20.10 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS2 -i 192.168.101.10 -t 192.168.10.20,192.168.20.20 |
設定を確認します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv print [ Standard Polling Parameter ] interval(s) = 5 sec times(c) = 5 times idle(p) = 60 sec repair_time(b) = 5 sec fail over mode(f) = NO Destination Host Virtual Address (Router Address+)NIC Address +----------------+-------------------+--------------------------------+ GS1 192.168.100.10 192.168.10.10,192.168.20.10 GS2 192.168.101.10 192.168.10.20,192.168.20.20 |
図3.21 ロードシェア構成の場合(仮想IPが活性化されていないGSがある場合)
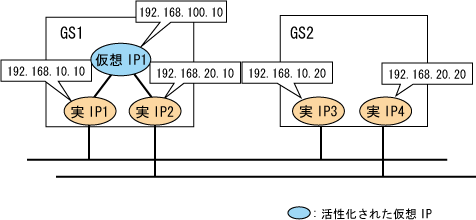
hanetobservコマンドで通信相手先の仮想IPアドレスと実IPアドレスを登録します。活性化されている仮想IPアドレスのうち1つと、活性化されていない仮想IPアドレスをもつGSの物理IPアドレスをペアとして設定します。
なお、1つの仮想IPアドレスに対して、複数台のGSの物理IPアドレスが設定された場合、最初に設定された物理IPアドレスをもつGSが、GLSの通信相手として認識されます。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.100.10 -t 192.168.10.10,192.168.20.10 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n GS -i 192.168.100.10 -t 192.168.10.20,192.168.20.20 |
設定を確認します。
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv print
[ Standard Polling Parameter ]
interval(s) = 5 sec
times(c) = 5 times
idle(p) = 60 sec
repair_time(b) = 5 sec
fail over mode(f) = NO
Destination Host Virtual Address (Router Address+)NIC Address
+----------------+-------------------+--------------------------------+
GS 192.168.100.10 192.168.10.10,192.168.20.10
192.168.10.20,192.168.20.20 |
2) PCLの他ノードに対する監視の設定
自システムがクラスタシステムで運用されている場合、通信相手のGSが停止した際にノード切替えが発生します。この時、hanetobservコマンドにより定義されたすべての監視先から応答がない場合、自システムのNICが故障したと判断しノード切替を行いますが、通信相手のGSがすべて停止した場合についてもすべての監視先が応答を返さなくなり、不要な切替が発生します。このため、運用ノードと待機ノードの双方で、互いに監視を行うことで、すべての相手システムが停止した場合に誤ってノード切替が発生しないようにすることができます。
クラスタ運用時にはhanetobservコマンドで運用ノード、待機ノードの双方で、互いに監視を行うよう設定してください。なお、その場合には、運用ノード、待機ノードの双方で相手ノードを認識させるために、仮想IPアドレスには引継ぎIPアドレスを指定します。
注意
通信相手のGSがすべて停止、かつクラスタの相手ノードが再起動された場合、リソース異常となり、クラスタアプリケーションが停止します。自システムのNICに異常がないときにリソース異常の発生を抑止したい場合、自システムに隣接しているスイッチの管理IPアドレスを監視先として設定してください。
図3.22 クラスタシステム
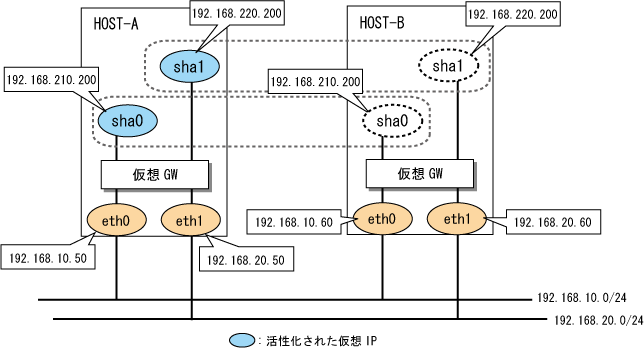
hanetobservコマンドで通信相手先の仮想IPアドレスと実IPアドレスを登録します。-nオプションには、クラスタ構成の他ノードの名前を設定します。
HOST-A上の設定 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n HOST-B -i 192.168.210.200 -t 192.168.10.60,192.168.20.60 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n HOST-B -i 192.168.220.200 -t 192.168.10.60,192.168.20.60 HOST-B上の設定 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n HOST-A -i 192.168.210.200 -t 192.168.10.50,192.168.20.50 # /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv create -n HOST-A -i 192.168.220.200 -t 192.168.10.50,192.168.20.50 |
設定を確認します。
HOST-A上の設定
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv print
[ Standard Polling Parameter ]
interval(s) = 5 sec
times(c) = 5 times
idle(p) = 60 sec
repair_time(b) = 5 sec
fail over mode(f) = YES
Destination Host Virtual Address (Router Address+)NIC Address
+----------------+-------------------+--------------------------------+
HOST-B 192.168.210.200 192.168.10.60,192.168.20.60
192.168.220.200 192.168.10.60,192.168.20.60
HOST-B上の設定
# /opt/FJSVhanet/usr/sbin/hanetobserv print
[ Standard Polling Parameter ]
interval(s) = 5 sec
times(c) = 5 times
idle(p) = 60 sec
repair_time(b) = 5 sec
fail over mode(f) = YES
Destination Host Virtual Address (Router Address+)NIC Address
+----------------+-------------------+--------------------------------+
HOST-A 192.168.210.200 192.168.10.50,192.168.20.50
192.168.220.200 192.168.10.50,192.168.20.50 |
伝送路異常検出シーケンスについて説明します。
GS連携方式では、通信相手ホスト監視機能で設定した通信相手の実IPアドレス、クラスタの他ノードの物理IPアドレスに対してpingを実行します。異常検出までの時間は以下のとおりです。なお、通信相手が先に異常を検出した場合は、ping監視による異常検出を待たずに伝送路が異常になったと判断します。なお、監視時間はhanetobserv paramコマンドで設定を変更できます。設定方法については、“7.15 hanetobservコマンド”を参照してください。
異常検出時間:
異常検出時間 = 監視間隔(秒)×(監視回数 - 1)+ pingのタイムアウト時間(*1)+ (0~監視間隔(秒)) |
*1: 監視間隔が1秒の場合は1秒となり、それ以外の場合は2秒となります。
デフォルトの設定値では以下のようになります。
5秒 × (5回- 1) + 2秒 + 0~5秒 = 22~27秒
図3.23 伝送路異常検出シーケンス
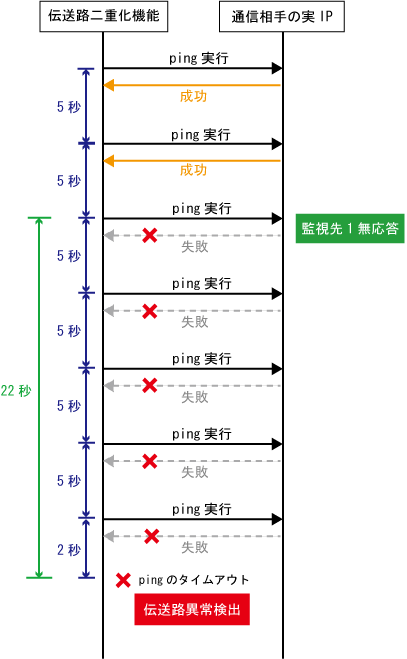
参考
ping監視は監視間隔(秒)で定期的に実行されます。また、監視先が故障してから次のpingが実行されるまで、最大で監視間隔(秒)必要です。このため、故障発生時から検出までの時間は最短で22秒、最長で27秒となります。
アプリケーションがネットワークを監視する場合、GLSが経路を切り替えるまでに異常を検出しないよう監視時間を調整してください。
伝送路の異常監視を開始した直後または復旧監視から異常監視に切り替わった直後は、リンクアップ待ち時間が経過するまで異常検出を待ち合わせます。
注意
実行したpingが30秒間無反応になった場合、pingのハングアップとして検出し、リトライを行わずに伝送路が異常になったと判断します。
伝送路復旧検出シーケンスについて説明します。
GS連携方式では、通信相手ホスト監視機能で設定した通信相手の実IPアドレスに対してpingを実行します。伝送路異常を検出後、GLSは伝送路の復旧を監視するためにpingによる復旧監視を行います。復旧検出までの時間は以下のとおりです。なお、通信相手が先に復旧を検出した場合は、ping監視による復旧検出を待たずに伝送路が復旧したと判断します。なお、監視時間はhanetobserv paramコマンドで設定を変更できます。設定方法については、“7.15 hanetobservコマンド”を参照してください。
復旧検出時間:
復旧検出時間 = 復旧監視間隔(秒)+ 復旧監視間隔(秒)×リトライ数(回) + (0~復旧監視間隔(秒)) |
デフォルトの設定値では以下のようになります。
5秒 × 0回 + 0~5秒 = 0~5秒
リトライ数を2回に設定した場合、以下のようになります。
5秒 × 2回 + 0~5秒 = 10~15秒
図3.24 伝送路復旧検出シーケンス(リトライ数(2回)の場合)