マルチシステム機能を使用する場合の、コンポーネントトランザクションサービスの運用方法について、デフォルトシステムと拡張システムの違いを説明します。
拡張システムの運用を行う場合、コンポーネントトランザクションサービスが提供するコマンドに対象のシステム名を-Mオプションで指定します。-Mオプションに指定するシステム名は、iscreatesysコマンドで指定したシステム名を入力します。
また、コマンドを投入する場合に、環境変数“IS_SYSTEM”にシステム名を設定しておくことで、-Mオプションを指定しなくても、拡張システムに対する操作を行うことができます。両方が指定された場合は、-Mオプションの指定が有効となります。
拡張システムの運用時に-Mオプションが必要となるコマンドを以下に示します。
■コンポーネントトランザクションサービス運用コマンド
コンポーネントトランザクションサービス運用コマンドで“-M 拡張システム名”を指定すると、拡張システムのコンポーネントトランザクションサービス運用およびその資源に対して、運用/操作を行います。
コンポーネントトランザクションサービス運用コマンドの詳細(-Mアプションの有無など)については、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。
■ワークユニット管理コマンド
ワークユニット管理コマンドで“-M 拡張システム名”を指定すると、拡張システムのワークユニットの運用およびその資源に対して、運用/操作を行います。
ワークユニット管理コマンドの詳細(-Mアプションの有無など)については、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。
■性能分析コマンド
性能分析コマンドで“-M 拡張システム名”を指定すると、拡張システムの性能分析の運用およびその資源に対して、運用/操作を行います。
性能分析コマンドの詳細(-Mアプションの有無など)については、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。
■アプリケーション開発コマンド(tdcコマンド)
tdcコマンドで“-M 拡張システム名”を指定すると、拡張システムのトランザクションアプリケーションのIDLコンパイルを行います。
tdcコマンドの詳細については、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。
■クラスタサービス運用コマンド
クラスタサービス運用コマンドで“-M 拡張システム名”を指定すると、拡張システムのクラスタサービス、およびその資源に対して、運用/操作を行います。
クラスタサービス運用コマンドの詳細については、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。
■バックアップ・リストアコマンド(コンポーネントトランザクションサービス関連)
バックアップ・リストアコマンドで“-M 拡張システム名”を指定すると、拡張システムのコンポーネントトランザクションサービスの資源に対して、運用/操作を行います。
バックアップ・リストアコマンドの詳細(-Mアプションの有無など)については、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。
■トレース・スナップの採取/出力コマンド(コンポーネントトランザクションサービス関連)
トレース・スナップの採取/出力コマンドで“-M 拡張システム名”を指定すると、拡張システムのコンポーネントトランザクションサービスの資源に対して、運用/操作を行います。
トレース・スナップの採取/出力コマンドの詳細(-Mアプションの有無など)については、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。
マルチシステム機能を利用し、システム間でサーバアプリケーション間連携機能を使用する場合の運用手順を以下に示します。サーバアプリケーション間連携機能を使用する場合、クライアントから要求を受信して、他サーバアプリケーションに要求を送信する“中継役”のアプリケーションのことを、“中継アプリケーション”と呼び、中継アプリケーションが呼び出す先のアプリケーションを、“中継先アプリケーション”と呼びます。
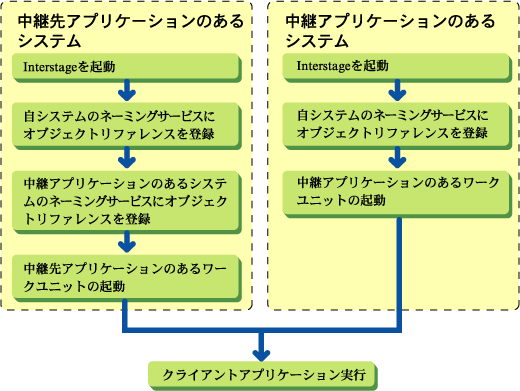
共にtype1で初期化されたシステム間において、サーバアプリケーション間連携機能を使用する場合には、中継するシステムのCORBAサービスのネーミングサービスに中継先のオブジェクトリファレンスを登録する必要があります。
以下に、拡張システムに中継アプリケーション、デフォルトシステムに中継先アプリケーションを配置するモデルを例に、ネーミングサービスへのオブジェクトリファレンスの登録例を示します。
拡張システムのネーミングサービスへの登録
(中継アプリケーションのオブジェクトリファレンス)
OD_or_adm -c IDL:Mod1/INTF1:1.0 -a FUJITSU-Interstage-TDLC -h exphost -p expport -n nameA -M expsys |
拡張システムのネーミングサービスへの登録
(中継先アプリケーションのオブジェクトリファレンス)
OD_or_adm -c IDL:Mod2/INTF2:1.0 -a FUJITSU-Interstage-TDLC -h defhost -p defport -n nameB -M expsys |
デフォルトシステムのネーミングサービスへの登録
(中継先アプリケーションのオブジェクトリファレンス)
OD_or_adm -c IDL:Mod2/INTF2:1.0 -a FUJITSU-Interstage-TDLC -h defhost -p defport -n nameB |
上記は以下の場合の例
中継アプリケーションのモジュール名 | Mod1 |
中継先アプリケーションのモジュール名 | Mod2 |
中継アプリケーションのインタフェース名 | INTF1 |
中継先アプリケーションのインタフェース名 | INTF2 |
拡張システム名 | expsys |
バージョン | 1.0 |
中継アプリケーションが存在するシステムのホスト名 | exphost |
中継アプリケーションが存在するシステムのポート番号 | expport |
中継先アプリケーションが存在するシステムのホスト名 | defhost |
中継先アプリケーションが存在するシステムのポート番号 | defport |
中継アプリケーションのネーミングサービスへ登録する名前 | nameA |
中継先アプリケーションのネーミングサービスへ登録する名前 | nameB |
![]()
中継する先のアプリケーションがAIM連携用のアプリケーションである場合には、OD_or_admコマンドに指定するインプリメンテーションリポジトリIDには以下を設定する必要があります。
FUJITSU-Interstage-TDRC |
マルチシステム機能使用時には、特に意識することはありません。
クライアントは処理要求を行うサーバのIPアドレスと、ポート番号を従来とおり設定することで、プロセスバインド機能が使用できます。
![]()
IPCOMを利用した連携は利用できません。
ワークユニット定義は、各システム間で共用することも可能です。ただし、実際のサーバアプリケーションの配置を同一にすると、片方のシステムで業務を運用している場合に、もう片方のサーバアプリケーションの修正などを行うことができません。
運用中のサーバアプリケーションの削除、変更を行うと運用中の業務のプロセスが異常終了します。
このため、両方のシステムを同時に運用するような形態のシステム構成を採る場合以外は、ワークユニット定義のアプリケーションの格納ディレクトリを示す、ステートメントを変更する必要があります。
この場合、事前にアプリケーションを格納するディレクトリをシステム単位に分割しておくことを推奨します。
拡張システム運用時のワークユニットのカレントディレクトリは以下のような構成になっており、標準出力と標準エラー出力が設定されます。
カレントディレクトリ:xxx/yyy.システム名/zzz |
拡張システム運用時のコンポーネントトランザクションサービスのエラーログは、以下のファイルに採取されます。
/var/opt/FJSVisas/system/システム名/FSUNtd/trc/lorb/errlog0 |