資源管理機能は、Interstage Information Storageへ格納されたデータの管理を行う機能です。
Interstage Information Storageへロード機能にてデータを格納する際に、管理レコード(ファイル名,所在,有効期間など)を資源管理に登録します。登録された管理レコードはデータを抽出する際に、抽出対象となるファイルを限定するために使用されます。抽出時にアクセスするファイルを限定することで、抽出効率を高めます。その他運用機能として、登録したデータの削除や管理レコードの変更などが行えます。
図3.17 資源管理機能
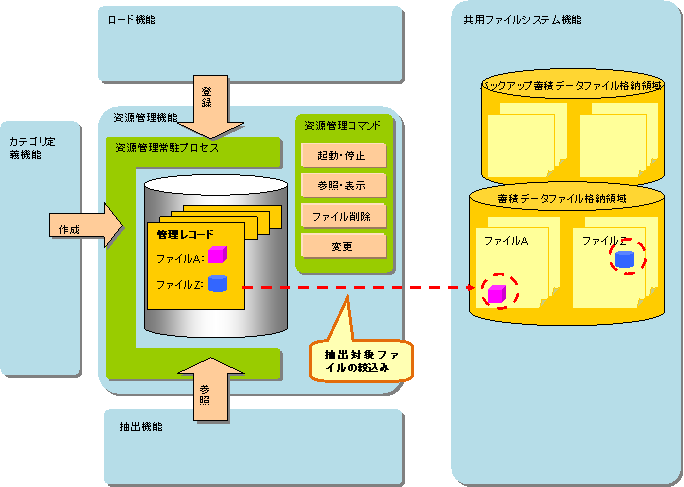
資源管理機能の主な機能には、以下があります。
資源管理常駐プロセスの起動・停止
蓄積データファイルの管理状態の登録
データ抽出時のファイル自動選択
蓄積データファイルの削除
蓄積データファイル管理状態の操作
蓄積データファイル作成中状態解除
資源管理常駐プロセスの動作状況表示
カテゴリ定義の参照
資源管理報と蓄積データファイルの不整合検出
資源管理常駐プロセスは抽出制御機能からファイル選択依頼の受付および抽出制御機能へのファイル選択結果の返却を行います。
資源管理常駐プロセスの起動方法は“導入ガイド”の“6.9.1 資源管理常駐プロセスの起動/停止確認”を参照してください。資源管理常駐プロセスの停止は終了指示コマンドを実行します。
資源管理常駐プロセスを停止させる方法には以下の2つの方法があります。
実行中の処理と待ち状態の処理がすべて完了してから終了します。
実行中の処理が完了した時点で終了します。待ち状態の処理はすべて破棄されます。
参考
「待ち状態」とは、資源管理常駐プロセスへの要求のうち、資源管理常駐プロセスの処理を待っている状態を指します。
ロード機能によって蓄積データファイルを作成すると同時に、資源管理に管理レコードを登録します。ここでは、ロード時に資源管理に登録される情報について、記述します。
データ格納時に登録される管理レコードの情報は主に以下です。
資源管理で管理されるファイル名です。カテゴリ定義時に定義したファイル名付与基準に基づいてファイル名が付与されます。ファイルの格納先も同時に管理します。
蓄積データファイルがロード機能によって作成され、管理レコードとして登録された日時です。
保存期限
蓄積データファイルを管理する最終日時です。この日時を経過したファイルは、蓄積データファイル削除コマンドによって削除が可能になります。また、保存期限を経過したファイルは抽出対象になりません。
蓄積データファイルをデータ抽出の対象とする開始日時です。データ抽出の実行時にこの日時に達していない蓄積データファイルは抽出対象となりません。
蓄積データファイルをデータ抽出の対象とする終了日時です。データ抽出の実行時にこの日時を経過した蓄積データファイルは抽出対象となりません。参照可能開始日時から参照可能終了日時の期間を参照可能期間と呼びます。
蓄積データファイルのバックアップファイル名です。カテゴリ定義時に定義したファイル名付与基準に基づいてファイル名が付与されます。ファイルの格納先も同時に管理されます。
抽出時のファイル絞込みのために蓄積データファイルのデータ中のCPMキー項目値の範囲を管理します。
注意
登録する日時項目には「ファイル登録日時≦参照可能開始日時<参照可能終了日時≦保存期限」の関係があります。
CPMキーを定義したカテゴリへのロードと同様の情報が登録されます。
ただし、CPMキーを持たないため、CPMキー値範囲の情報は登録されません。
抽出条件式にCPMキー項目を含んでいてもカテゴリに定義したCPMキーの属性と抽出条件式の書式が一致しない場合、ファイル選択は行われません。全てのファイルが抽出対象となります。
資源管理機能では、データ抽出時に蓄積データファイル名が指定されていない場合、抽出対象とするファイルを自動選択します。自動選択される対象は、資源管理で管理されている蓄積データファイルのうち、参照可能期間にあるファイルです。カテゴリ名および、抽出条件をもとに、抽出対象ファイルを自動選択します。
指定されたカテゴリがCPMキーを定義したカテゴリの場合、検索条件から抽出対象ファイルを自動選択します。
指定されたカテゴリがCPMキーを定義していないカテゴリの場合、全ての蓄積データファイルを抽出対象とします。
また、データ抽出時に蓄積データファイル名が指定された場合は、CPMキーの定義の有無を問わずに指定された蓄積データファイルを抽出対象とします。
抽出対象となるファイルの指定有無とカテゴリの管理形式によって、下表の通りに抽出対象ファイルの自動選択が行われます。
抽出対象ファイルを指定する | 抽出対象ファイルを指定しない | |
|---|---|---|
CPMキーを定義したカテゴリ | 指定されたファイルが抽出対象となります。 | ◎ 資源管理に登録されているファイルから抽出条件をもとにファイルを自動選択し、抽出対象とします。 |
CPMキーを定義していないカテゴリ | 指定されたファイルが抽出対象となります。 | 資源管理に登録されている全ファイルを選択し、抽出対象とします。 |
ここでは、CPMキーを定義したカテゴリにおける抽出対象ファイルの自動選択(上表の◎部)の詳細について記述します。
なお、条件式の記述方法は"アプリケーション開発ガイド"の“第3章 条件の書式”を参照してください。
ファイル自動選択に使用される抽出条件
抽出対象ファイルの自動選択では抽出条件に指定されたCPMキー項目に対する条件式からファイルを自動選択します。
抽出対象ファイルの自動選択を使用するためには、抽出条件にCPMキー項目に対する条件が含まれる必要があります。資源管理機能は、CPMキー項目に対する条件と資源管理上の管理レコードから、抽出対象となるファイルを自動的に選択します。
ただし、抽出条件にCPMキーが含まれない、もしくは含まれていても自動選択できない条件構文の場合、資源管理に登録されている指定されたカテゴリの全ファイルが抽出対象として選択されます。
CPMキー項目に対する条件によって管理レコードからファイルの絞り込みを行える場合、ファイルの自動選択が有効になります。
例1
CPMキー項目:作成日
抽出条件:作成日が“20090601”かつ、従業員番号が “FJ123456”
図3.18 例1 自動選択が有効となり、ファイルが自動選択される場合(ファイルCが選択されてる)
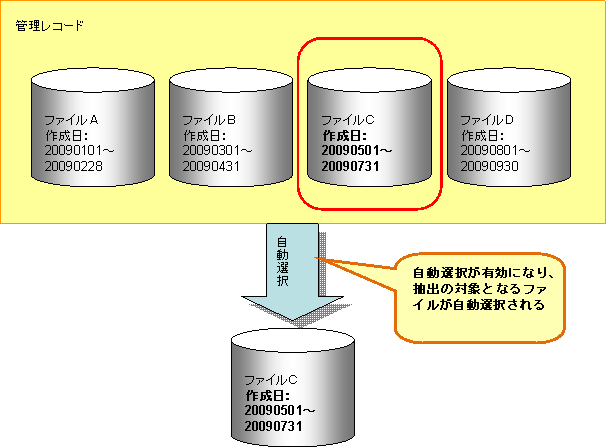
「AND」条件で絞込みが行え、管理レコードに登録されているCPMキー項目「作成日」と抽出条件式に記述した項目「作成日」が一致したため、自動選択が有効となります。抽出条件式に指定したCPMキー項目「作成日」がファイルCのCPMキー項目「作成日」の範囲内に該当したため、ファイルCが選択されます。
例2
CPMキー項目:作成日
抽出条件:作成日が“20091015”かつ、従業員番号が “FJ123456”
図3.19 例2 自動選択が有効となり、ファイルが自動選択される場合(対象ファイルなし)
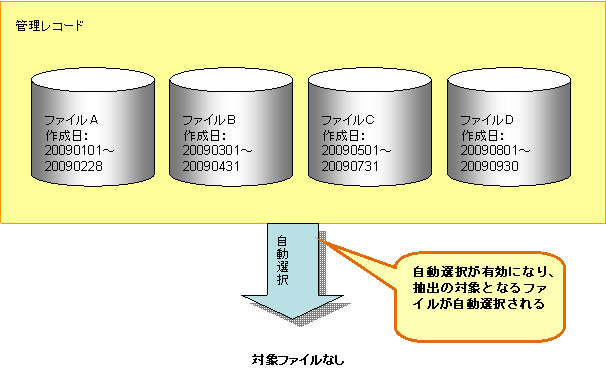
「AND」条件で絞込みが行え、管理レコードに登録されているCPMキー項目「作成日」と抽出条件式に記述した項目「作成日」が一致したため、自動選択が有効となります。抽出条件式に指定したCPMキー項目「作成日」がファイルA~DのCPMキー項目「作成日」の範囲内に該当しなかったため、自動選択の結果は対象ファイルなし、となります。
ファイルの自動選択で限定ができない抽出条件の例
CPMキーに対する条件によって管理レコードからファイルが絞り込めない場合、カテゴリに登録されている全ての蓄積データファイルが抽出対象となります。
例
CPMキー項目:作成日
抽出条件:作成日が“20090601”または、従業員番号が “FJ123456”
図3.20 例 自動選択でファイルが限定できず、全ファイル選択となる場合
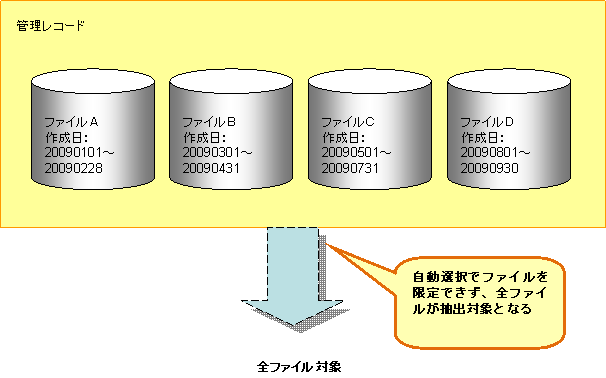
「OR」条件でCPMキー項目と他項目が指定されているために、絞込みが行えなかったため、自動選択が有効とならず、全ファイルが対象となります。
カテゴリに定義したCPMキーの属性と条件式の関係を、以下に示します。
文字列属性のCPMキー
文字列属性のCPMキーに対してファイル自動選択に使用される条件式は、「文字列」、または「パターン」比較の条件式です。「数値」比較の条件式は使用されません。
数値属性のCPMキー
数値属性のCPMキーに対してファイル選択に使用される条件式は、「数値」比較の条件式です。「文字列」、または「パターン」比較の条件式にはファイル選択は使用されません。
CPMキーの属性と条件式の関係を示します。
CPMキーの属性 | 比較演算子 | 種類 |
|---|---|---|
文字列または、パターン | ==、!== | 完全一致 |
=、!= | 部分一致(演算子前方一致指定の場合) | |
<、<=、>、>= | 大小比較 | |
数値 | =、!= | 完全一致 |
<、<=、>、>= | 大小比較 |
注意
前述したCPMキーに対する抽出条件であっても、複数の条件がANDやORで組み合わされ、かつ否定形で記述されている形式はファイルの自動選択が行われない場合があります。
例
NOT (CPMキー1に対する条件 AND CPMキー2に対する条件)
CPMキー1に対する条件 AND NOT (CPMキー2に対する条件 OR CPMキー以外に対する条件)
自動選択を行えない場合は、カテゴリに登録されている全ファイルが抽出対象となります。
資源管理に登録された蓄積データファイルが不要になった場合には、蓄積データファイル削除コマンドを使用して削除します。蓄積データファイル削除コマンドを実行することで、蓄積データファイルを物理的に削除します。蓄積データファイルが削除されると、対応する管理レコードは「削除済み」状態に変更されます。
参照
蓄積データファイルの削除方法は“運用ガイド”の“1.6 データの削除”を参照してください。
蓄積データファイル削除には、大きく以下の二種類があります。
保存期限満了後のファイル削除
保存期限を満了した蓄積データファイルおよびバックアップファイルを削除します。
ポイント
蓄積データファイル格納先領域の枯渇を回避するために、保存期限を経過した蓄積データファイルを定期的に削除する運用を推奨します。
個別指定のファイル削除
蓄積データファイル名、格納先領域、登録日を利用者が指定して蓄積データファイル及びバックアップファイルを削除します。誤ってデータ格納してしまった場合などに使用します。
保存期限満了後のファイル削除は、保存期限を満了した蓄積データファイルおよびバックアップファイルを削除します。
削除の指定には、以下の2つがあります。
保存期限の満了日時指定による削除
指定した日時以前に保存期限が満了している蓄積データファイルを削除します。
日時を指定しなかった場合、蓄積データファイル削除コマンド実行時以前に保存期限が満了している蓄積データファイルを削除します。
カテゴリ定義時に「バックアップ蓄積データファイルの同時削除」が定義されている場合、バックアップファイルも同時に削除されます。
注意
バックアップ蓄積データファイルの同時削除を行わない場合、残ったバックアップの削除は個別指定のファイル削除でのみ削除可能です。
例
削除実行日時: 2009/09/30/00:00:00
削除対象カテゴリ:CATA
削除条件:保存期限が2008/11/30/00:00:00以前のファイルを削除
図3.21 例 保存期限の満了日時指定による削除
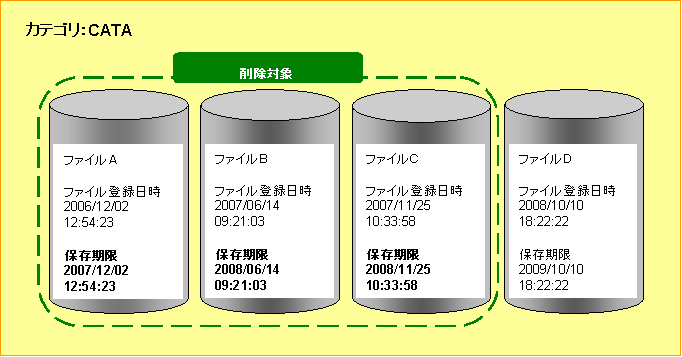
ファイル登録日時指定による削除
指定した日時以前に資源管理に登録された蓄積データファイルの内、既に保存期限が満了しているファイルを削除します。
このとき、カテゴリの「バックアップ蓄積データファイルの同時削除」の設定は無視されます。バックアップ蓄積データファイルを同時に削除するかを実行時のパラメタで指定してください。
例
削除実行日時: 2009/09/30/00:00:00
削除対象カテゴリ:CATA
削除条件:2008/11/30/00:00:00以前に登録された、かつ保存期限を満了しているファイルを削除
図3.22 例 ファイル登録日時指定による削除
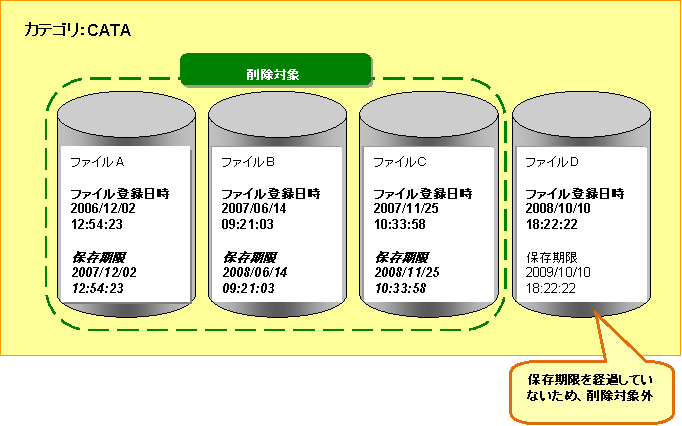
「保存期限満了後のファイル削除」は、保存期限を満了している蓄積データファイルが削除されますが、個別指定のファイル削除は、保存期限を満了しているかどうかに関わらず削除されます。
このとき、カテゴリの「バックアップ蓄積データファイルの同時削除」の設定は無視されます。バックアップ蓄積データファイルを同時に削除するかを実行時のパラメタで指定してください。
注意
保存期限を満了していない蓄積データファイルを削除する場合は、ロード及び抽出で使用されている蓄積データファイルを削除しないように十分に注意してください。
資源管理に誤って登録してしまった場合以外は「保存期限満了後のファイル削除」を使用してください。
個別指定のファイル削除は実行時に指定された以下の3つの条件をもとに削除を行います。なお、各条件は省略可能ですが、最低1つは指定しなければなりません。また、各条件を組み合わせて指定した場合には、全ての条件を満たす蓄積データファイル及びバックアップファイルが削除されます。
蓄積データファイル名(複数指定可)
資源管理に登録された日時(指定された日時以前を削除)
蓄積データファイルの格納領域(ディレクトリ)
資源管理機能では、蓄積データファイルごとの管理レコードを管理しています。管理レコードで管理される蓄積データファイルの状態を資源管理状態と呼びます。また、これらの情報は資源管理にて管理されます。
図3.23 資源管理状態
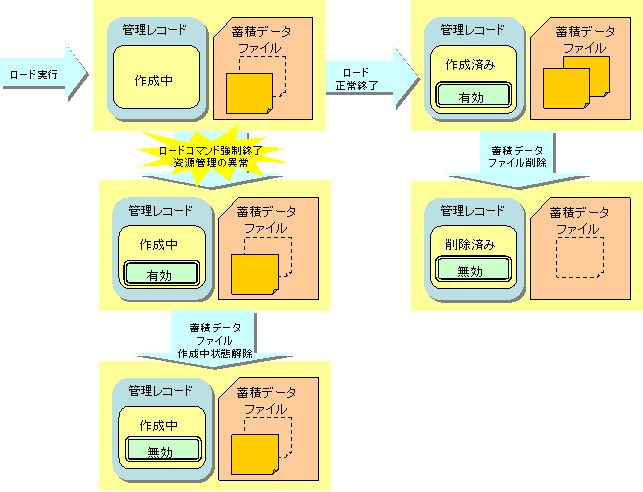
ロード機能の実行が正常に終了すると、管理レコードの状態は有効状態となります。
蓄積データファイルの削除を実行すると、管理レコードの状態は削除済み状態になります。
資源管理状態変更コマンドは「削除済」や「無効」状態の管理レコードの削除、管理レコードの内容変更を行います。
資源管理状態変更コマンドには、以下の種類があります。
管理レコードの削除
削除済レコードの削除
無効レコードの削除
蓄積データファイル管理期限の変更
保存期限の変更
参照可能終了日時の変更
蓄積データファイル及びバックアップファイルの削除後、削除済状態となった管理レコードや、蓄積データファイル作成中状態解除コマンドにより無効状態となった管理レコードを削除します。
無効化された管理レコードが多いと、「データ抽出時のファイル選択や蓄積データファイルの管理状態の登録などの処理性能劣化」や「管理領域の枯渇」などのトラブルが発生します。
また蓄積データファイルの管理状態が「削除済状態」や「無効状態」であっても、管理レコードが残っている状態では、該当する管理レコード上と同じ蓄積データファイル名でのロードは行えません。
これらを回避するために、定期的に管理レコードの削除を実施する運用を推奨します。
管理レコードの削除には、以下の2つがあります。
管理状態が有効状態である蓄積データファイルの保存期限および参照可能終了日時をファイル単位に変更します。
以下の場合に、本機能を使用します。
参照可能終了日時を延長する必要がある場合
参照可能終了日時を短縮する必要がある場合
参照可能終了日時の設定を解除する必要がある場合(無期限に設定)
保存期限を延長する必要がある場合
保存期限を短縮する必要がある場合
保存期限の設定を解除する必要がある場合(無期限に設定)
注意
「ファイル登録日時≦参照可能開始日時<参照可能終了日時≦保存期限」の関係を保持した変更のみ可能です。
ロード処理中に、「ロード機能プロセスのダウン」などの予期しないトラブルが発生すると、資源管理機能に登録された管理レコードが不完全な状態になってしまうことがあります。
蓄積データファイル作成中状態解除コマンドは、データ格納時の管理レコードの状態確認および不完全な管理レコードを無効化します。
ロード機能は、管理レコードを登録する直前にシステムログに「排他獲得番号」および「排他獲得日時」を出力します。
「排他獲得番号」および「排他獲得日時」を蓄積データファイル作成中状態解除コマンドに指定することで、障害となったロードに対する管理レコードの「状態確認」および「無効化」を行います。
注意
本コマンドは管理レコードを「無効化」するのみであり、作成途中の蓄積データファイルやバックアップファイルの実体は、利用者がOSのコマンドなどで削除する必要があります。
無効化状態であっても同一名の蓄積データファイルのロードは行えないため、同一名での蓄積データファイルの再ロードが必要な場合には、事前に無効レコードの削除が必要となります。
本処理は、トラブルの原因を取り除いた後に実行してください。
資源管理常駐プロセスは、「データ抽出時のファイル自動選択処理」を行っています。この常駐プロセスの動作状況は稼働状況表示コマンドで確認できます。また、稼働状況表示コマンドを実行し、正常に資源管理常駐プロセスの処理状況が表示されることで、資源管理常駐プロセスの起動確認を行うことができます。
カテゴリ定義情報の参照は、カテゴリ定義参照コマンドで確認することができます。定義情報を参照したいカテゴリ名を指定し、カテゴリ定義参照コマンドを実行すると、定義されているカテゴリ情報が標準出力に出力されます。出力されるカテゴリ定義情報は「カテゴリ情報」、「領域情報」です。
カテゴリ情報は主に以下の情報を表示します。
データ形式(XMLまたはCSV)
バックアップ取得設定情報
保存期限の設定情報
蓄積データファイルのファイル名構成情報
CPMキーの定義情報
領域情報は主に以下の情報を表示します。
蓄積データファイルの作成先領域と有効期間
バックアップファイルの作成先領域と有効期間
参照
表示項目の詳細については、“コマンドリファレンス”の“dcccat”を参照してください。
Interstage Information Storageで管理しているデータにトラブル(ディスクの一部故障など)が発生した場合、資源管理で管理している蓄積データファイルの情報と蓄積データファイルに不整合が生じてしまうことがあります。
蓄積データファイルの不整合検出コマンドは、管理レコードと蓄積データファイルの不整合を確認することができます。
参照
詳細については、“運用ガイド”の“3.7.1 不整合検出コマンドによる不整合の検出”を参照してください。