ファイル受信について説明します。
ファイル受信は、他システムにあるファイルを収集する場合に、利用する機能です。
ファイル受信には、ファイル受信(自局主導)、ファイル受信(他局主導)の2種類の収集方法があります。
ファイル受信の対象環境については、“4.2 相手側システムの接続について”を参照してください。
ファイル受信(自局主導)
Information Integratorから、業務システム(収集元システム)にあるファイルを収集します。
情報活用システム(配付先システム)のスケジュールに合わせて、必要な情報を持ってくる場合に、利用します。例えば、情報活用システム側が、毎朝時点での最新情報を保持しておくことが必要な場合、ファイル受信から、配付先システムに到達する時間を計算し、ファイル受信するスケジュールを指定します。
図1.3 ファイル受信(自局主導)
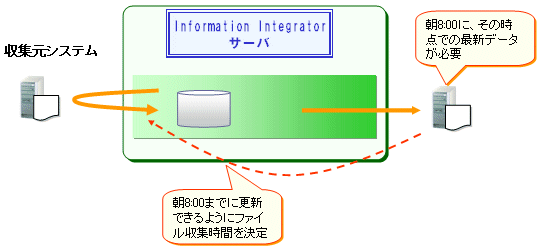
ファイル受信(自局主導)は、複数の収集元システムにあるファイルを収集することができます。
図1.4 複数の収集元システムからファイルを収集する場合
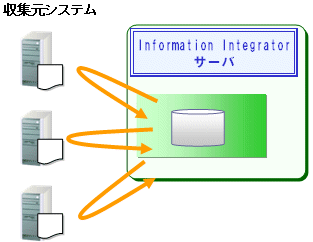
ファイル受信(他局主導)
収集元システムから送られてくるファイルを、Information Integratorで監視し、送られてきたことを確認してから、後続処理を実行します。
ファイル受信(他局主導)は、収集元システムの運用スケジュールに合わせて、処理を実行できることが特長です。例えば、ファイル受信(他局主導)は、複数の収集元システムから送られてくるデータが揃うのを待つ、または1つの収集元システムから複数のファイルの受信を待つ場合などに利用します。
ファイル受信(他局主導)を利用することで、以下のような運用ができます。
収集元システムの運用スケジュールに合わせて処理を実行
収集元システムで必要なデータの準備ができてから、Information Integratorにファイルを送付します。収集元システムで生成される最新のデータを、随時処理できます。
図1.5 収集元システムの運用スケジュールに合わせて処理を実行するパターン
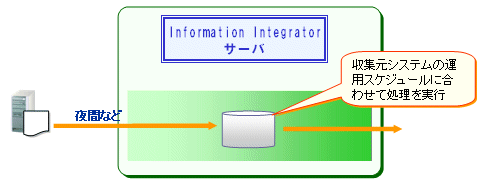
ファイルの受け取り状況に合わせて後続処理を実行
必要なデータは、収集元システムで準備ができ次第送付し、Information Integratorは、自身の運用スケジュールに合わせて、処理を実行します。最新のデータを受信しつつ、配付先システムの運用に合わせて、データを送付することができます。
また、複数の拠点からのデータを収集する場合や、結合して利用するファイル同士を収集する場合にも利用できます。
図1.6 ファイルの受け取り状況に合わせて後続処理を実行するパターン
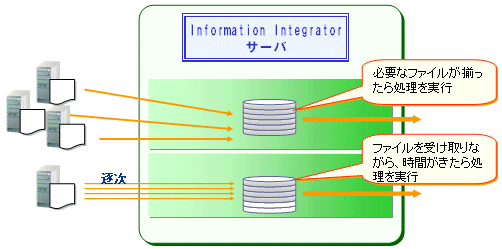
圧縮・解凍
ファイル送受信の転送時間は、転送データのサイズに比例します。大規模データの転送や、回線速度の遅いネットワークを利用する転送では、転送時間の増加が顕著になります。
このような場合、ファイルを圧縮、転送後に解凍することで、ネットワーク上に流すデータ量を削減し、転送時間を短縮することができます。
Information Integratorでは、ファイル送受信と連動して自動的に圧縮・解凍します。
圧縮・解凍は、データの転送時間を短縮することが目的です。データ圧縮、解凍の処理速度より、転送速度の方が遅い回線を利用している場合に指定してください。また、転送するデータがすでに圧縮されている場合は、データ圧縮を行わないで転送してください。
多重度制御
ファイル送受信、相手側ジョブ起動、ジョブ結果通知を行うことによるシステムおよび通信パス単位での回線の同時使用数のことを転送多重度と呼びます。Information Integratorは、この転送多重度の上限値を設定できます。
多くの相手システムとファイル送受信を同時多重実行する場合、Information Integratorサーバの負荷増大に伴いプロトコル応答電文の通知が遅延します。これにより、相手側システムでタイムアウトエラーやネットワークエラーを検出し、ファイル送受信異常が多発する場合があります。多重度制御で同時処理するファイル送受信数を制限することで、受付済みのファイル送受信の応答遅延を防止することができます。
また、HULFTを利用する場合の転送多重度は、HULFT製品の設定に従います。